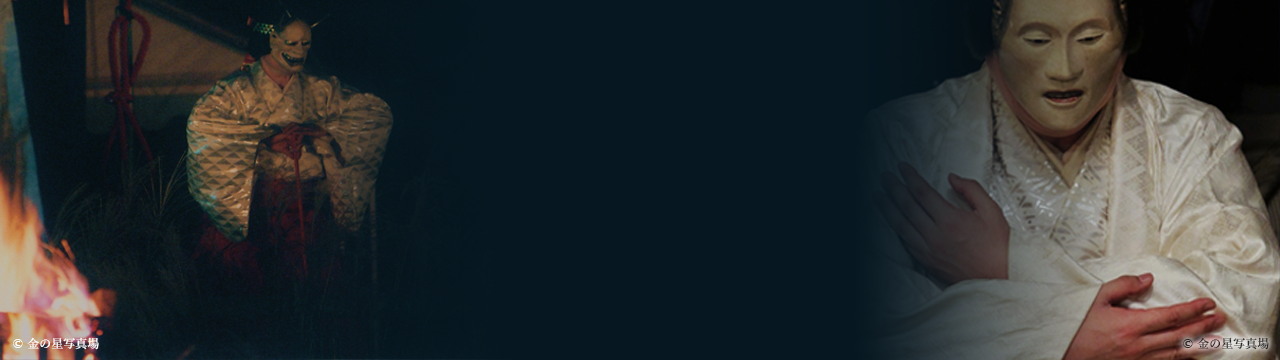太田 直道
太田直道 プロフィール
1946年大阪府に生まれる。仙台市在住。
1969年京都大学文学部卒。宮城教育大学名誉教授。文学博士。ドイツ哲学を研究。
40歳の頃より能を金春流79世宗家金春信高、80世宗家金春安明に師事。
公益社団法人能楽協会会員。
東日本大震災の頃より『源氏物語』に傾倒。
著書に『人間の時間ー時間の美学試論』他。
2023年9月29日
金春安照伝書を読む ――能の詞花を訪ねて32
金春安照(八郎禅曲)(天文18年(1549年)−元和7年(1621年))は、織豊時代から江戸時代初期にかけて、豊臣秀吉と徳川家康の手厚い庇護のもとに活躍した金春流の黄金期の大夫である。彼は天正13年(1586年)に大和国の大名であった豊臣秀長に厚遇され、豊臣家と結びついた。秀吉は後年能に耽溺したことで知られているが、彼の絶大な庇護を受けて、能が支配層の芸術として不動の地位を確立するとともに、金春流がその筆頭となり栄華の頂点に立ったのであった。秀吉が名護屋に滞在した時にも召し抱えられ、のちに家康にも厚遇された彼は、文字通り能楽大夫の頂点の栄華を身に受けたのであるが、彼自身はこのような世の栄光に安んじることなく、むしろストイックなまでに芸道一筋に励んだであろうことは、彼の伝書からも伺える。『当代記』に「今の世には今春八郎大夫(安照)に昔残りけるか」と評価されたように、彼はこの栄華の境遇にあって伝統的で正当な能をひたすら追求したのであった。
能楽の精神と技法を説く理論作業は禅竹から後の時代では概して活発ではないが、禅鳳や安照らの主として金春座の大夫たちによって担われてきたということができる。安照は禅竹から数えて六代目の大夫であるが、禅竹の「六輪一露」の説、禅鳳の風流に見られる舞台演技論を受け継ぎつつ、彼らとも趣を異にする独自の能楽論を打ち立てた(尤も、安照には体系的な理論書というものがなく、弟子筋に相伝として与えられた数種の秘伝書が残されているのみである)。
安照の伝書には、「秘伝書上」と称される「能の技術面に関する多様な記事が不統一に寄せ集められ」た比較的簡略な冊子(慶長十一年(1606年))と、無題のより大部の三冊の伝書(表章等によって『金春安照能伝書 甲本、乙本、丙本』と名づけられた)などがある(『金春安照伝書集』表章・小田幸子校訂、法政大学能楽研究所編 能楽資料集成9、わんや書店)。そのうち、安照の理論ともいうべき「真(心、安照は「真」と「心」をほぼ同意に用いている)の理論」と「心法修行論」が展開されるのは「乙本」と「柄本」である。このことについて、小田幸子は次のように述べている(「金春安照の能楽論」、『中世文学』第23巻、1978年)。「安照能楽論の基本となる二つの考え方は、ともに「所作」に対立する「心」を 問題とし、修行が要請されていることがわかるであろう。そして、この二つの基本認識を基盤とし、心から事をなくすための修行論と 演技論が展開される。それが、後述する安照能楽論の眼目たる「心法修行論」と「真の理論」なのである。」
それゆえ、本稿ではこれら二つの伝書を中心に、彼の能にたいする理論的思索の跡をたどることとしよう。
彼の伝書には、個々の能作品についての舞台上での技法・心得などの相伝の記事も含まれるが、多くの箇所にわたって「謡」と「仕舞」の要領についての論考が展開されていて興味深い。先ず、「謡」についての安照の言葉をたどって見よう。(*の文章は、文意の要約を筆者が付したものであり、現代語訳ではない。)
うたいハ、はらにほねおらせ候へバ、かほにくせなき物也。うたひにも、云出す文字・いひはなす文字、大事也。心がけ専也。うたひはつる文字と、云出す文字と、同前なり。うたひ出したる文字を、云果るまで忘れず候と申伝候。(『金春安照伝書集』表章・小田幸子校訂、法政大学能楽研究所編 能楽資料集成9、わんや書店、17頁:以下、同書は頁数のみを示す)
*謡は、腹に力を込めれば、無理をした顔つきにならないで済むものである。謡初めの言葉と謡終りの言葉はとくに重要であるから、注意が必要である。終りの所の謡は謡い始めと同じようでなければならず、初めの箇所を謡い終るまで心に留めておかねばならない。
大かた、うたひは、すぐに、つよミをもつて、うつくしく、しづかに、かろく、おもてハふしのなきやうにて、よくきき、又ハつけてうたへバ、ふしこもりて、しづかなるかと思へばさきへ行やうに、しかも、ゆるゆるとして、ゆふにやさしく、つよきやうにうたふを、よきうたひと申伝候。文字をあざあざと、ぼけやかに、おちつき、さすがにまたさらりとうたふ事ハ、まねもならぬ物也。上手は、文字を人のみみにさハらぬやうにはこびぬすむを、へたハ、人にしらるるやうにうたふ也。
(同書、45頁)
*謡は、まっすぐに、強含みで、美しく、かろやかに謡うがよく、節は際立たせないで、静かに収まるかと思えば、さらさらと進み、やさしくて同時に強い謡がよい謡である。言葉ははっきりと、しかし謡は「ぼけやかに」謡うのがよい。上手な謡手は、言葉が聴き手の耳に障らないように「はこびぬすむ」ものである。
安照の謡にたいする心構えをよく表している文章である。文意は難読であるが、含蓄があり、「よきうたひ」とは何かを考える縁となるであろう。安照は安心立命した名人の謡い方を「ぼけやか」と表現しているが、これは最高位の謡のあり方を言い表す言葉であり、言葉をはっきりさせながら、おおどかで伸びやかに謡うというほどのことを言い表した言葉である。文字遣いには細心の注意を払いながら、しかも文字に心を留めないで謡うのがよいという。謡は能の「はかせ」であり、地謡の善し悪しが能の位を決するという。
惣而うたひにも、をしよき所はをさぬやうに、引よき所ハひかざる様に、ミじかき文字ハゆふに聞え、又のべたるあとは文字をつめ、詰たるあとはのべ、ならぶ文字はならばざる様にと心がけてよし。万事諸芸に渡る心持也。(同書、86頁)
*総じて謡は、押しやすいところは押さず、引きやすいところは引かず、短い文字はゆったりと、引いた後は文字を詰め、詰めた後は延ばし、文字が並んでいるところは並ばないように謡うのがよい。これは諸芸に共通するルールである。
次は、謡の稽古のあり方についてのコメントである。彼は謡をほとんど「口内芸術」であるかのように考えている。彼の指示は具体的であり、要を得ていて興味深いが、とくに発声の修行、「口内のけいこ」についての言及はきめ細かく、示唆的である。
謡ハ、体・ゆう(用の字を当てる、体にたいして属性的なもの・はたらきをいう)・のべちぢめやうをよくおぼえ、口内の所をただしく、あざやかに、少もへつらい作りこしらゆることなく、ただ其ままの所を以、五音の心を修行して、諸人のみみに五音のうたひわけよくきこゆるやうに、口・セ(舌)・シン(唇)、意、慥(たしか)にうたふ所、口内のこと所作のけいこ・修行なり。謡稽古のために、何れの謡をもつよく、文字をただしく、たけはば一ぱいに引つめ、はづむ心をうたふ也。(同書、161頁)
*謡は、ことばの意味、役割、延べ縮めをしっかりと理解し、「口内の所を正しく、鮮やかに、少もへつらい作りこしらゆることなく」謡うことが肝要である。五音の曲種を学び、それぞれの違いがよく聞き分けられるように、「口・セ(舌)・シン(唇)、意」を鍛錬し、「口内のこと所作」の稽古を積まなければならない。謡稽古は、強含みに文字を正しく、嵩幅いっぱいに、はづむ心で謡うべきである。
直成道にハ、こともなき子細也。こともなく、ただ其ままの心にふしをつけてうたふを、まことの謡と云。五音それぞれに心をそめ、其心にうつると云も、本分の理を根本にして、祝言・幽玄・恋慕・哀傷・閑曲、五音の所を謡わけ、其心口外へ聞ゆるを以、まことの謡と云なり。
*謡の道においては、事から離れ、心を直ぐにして謡うのがまことの謡である。祝言・幽玄・恋慕・哀傷・閑曲の五種の能のそれぞれに心を注ぎ没入させ、それぞれの基本を受けとめて、謡いわけることによって、聴くものにしっかりと伝わるようにすることが、まことの謡である。
それにたいして、彼が斥ける悪しき謡についても、伝書の随所において触れられている。そうじて、わざとらしく、自ら悦に入り、ことさら聴かせようという作為の謡を彼は強く嫌うのである。
あわれなるうたひにて候とて、文字も聞えぬやうにくどきたててうたふ事、きかれぬ物也。千人・万人の中にてうたふ共、不残人のミミによく入やうに、文字をさわさわと、けなげにうたいたるがよし。たとへ声たたず、地声にてうたふとも文字のわけよくきこえ、くちの内、くるくるとよくまハるやうに、常にこころがけうたふべし。……声をほそめ、ふとむる事、嫌ふなり。惣而、うたひをおもしろがらすやうにうたふ事、第一あしき事也。心のつよミにて四曲共にうたへば、其つよみの内から、うつくしき事われと出るやうにうたふがよし。声よきとて、うたひをおもしろがらせ、わがうたひをわれときく様なるハ、声きく音曲とて嫌ふ也。わがうたひて、人にきかするやうに謡うてよし。声をひきく謡とも、人のみみによく入様に謡事、第一也。(同書、43ff.頁)
*悲しい歌だからといって、何を謡っているやらわからないほど節をひねくりまわす謡は聴けたものではない。いかに大勢の聴衆であろうとも、耳によく入るように文字をまっすぐに飾らないで謡うのがよい。地声で文字の区別がよく聞こえるように、口内の稽古をよくするがいい。声を細めたり太めたり、面白がらせるように謡ったり、自分で悦に入って謡ったりすることは、第一に悪しきことである。心を強く保ち、自然に美しい調子がその強さの中から表れるように謡うのがよい。よい声だからといって面白がらせるように、自分の声を自分に聴かせるような謡は、「声きく音曲」であり、よくない。低音部の謡でも聴衆の耳によく入るように謡うことが第一に肝要である。
また、彼は謡には「事のうたひ」と「心のうたひ」とがあるといい、二種の謡方を指摘しているが、「事のうたひ」は外に心を向けた謡であり、うわつらの文言をたどるような謡であり、言葉ばかりが走る悪しき謡である。謡は心のうちにあるものが言葉となって聴くものに伝わるとき、真の謡とされるのである。
事をうたふと、心を謡ふとのかわりめ有之。ことをうたふハ、外からのうたひやう也。心をうたふハ、うちに有之。(同書、178頁)
次に仕舞についての彼の議論を見てみよう。謡における彼一流の観点は、仕舞においても貫かれる。仕舞もまた身に込められた力がくせなく、「ゆふ」(ゆったりとしておおらかな様をあらわすのに安照が用いる独特の用語)に現れるのがよいとされる。仕舞も謡と同様に、外なる表現に気を取られてはならず、「おもしろがらすように舞う事」は最悪なのである。彼はいわば「心の舞」ということを一途に主張する。「こともなく、ただ其ままの心にふしをつけて」舞うのである。
仕舞は、物ずくなにして、身なり・けい気・くらいけたかくして、習を含、仕舞を残し、しかもまたゆふにして手違なく、あぐまず、あづからず、せはしくいそがしからずして、身躰うつけざるがよし。静成能にもはやき能にも、つまる能・つまらぬ能あり。但仕手による也。ゆふなるハつまり、はやき能はゆふなるがよし。はやきもはやきにより、ゆふなるもゆふなるによるべし。習無之てハ成がたし。縦ば、櫓かずの立たる大船をこぎ出したるがごとし。重クかろきがよし。又面のあつかひを専と心得、頭をふり、面をいかし、扇をうごかし、仕舞多にするに依て、諸能ともにせはしく、位もなく、手うすく見ゆる物也。ゆふにけたかき女能なれ共、下女・遊女のかたちに見ゆべき也。又大蛇のうごかざると小蛇のうごきはたらくとハ、うごかざる大蛇をそろしかるべき也。但うごきはたらかざるがよきとても、ならはずしてハ成がたし。(同書、67頁)
*仕舞は、もの少なく舞い、位を気高く保ち、「ゆふ」にゆったりと構え、身体がぼんやりしないのがよい。静かな能、早い能、詰まる能、詰まらぬ能があるが、それらの能を仕手がこなすのが技量であるが、稽古を積まないでは可能でない。舞は、漕ぎ手が大勢の船が静かに滑り出すように舞い出すのがよい。「重くかろき」に舞うのである。また、「動かざる大蛇」は恐ろしいものだが、仕舞もそのようであるのがよい。ただ、稽古なしではこれは容易ではない。型を多くして、忙しく、手薄く動きまわる小蛇のような舞は品位がない。
このような仕舞を会得するためには、彼は「腰にほねおらせ候て、腰をよくすへ」ることが肝要であるという。そのことによって、ともすれば流されようとする舞に制動をかける不動力(対抗力)が生まれると彼は考えているのであろう。また、他のところでは彼は「心にも着すべきところ」がないことが肝要とも言うが、心が身の表現に気を取られて、腰が浮ついてしまうことを咎めているのであろう。外見に執着することがいけないのである。そのためには、腰をよく据えることが肝要なのである。
また彼は、「すぎたる」仕舞、「おほかる」仕舞を「しらうと」、「いなか芸」と言って非難する。いなか芸とは、仕舞をわが手作りのように細工し、「せはしくいそがし」く舞うさまをいう。これもまた、執着ということの弊害を突いた言葉である。これにたいする「上手」の舞とは、「ただ一はけに、ひだすくなに仕る」舞だという。これも安照の面目を示す言葉である。
者ごとに仕舞過たるハ、せはしくいそがしきなり。しらうとハ、しまいおほなるがよきと心得申候。さあるにより、いなかへくだりてハ、しらうとづきのするやうに、師匠のをしへぬ事をわが手づくりに、しまいをつけてするにより、手前の芸もくづれ、いなか芸に成申候。上手の上からハ、ただ一はけに、ひだすくなに仕る也。初心なるとも、ひだすくなるがよきと申伝候。仕舞おほなるをバ、当座の花とてきらひ申候。(同書、28頁)
こうして、彼の謡仕舞論は一貫しており、一切の執着心を捨て、心をおほどかに「ゆふ」に安定させ、外見や「事」に捕らわれない境位を説くのである。この境位は禅宗のそれに相通じるが、そこには禅竹以来の禅への傾倒が受け継がれていることが窺えるであろう。この執着を排する心は、己の自己を脱落させ、「ただおのれと身のあつかひの有」ような状態をいうのである。そしてそれは同時に、「むかしの人たちのたち居振舞は是なりと思ひて能をする」ことに通じると彼はいう。そえゆえ、脱我に通じるこの境位はたんなる無我の境地ではなく、シテの当に人物に「われともしらず出たる様」になるまで精進することを踏まえているのであり、鍛錬の結果の脱我というべきであろう。このような位に達することを彼は「うたはずまはず」と形容し、それを家の家訓としたのである。
能の本意と云ハ、仕舞によらず、身のよせひ・面のあつかひによらず、謡の本意、其能の本意・位、我と心にうかび、いにしへの人の物まね共おもはず、謡の本意・習を含、其文言にひかれ、ただおのれと身のあつかひの有こそ、能の本意とハ云べき也。又能も謡も、昔の其人に成、謡ハいにしへの人のいひし言の葉をわが身の上と思ひていひ、する芸もむかしの人のたち居振舞は是なりと思ひて能をするがよきと、申伝也。去ながら、ただ其人に成たるがよきと聞たる斗にて、言葉にハ云とも、いにしへの人にハ成がたし。稽古・習、残所なくきはめぬれば、其人に成べきと思ふ心もなく、謡共舞共習ともおもはず、よろこび・いさミ、或ハ恋慕・かなしミも、ただ我心より、われともしらず出たる様にあるによつて、する芸もさあつつべしく見え、見物する人も、むかしの人もかくあるべきとおもふ物也。習・稽古・鍛錬もなくして、其人に成べきとおもふ心は、ならぬ子細也。(同書、62頁)
*能の本位とは、能の本意・位が自ずと心に浮かび、物まねとも思わずになるまで謡の文言に自然と身が合うようになることである。昔のその人になり、「いにしへ人のいひし言の葉」を我が身のそれと受け取り、立ち居振る舞いもその人になりきるということは、言うは易しで、「稽古・習、残所なくきはめ」ることがなければ困難である。「よろこび・いさミ、或ハ恋慕・かなしミ」も我とも知らず我が心から出るように舞えば、見物人も「むかしの人もかくあるべき」と思うのである。
こうして、彼が説く謡仕舞のあり方はいわば客我不二ともいうべき水準を志向している。そのとき心の芸術としての能が実現するのであろう。ちなみに、謡と舞の一体性を説いた次の彼の言葉も印象的である。
かたちなき舞とハ謡を云なり。声なき謡とハ舞の事也。爰を以、能と謡ハかげかたちのごとしと云也。謡の本意を知れば、能の本意を知る也。(同書、45162頁)
さて、安照の伝書はなによりもその「真の理論」と「心法修行論」において異彩を放っている。これらの彼の理論は、心=真という彼独特の「心論」を土台にしている。心は真でなければならず、真は抽象的な真理ではなく、心において表れるものでなければならない、という見地が彼の能楽理論の全体を貫いているのである。「心」が能における舞台表現論の中軸に置かれることが、彼の議論のすべての核心である。次に、難解な長文であるが、彼の「心」にたいするこのような捉え方を瞥見してみることにしよう。
心と云ハ、目に見、聞、はなに入、したにあぢわひなどして、其しなじな我にうつりとまり、祝言・幽玄・恋慕・哀傷、それぞれの事身にふれ、あらゆることのわけを知り、分別・くふうをなす所を、心と知るべし。此心ハ、善にも行、悪にもうつる也。心と云に二つあり。道をよく習、修行をなせば、心と云と本心と云わけを知る也。此本心と云ハ、善にもゆかず悪にもうつらず、みる事・聞事、万物に着する事なし。無心無念にしてあり。ことのあることにハ、有に随而、理と本心と合て事を調るによつて、邪気の入べき様無之。理ハ仏性共云、無事ハ神心と云。是を能の本尊としてことわざをなすにおゐてハ、謡ともまふとも、扇をさす共引とも、足をはこぶとも、少もつかゆる事のなきを、神べんとハ云也。
情と云ハ、物ごとに着せず、さしむかふ当分当分の事につけて、ゆふにやさしき心也。月よ、花もみぢよ、恋慕・哀傷、あわれをかなしミ、あるひハよろこび、なさけふかき心のあるを、せいと云。是ハ、能のつや、やハらぐる所の心を云。……心ハ、惣身にみちてしづか成によつて、水のごとし。情ハ、着せぬ心を以、浪のごとし。性ハ、きよくあきらか成によつて、氷のごとしと云也。性・心・情と云も、気・血の中にやどり、我身のあるじ也。気・血、性・心・情、少しづつ替りハありといへども、水・浪・氷と云心也。至極の所ハ、万能一心と云るがごとし。(同書、146f.頁)
*心とは、五感のそれぞれを働かせ、祝言・幽玄・恋慕・哀傷の能のそれぞれにふさわしい形に分別工夫をなすものである。心は誤った方向に行く心と本来の方向にいく心(本心)とがある。道をよく習、修行をなせば本心を知ることができるが、その本心とは万物に執着することなく、無心無念のことである。有に随い理に合すれば、邪気が入り込んでくることもない。無事(事にとらわれない)の「神心」ということを能の本尊として、謡・舞に精進し、少しもつかえることがなくなれば、「神べん」の境位にまで至ることができる。
心は静かであるから水のごとくであるなら、情は着するところのない浪のごとくである。性は澄みきった氷のごとくである。情は目前の事物にたいして「ゆふにやさしき心」を向ける働きである。性はあはれを知り、なさけ深く、「つや、やハらぐる所の心」ことをいう。心身のさまざまな働きの基本となるものが心・情・性である。そして、それらの総称が心である。心は身の中にあり、その主人であるが、その極まるところは万能一心となるのである。
彼が考える理想の心は「無心」である。様々なことをなし、「しなじなに念の有ル心」は「まことの心」ではないという。能においては、いかなる作為(この作為を彼は「事」と呼ぶ)があってもいけないのである。「まことならざる心にて、まことならざる事に着をなし、心をうごかし念をおこす事、道の心にそむき、能の心にちがふ所が、能の道にまよふ子細也」。「まことならざる心」とは、あれこれのことをしよう、見物人をあっと思わせよう、面白く演出しようなどと思案をめぐらして創意工夫をすることであり、「まことならざる事」とは、そのような心によって作り出された舞台のありさまである。このような私心の世界を安照は徹底して斥けるのである。この作為の心を彼は目を指で押さえたときの視覚を喩えに引いて説いていて、まことにユニークである。
ゆびにて両の目の上ををして月をみれば、月のそばに又月ありて、二つにみゆる也。そばの月とて別に有にハあらねども、目をおすと云事があれば、一つの月も二つにみゆるがごとく、心も二つハなけれども、色々の事をなさんと思ふ念があれば、心がさまざまにまよふて、よき事に着しても、悪事に着しても、極る所ハ悪に着するぞと云儀也。又、一つの心と云ハ、善とも悪共おもわず、無念無心にして、一切、心に事のなき心なり。是を仏性と云也。(同書、176頁)
*私心(色心)が着くと、目を指で押せば像が二重に見えるように、心が二重化して色々の事を為そうとして迷いに陥る。極まるところは悪に着するしかない。それゆえ、一つ心を持してその心を無念無心に保ち、一切心に事を起こさないようにすることが肝要である。
能の心は無心である。「何の心もなきを能の根源・本分ぞと知る事ハ、やすくして又かたし」。無心は能における心の真の状態であるが、この状態に至ることが至難であり、修行を重ねないでは不可能であることを彼は繰り返し説くのである。心を執着させてあれやこれやと体裁を繕うことを彼は「事所作」という。「とやせんかくやと思ふ心がとどこをりて着すれば、能の本意もうせ、所作にふしが出くる物也」。169無心とはこのような事所作を離れることである。事所作が能にあってはいけないというのではない。所作のない能はありえないであろう。そうではなく、舞台に立つシテがあれやこれやと思い巡らすことが能を損なうのである。事所作は初心のときから一筋によく覚えておくべきことである。それゆえ、事所作から離れた無心の能は徹底した稽古を経ることなしには可能でない。
初心の時より、こと所作をただ一筋によくおぼえておけば、とやかくやとおもふしあんがなく、我もしらず、たくまず、少もこと所作に心のとどまる事がなければ、こと所作ハをのづからうせて、ひとり能の本意があらハるる也。(同書、4169頁)
色々のこと所作をなさんとおもへば、其事々々に念がおこりて、事も心もはてしなく、やむ事なし。色々の事がなければ、念もおこらず、事も心もおこらねば、ひとり本心があらハれて、をのづからまことの能とハ成子細也。一切の事から念がおこり、念から念がおこる事を去て、なき所に一点之来るを、能の本分と云也。(同書、193頁)
安照は「風姿花伝」を彼一流の独特の仕方で解釈している。誰もが知る「風姿花伝」の名を彼自身の心論に引きつけてその真意を説いたものである。一つは、風と花の喩えによって舞台における心と身の関係を説いているものである。その議論はユニークであり興味深い。風が知られるのは花が動くことによってであるが、花を動かす風は心(気)であり、動く花は身であり、所作であるとして、心の本源性を説いている。もう一つは、空と色から「花」(舞台での演舞を花と呼んでいるのであろう)を説き、花のためには空の心(心の気が無事であること)が要とならなければならない、と語るのである。
風姿花伝と云事。風ハかたちなけれども、万木千草を動して風のかたちを顕す。是則、一気の体と云なり。花ハ、桜木の中に花のかたちはなけれども、春と云時節を以、色香言語にのべられざるかたちを顕す也。能も、動所ハ一気のせいが風の吹ごとくにこと所作となり、我身ハ、桜木のごとくに、能の種ハなけれども、春の時節を請て花のかたちを顕ごとく、修行が能の種となりて、かたちも事もなき所より、妙・奇特なるかたちが顕るを以、風姿花伝とハ云也。(同書、150頁)
*風に形はないが、万木千草を動かして風の形が見えるのである。これを「一気の体」と呼ぼう。花は咲く前には桜木の中にその形はないが、春の時節が到来すれば、美しい花を咲かせる。能も同様で、我が身は木であるが、稽古という準備を備えておけば時節を得て「妙・奇特なるかたち」を顕すことができる。これが風姿花伝である。
風姿花伝と云ハ、空・色の二つ也。空は心、色は我が身の事也。此二つハ水・波のごとし。浪ハ気也。水ハ心。気につるる心、心につるる気なれども、色々にことをなせば、其気にひかれて、花のかたちがかくれ、みえざる也。花のかたちがみえざれば、能の本意がぜつするによつて、花のかたちがかくれぬ所の修行をなし、花のすがたをあらハしたる也。其あらハしやうハ、事があれば血気が出る。事がなければ、血気の出べきやう無之。血気がつよからねバ、花ハをのづからあらハるるほどに、ただ事なくして花のかたちをあらハさんとて、無事になしたれば、花のすがたがあらハれたる也。(同書、168頁)
*風姿花伝は空と色の関係を説いている。空は心であり、色は身(舞台の姿、花)である。あるいは水と波にも喩えられる。水は心であり、波はその表面の動き(気)である。この心と気との関係が整わなければ、花の形が隠れ、「能の本意」が失われてしまうのである。気が事に引かれて一向に技に向かえば血気となり、花が失せる。修行を重ねて、気を抑え、事をなくせば花の姿が表れるであろう。
能の真髄が心にあるとする彼の基本思想は、具体的な修行についての諸注意においても多彩に語られる。心をしっかりと定め、性(本性)と合致させ、不動の安定を得れば、能は自ずから成就することを、彼は手を替え品を替えて説くのである。以下では、そのいくつかを紹介しよう。
有程の習・こと所作に至るまでも、少も心をとられぬほどによくれんますれば、習・こと所作に心をおく事なし。それに能と云道の修行をなせば、あらゆる事をさらん、せつだんせんとおもはね共、もうねんおのずから去て、あらゆることもなくなり、本心が事所作となり、其心、行にあらはるるを以、意心・妄念をせつだんしたるとハ云也。無心、又有心事なきを以、真の能共妙共云之也。(同書、144頁)
*稽古の練磨が十分になれば、演技や型に気を配ることがなくなる。事所作を切断しようとする妄念も消え失せ、心が自ずから事所作に合致する。無心、「有心事なし」の心が能の真であり妙である。
たとへば、くろがねをもつて作るといへども、上手のかぢのうちたる刀にハ、にゑ・にほひ・つや・位ありと云。下手かぢのうちたるハ、つや・位と云事もなければ、何の見所もなきと云り。如此、くろがねを以作り出すことだにも、上手の所作なれば、言語いわれざるかたちを作り顕す也。……能にも、かげ・にほひ・べに・うしろい・つや・位と云てあり。是ハ所作を以調たる能にハあらず。道の修行をなせば、修行が、つや・位・かげ・にほひとも成ぞと知るべき也。(同書、160頁)
*刀を打つにも上手と下手とでは大きな違いがあるように、能にも道の修行を心得た者とそうでない者との間には、かげ・にほひ・べに・うしろい・つや・位が整うか否かの違いがあるのである。
水に舟をうかめ、舟に又心をのせよと云儀あり。舟に又心をのせよと云ハ、所作に又心がのらざれば、からふねのながるるがごとく、所作がかろはづミにゆきておちつかざるによつて、舟につミ物があれば、おもふかろく、おちつきてよしと云。所作の働様のたとへに云たる事也。たとへば心に所作がありとも、心の所作を心にのすると云事を知るべし。(同書、190頁)
*舟に心(船頭)が乗らなければ、舟はから舟となり水に流されるだけである。積荷がなければ舟は落ちつかない。所作においても同じで、「心の所作を心にのする」ことが肝要である。
性より出る心、明鏡、聖賢の心のごとし。此性に合する心を以こと所作をなすにおいてハ、事をもとめて所作となす事なく、心が事所作となりて位にそなハり、所作なくてもことのあらハるるやうに有之を、まことの能と云。此性なければ、位と云事もなく、あるじもうせて、其身に力もなくなり、事の顕べきやう無之。(同書、146頁)
*「性より出る心」があれば、おのずと心が事所作と一致して位が備わり、まことの能となる。心に性がなければ位も失せ、主位も保てず、演技に力なく「事」の表れようもなくなる。
以上のように、心の不動をめざす彼の修行論は、結局禅竹の語る「六輪一路」の思想に立ち返ることを訴えているように思われる。六輪一路の思想が心の修行のあり方を説くものであることを、彼は確かに見届けたのである。禅竹の説く六輪は寿輪から始まり空輪で終わるが、寿輪も空輪もともに無色の円相であり、空の心を表している。禅竹は寿輪を「色心不二、歌舞一心」と形容するが、これは安照の言う無念無心と同意であろう。六輪の思想では、能の成就は一つの循環運動であり、空(寿輪)から始まり、事(像輪)の域を経て、ふたたび空(空輪)に戻り、かくて能の境位は循環すると考えるのである。このような六輪の循環と同じように、安照の説く無心無念は、たんなる不動の心ではなく、無から有へ、そして有から無に還帰する無の自己成就の運動の極点であり、安心立命にいたる心の運動の始まりであるとともに終りでもある。無心無念は「能の悟り」の境地でもある。
このような空と無の能楽思想は、禅竹が禅僧のもとで親しみ、以後の代々の大夫もそれぞれに親しんだ禅宗の影響が大きいことがうかがえる。彼らは能の世界が禅宗の教えに通底することを体得してきたのである。ここに、禅竹から安照にまでいたる金春の大夫たちが受け継いできた能の思想の大要を見ることができるであろう。
無念無心の物が、天地の間にて、あらゆるものに成て、あらゆることをなし、又無念無心に成て、なき所に極る。能の本意も如此也。是則能の本分、六輪の根本と知るべし。(同書、169頁)
*無念無心の境地にいたれば、あらゆる場面においてあらゆることを成しながら、何もなさぬ無の極みに居ることができる。これが能の本文であり、六輪の根本である。
何と云事もなく、むかしより仕来る事をも、事共所作共おもわず、行も帰るも左右へまハるにも、事をなさんとおもふ心ハ少もなく、ただ其謡の声・こと葉がみみに入、其謡の心が我心に通じて有やう、其心斗が心にうかミ有やうにて、かなしき事も、うらめしく恋しき事も、何の事もなき我にうつりて、ひとり其心がもよほす様に有之が、則仏性、能者の成仏と思ふべき也。(同書、177頁)
*能の演舞は、私心を少しも挟まず、謡の声が耳に自然に入り、謡の心がわが心に自ずと通じるというスタイルがよい。そうすれば、悲しいことも恨めしいことも「何の事もなき」我が身にひとりでに移って、自らの思いのようになる。これが演者の成仏というものである。
禅竹の六輪一路には一剣が最後に添えられている(六輪一剣)。この一剣とは何であろうか。安照はこの剣に事所作の迷いを断つ「一拍子の打」(宮本武蔵)を読み取っている。彼が用いる「せつだん」という語はこのことを言い表しており、能の演舞において「断念」の心が肝要であることを訴えている。事の分かれ道における一念の発揮、心の裁断があって、無心無念はたんなる無ではなく、力強い能を生み出す根本原理であることを説いているのである。
ただ一念おこる所が、まよふ道へ行か、まよハぬ道へ行かの二つなり。まよハぬ道へゆけば事も善也。まよふ道へ行ばなきも悪也。是によつて、善悪の二道におもむく所がかん用也。此心をさとれば、能の根本を知る也。(同書、189頁)
*ただ一念(一剣)によって迷う道に進むか迷わぬ道に進むかが分かれる。この善悪いずれの道に進むかを裁断することを悟れば、能の根本が了解されるであろう。
道を知ると云ハ、こと所作、あるいハあるとあらゆる程の事を、能々相伝・けいこ・たんれんをなして後、其念をさらざれば、はてしもなくことをもとめ、様々の念にまよひ、還而邪念と成ゆへに、すいもう一剣にて、あらゆることの念をことごとくせつだんせんために、一剣を顕置たり。(同書、144頁)
*道を知るためには、ありとあらゆる稽古を尽くしても、誇る私念をすてなければ、かえって欲にかられ、思いに迷い、邪念にとらわれるゆえ、吹毛一剣で思念をことごとく切断することが必要である。このために一剣が置かれるのである。
六輪一路の教えは、事の地平から心を離し、性に安居して動かず、為さず、私心によって事を処することを戒める、という能の家の矜持を導くための相伝であると、彼は考えているに違いない。
昔より、金春家ハうたはずまはずの家と申伝也。(同書、63頁)
昔より仕り来らぬ事を、今新く我作意に事所作に顕仕事、しやかもどきと云て、道にちがひたる儀也。昔より仕来る事に、あやまり・てにはちがひ成事有之と云共、昔よりのあやまりをば、あやまりにたてておく事を、家の法となし置事也。爰を以、理ハやぶれど法ハやぶらぬと云伝るなり。(同書、149頁)
*金春家は昔より新しい作為によっては「うたはずまはず」と相伝されてきた。
昔から伝えられてこなかったことを新しく我意で事所作をなすことは、釈迦もどきといって、道に外れたことである。昔からの誤りがあれば、その誤りを誤りとして立てておくことが家の法である。理屈には外れるが、法を守るべしと伝えられてきたのである。
2022年8月26日
禅鳳伝書を読む(二) ――能の詞花を訪ねて31
禅鳳の諸文書のテーマは、一貫して舞歌二曲(謡と舞)に関する「心構え」の問題をめぐっている。ここでは、『反故裏の書』および『禅鳳雑談』における彼の特徴ある議論をたどってみよう。『反故裏の書』は三編に分かれるが、メモ書き風の多くの断片からなり、その内容も『毛端私珍抄』と重複するものが多い。そこにも彼一流の「風流」の考え方が現れていて、興味深い内容が散見される。他方、『禅鳳雑談』は、彼の日常の言行を弟子(藤右衛門と云う)が書き記したものであるが、能にたいする彼の思いや当時の奈良の様子が屈託なく伝えられていて、興味深い資料である。
禅竹は『五音三曲集』において、能の「位」を、祝言・幽玄・恋慕・哀傷・闌曲に分類していたが、禅鳳もこの分類を踏襲し、それぞれの曲趣を、次のように樹木に喩え、その性格を割り当てている。ここにも彼の直感主義的な表現法がよく表れている。
先祝言がうへ木のやうなる物にて候。さて幽玄と申はえだなどの心にて候。それより出候あいしやう(哀傷)・れんぼ(恋慕)にて候。是は葉・花などのごとくにて候。さて、花ばかりにてみが候ねば、よわく候てわるく候。。閑曲(闌曲)、み(実)にてあるべく哉。(表章・伊藤正義校注『金春古傳書集成』、わんや書店、1969年、476頁)
この五音の曲種との関わりにおいて、彼が特に重視するものは女能である。女能は能の核心部を担い、その美の頂点にあることを繰り返し述べるのである。その女能の装束について。
女能は、小袖などかんよふ(肝要)なり。いかにもうつくしく、たけながく、ゆるゆるとき(着)なしてよし。みじかき小袖などきれば、身なりにくせつく物也。足もとをみる物也。うしろのゑりなど、さのみかけず。上下(かみしも)のしたにきる物にはかはるべし。惣而(そうじて)、きる物に心さはる事あれば、能にくせあり。いかにもよくよく心へたる者にかいしやく(介錯)させていでたつべし。(同書、352頁)
世阿弥は女能の心構えを「心を体にして力を捨つる宛てがひ」にもとめていたが(『二曲三体人形図』)、禅鳳はそれを装束付においても求めたのであろう。次の面についての彼の言葉にもそのような心根が感じられる。装束で身を包み、面を付けて幕に向かう禅鳳の気迫が感じられるような文章である。
おもて(面)のつよきはきらふ也。面よわくてしよさ(所作)のつよきは、しよさより人を見おろしたるは、よし。只おもてつよきばかりは、必々、しよさ次成物也。内にてのたしなみかんよふ也。おもてはよはく、けいこはつよきをよしとする也。祖父禅竹、此事を常に申されし也。(同書、360頁)
彼の音曲(謡)論はとくに注目される。謡についての禅鳳のコメントは微に入り細に渡っており、彼がいかに謡の精進に心を砕いていたかがよくわかる。また、彼は「音曲をそれ程大事とは皆々心得られぬやうに存候」と述べているが、謡を軽視する風潮をたしなめ、弟子たちに言い聞かせるためであろうか、興味深いのは、多くの喩えを取り出して謡の要領を説いている点である。先ずは、お茶の喩。
音曲のよきは、上々の茶を、よきつぼに入て、よき時分に口をきりて、よくひきて、しる(汁)・花香のあるやうに、ふるきうたひにも、しる・はながありて、あたらしきやうなるを上々とす。(同書、397頁)
禅鳳は茶人村田珠光と交友があったが、彼の能にたいするまなざしには茶道の美意識が加わっているものと思われる。謡の向上のためには、茶を点ずるような周到な準備と要をえた段取りが肝要だと云っているのであろうか。また、彼は謡の要領をあるいは樹木を例に引き、あるいは淀川の流れを引き合いに出して、一方ならず諭している。
うたひはすぐ(直)にうたふべし。こつき(木付)のうつくしき木に花のさきたるがごとし。ふしは、はつき(葉付)のごとく、さだまりたるにほひをあらせて、うつくしくうたふ也。(同書、446頁)
謡は、淀川の水などのやうに、うへはいかにもゆるゆるとして、底のたぎりたる、よく候。(同書、423頁)
「よき音曲」を謡うことはまことに「一大事」であり、そのような謡を実際に聴いたことはさらさらないと、彼は言う。謡の困難さは能のなかでも至極だというのである。傾聴すべきは、謡の要は「うたひ」や「ふし」にあるのではなく、ただ「心のかわりめ」にあると、彼が述べていることである。「心のかわりめ」とは、平素からの覚悟と生活のたしなみ、謡にのぞむ際の心の持ちよう、そして曲種に応じて「五色にうたひをかき分」けるという配慮の濃やかさをいうのであろう。
世にひろく五音又は音曲の大事などとて人のもち候へ共、音曲のよきをば更々聞図候間、一大事の物と存候。大かたのたしなみにては難成候。朝夕仏神に祈、立つにも居にもわすれずしてなげきたしなみ、一大事と思ひ給候はずはなるまじく候。五音といふは、うたひによらず、ふしによらず候。ただ心のかわりめにて候。然共、五色にうたひをかき分候。此謡のこころのごとく心えてうたふべし。(同書、409頁)
次に、謡の具体的な要点を述べた彼の言葉をいくつか挙げよう。彼の日頃の鍛錬の迹が伺えるような、まことに傾聴すべき内容である。
大かた謡ひは、すぐにうつくしく、しづかにかろく、おもてにはふしのなきやうにて、よくきき、又はつけてうたへば、ふしこもりて、しづかなるかとおもへばさきへゆくやうにて、しかもゆるゆるとして、ゆふにやさしく、つよきやうにうたふを、よき謡と申候。又わるきうたひと申は、うち聞たる所は、やうがましく(もったいぶっており)、ふしおおく、うきしづみて、声をふとめ細め、のび過、又はちぢみなどして、はやくしたるく(速かったりだらだらしたり)、文字きこへずして、つけてみればことなることもなきやうなるを、わるきうたひと申候。もじをぬめらかして(ぬるぬるとすべるように)うたふを、ことにことにきらひ候。もじはさわさわとして、しかもぼけやかに(はんなりと美しく)うたふをよきうたひと申也。(同書、412頁)
能にも音曲にも、影・にほひ・ゆふ(ゆとり)のあるをほめ候。物にたとへば、馬の上手は、物の色の見えぬ程(速くて過ぎ去るものの色を判別できないほど)むま(馬)を出しても、くらのうへ、身なりもくづれず、たづなをゆるゆるととりて、天地四方をもながめ、おもしろきむち・たづな、曲をものらんと(曲乗りをやろうと)おもふやうなれば、ゆるめきて、かげ・にほひもありて、おもしろくみゆる也。馬のへたは、ただくらつぼに取りつきても落ぬを、やうやう馬にのりたると思ふ也。うたひものふも如此候。ほそみちなどをふみはづさじとあよみ候やうにはたらきうたひ候へば、更々おもしろき所もなく候。(同書、414頁)
音曲に嫌物は、声をふとくほそくつかふ事、うきしづむやうにうたふ事、吾うたひをわが聞やうにうたふ事、音曲ありときかするやうにうたふ事、めをふさぐ事、拍子をたかくうつ事、文字を聞えぬやうにうたふ事、人をしかるやうにうたふ事、おもしろがらするやうにうたふ事。(同書、423頁)
比喩を縦横に用いて、謡の要領を諄々と説く彼の説明はまことに興味深い。彼が弟子に屈託なく語るその口吻が伝わってくる。このように謡の要領を平易に説く事例は他に多くないであろう。なおそのいくつかを紹介する。
うたいは、のべしぢ(縮)め、つめひらき・うけおし(受押)、かん用にて候。是は人々しらず候。ただおもてむきはつねの物にて候。なべてのおもて、世間の物、それにゆふゆふとやさしく、こまやかにしみこほり候てうたい候。(同書、465頁)
こゑをきくうたい、わるく候。吾うたい候て、ひとにきかせ候やうにうたふがよく候。うたい、口にて行候てわるく候。どうにてうたい候てよく候。(同書、466頁)
うたいをうたふに、ふしの有所を大事と心得候ほどに、心とまり候て、おもくわるくなり候也。ただかろく、するりと、地ぐみ(地拍子)よく遣候。(同書、470頁)
うたい、口びるにてゆき候事、わるく候。どうより何にもつよくうたい候はでは、先達には成がたく候。(同書、476頁)
見られるように、彼は謡における「どう(胴)」の役割をとくに重視しているが、同様の指摘は舞についても述べられる。
舞に手がまひ候ほどにわるく候。心がまひ候てよく候。どう(胴)に心をもち候へば、足もかろがろとゆき候物にて候。かほに心が候ほどに、こしがよわく、あしにそくい(飯粒で作った糊)をつけ候やうに見へ候。(同書、449頁)
次の話は意表をついた譬えを挙げて謡の要領を述べたものであるが、ここで云う「大きなる柱」を「どう(腹の丹田、あるいは皮肉骨における骨をイメージすると良いであろう)」と理解すれば、まことに要を得た譬えだとわかるだろう。
三輪・かきつばたなどのいいごと(掛け合いの部分)も、たとへば、まん中に大きなる柱をたてておき、其まわりをくるりくるりとめぐり候て、何と申ともはしらをはなれ候はで、ころりとつめていい(謡い)候。(同書、475頁)
さて、謡と舞の根にあるものが拍子である。彼は『反古裏の書』において、拍子の重要性について説き、「拍子にはづるる時、能いでくる事なし」とまで述べていた。拍子は歌舞修練を積んだものがはじめて自由に操れるものであり、掌にものを転がすように習熟しなければならないものだと、彼は繰り返し述べている。。
拍子と云事肝要也。歌舞共に拍子よりおこる。皮肉骨と云に、拍子は骨也。拍子は、踏もひやうし、ふまぬもひやうし也。ちがはぬを至極と思ふ事、おかしき事也。馬にのる者の、くらつぼにとりつきて落ぬを、至極と思うふやう也。拍子をば我物にして、あとにもつれ、さきにもたて、そばにもおき、手にもにぎり、ふところにも入れ、又打捨も舞はたらくを、拍子ききと云也。此すぢめ大事也。(同書、392頁)
ひやうしは、わがひくわん(被官)の者(召使い)をつかふごとくにおもひて、あとにもをき、さきへもやり、手にももち、ふところにも入、又ひやうしをすて、とりあげ候やうに、心にまかせて、拍子にかかはり候はで、能をもし、うたひをもうたひ候程に候はでは、おもふやうにはなるまじく候。(同書、416頁)
最後に、禅鳳による能楽師の「戒律」ともいうべき文章をいくつか見ておこう。
いづれのみちもおなじ事ながら、能はことにことに行住座臥のたしなみ・くふうなくてはなるべからず。くふうはみちをならいて後の事也。ならはでくふうはいたづら事也。常住心にかけてくふうすれば、必めづらしき事どもいでくる也。ならはぬさきのくふう、必悪見邪道に入る也。(同書、361頁)
当世は何事もまんぢたる(慢心した、うぬぼれた)者名人になる也。大かたしまねくりて(まねばかりして)まんずべし。則上手に成る也。昔はことごとく上手成ゆへに、名はすくなし。当世は下手成ゆへによりて、名人おほし。是は、まんずる者をば上手と心ゆるゆへ也。(同書、370頁)
人に物をならふに、くせをまねて、よき所をばまねず。みなみな悪見に入心也。たとへば、其師のくせありとも、くせおばのけて、よき所をまなぶべし。(同書、377頁)
うたひをおほくおぼゆる事、丸本(一冊全部)などを御すき候て御うたひ候事、返々然べからず候。よきうたひをすくなくおぼえて、細々に稽古候事、肝要にて候。(同書、422頁)
物のしつめ(詰)たきは、しよく(俗)なるかたなり。物がたらずなるかたを、じんじやう(尋常)なるかたに、取べし。けいこのかたは物ずくななるかたよく候。一色草などの、ひやく(秘薬)にて、そと物をすうやうなるがよく候。(同書、470頁)
2022年2月17日
禅鳳伝書を読む(一) ――能の詞花を訪ねて30
金春禅鳳(八郎元安、享徳三年(1454)〜天文元年(1532))は、室町時代後期、戦乱と激動の時代に活躍をした金春座の大夫である。禅竹の孫であり、彼が十五歳のときまでこの祖父から薫陶を受けていたから、「大かた身おぼえ、聞おく事ども」も心底に残っていたようである。また、父宗筠(そういん)(七郎元氏)に二十七歳のときに先立たれ、大夫を継いでいるから、彼は若くして金春座を率いるという大任を負ったのである。
彼は後年、彼ら父祖を振り返って次のように感慨を語っている。
其みなもと遠しといへ共、近くは曽祖父観世之世阿弥、祖父禅竹、亡父宗筠までは、此みちひとつにして、其身きよふなるがゆへに、世にほまれありし也。愚老、きよふなく、みちにすくことなきによりて、二道(歌舞の道、すなわち申楽)ともに絶はてたり。(表章・伊藤正義校注『金春古傳書集成』、わんや書店、1969年、331頁)
室町後期の困難な時代状況のなか、都での勧進申楽の開催など、金春座の隆盛に貢献した禅鳳であるが、世阿弥、禅竹の威光がなお眩しく、周りから特別の目で見られ、重責に耐えようとしているさまが、この言葉ににじみ出ている。
禅鳳には、「嵐山」「生田敦盛」「一角仙人」「東方朔」「初雪」の現行曲五番その他の作品があるが、視覚的演出を重視したその作風は「風流(ふりゅう)」と呼ばれ、観世信光小次郎の後を受けて、申楽の世界に新風を吹き込んだものと考えられる。たとえば「初雪」は小品ながら、奥ゆかしい上臈の居宅を舞台とし、白尽くしの装束に白い鶏の立物を頭に置くという出立ちがまことに爽やかであり、また、亡くなった鶏〈初雪〉を上臈たちが弔うという意表をつくストーリーが清楚な世界を現出させており、「風流」の趣を見事に表している。さて彼には、能の作品の他に、『毛端私珍抄』『反故裏の書』『禅鳳雑談』などの伝書がある。ここではこれらの伝書の一端を訪ね、世阿弥、禅竹らによって確立された申楽が、どのように継承され変容していったのかを考える一助としよう。
『毛端私珍抄』とは奇妙な名前だが、「九牛が一毛にもおよぶべからず」(大きなもののなかの極々一部)という思いから、また、「他人にみすべき事ならぬ」という相伝の意からつけられたという。未完の書であり、後に紹介する『反故裏の書』を合せて一書にする心積もりであったものと思われる。むしろそのための草稿ないしメモであったと考えられ、その文章は整合的とはいえず、断片的である。
内容は、「第一 二曲三体(音曲)」、「第二 舞」と、歌舞の心得を説くものである。その行論は理論的な展開ではなく、主に舞台上での心得を説いており、現場の要を示すという妙が感じられる。
惣而(そうじて)、諸道は、ならひと数寄ときよふ(器用)と三也。この三そろへば、いづれの道も上手の名をうる也。一か(欠)くれば中分なり。此三のうちにては、数寄かんよう(肝要)ならん哉。たちひきよふすぐれずとも、すく心あればならふ事あり。すきてならはゞ、きよふなくとも無下なる事あるまじ。きよふなれども、すかずならはぬ人は、無下なることある也。(同書、332頁)
冒頭の言葉である。すべての芸道に、「習い」と「数寄(風流、好み)」と「器用(技倆)」とがあるという。三者がそろえば申し分ないが、なかでも「数寄」が肝要であるという。「数寄」とは芸に対するセンスであり、九鬼周造のいう「粋」に通じるものであろう。禅鳳自身は映像的な華やかさ、「風流」を求めたが、これが反転すると、「わび」や「さび」になるのであろう。二番目は「習い」である。習いは稽古であり、稽古があるかぎり「無下」には陷らぬという。稽古は「器用」=才能をも上廻るのである。「すく心」があり、その上に「ならふ事」が重なれば、「きよふ」を問わずとも芸劫が身に着くという思想は至当である。
禅鳳の伝書の一つの特徴は、舞台の上での心得、謡の有り様、舞の要所を単刀直入に書き示したところにある。舞台に生きた者が、受け継がれた舞台表現の精髄を反芻し、さらにそこに新しい息吹を導き入れること、このことに禅鳳の主要な関心があったものと思われる。石井倫子はこのような禅鳳の姿勢を「場面重視主義」と名づけ、舞台演出の「多焦点的な構成」に、その特色があると指摘した(『風流能の時代 金春禅鳳とその周辺』、1998年、東京大学出版会)。伝書には今日の現行能とは異なる指示も見られ、当時の舞台の実際を知るうえで大いに参考になるものである。先ず、尉・修羅・女という「三体」の「かたち」について見てみよう。
又、ぜう(尉)にもしなあり。木こり・すみやき・しほくみ・鵜かいなどのやうなるぜうは、其かゝり、にせよき物也。脇などの前のぜう、かぶり(冠)・なおし(直衣)などにてまふこと、一大事也。すぐすぐとして、らふらふと、花やかに、けたかくなくては見ぐるしきなり。此すぢめ、上ゝの大事也。(同書、333-4頁)
庶民の老人と貴人あるいは貴人を前にした老人とを区別することが「一大事」という。面で言えば、三光尉と小尉との違いにも当たるのであろう。その貴卑によって能の位が明瞭に区別され切り離されていなければならないというのである。とりわけ、彼は小尉の老人を「すぐすぐ」、「らふらふ」と演じ、そして「けたかく」表すことの難しさを説くのである。
修羅は軍体なれば、いかれるかたちなれども、能には花やかなるかたちを本とす。修羅によりて、いかにもうつくしくいでたちてよきもあり。つねまさ・たんざくたゞのり・ともあきらなどは、いかにもいでたち花やかに、仕舞も花ゞ(ばな)とすべし。(同書、334頁)
軍体は、世阿弥が「体力砕心」(力を体にし、心を砕く)といい、禅竹が「武士の矢波つくろふ籠手(こて)の上に霰たばしる那須の篠原」という歌を挙げ、清冽な緊張感から生まれる「幽玄」をその美としたが、禅鳳はそこにも「花やかさ」を求めた。彼は、軍体の能にも修羅固有の花やかさがあるとし、その風流を求めたのである。
女体の能について、
是は、ことにことに此みちの肝要也。先、男の身にてうつくしき女にならん事、誠およぶべき事ならず。ことに、身なりわるく、はづれ(装束で蔽えない体の端々の部分)くろく、いやしきおとこの女になることなれば、大かたに心へ候はゞ見ぐるしきこと也。いかにも身をほそむるやうにもちて、手・足・面之はづれなどもしろくうつくしきやうに、若き時よりはづれをたしなむべし。能にいでん時も、手足をよくあらいて、毛ぶかくなきやうにたしなむべし。身なりて(は)、いづれも同事なれども、はらにちからをもちて、手足はなへなへと、心をかみすぢのさきまでも入て、たとひわがうゑへばんじゃく(磐石)などおちかゝり、又は、能の場(には)にことなどいでくることあり共、身をくづさぬやうに心へて、物を堪忍するやうに心ふべし。(同書、335-6頁)
風流主義の極みとも思われるほどの舞台本位の思想が表れた行文である。鬘物や狂女物は能の花であり、核心部(破)であるが、彼は演者に女の性(さが)を表すために、全身全霊を込めよと要求する。女の能は、「ことにことに此みちの肝要也」という。そして、「たとひわがうゑへばんじゃく(磐石)などおちかゝ」ろうとも身を崩すなという。舞台という現場に花を咲かせることが鬘物の能の真髄であれば、演者には風流にたいする絶対的な覚悟が必要だという彼の風流主義はどこまでも手厳しい。
女物狂物に関する次の言葉は、女体の能のなかでも、とりわけ風流が純粋な形で表れたものと評価する彼の姿勢を端的に表していると思われる。
女物狂、おもしろき物也。一大事也。其心に思ふことを面にして、しかも花やかなる所かんよふ也。くるふうちにもおもふ事を忘ず、心をふかく思入てはたらくべし。狂人は物のあまりと(に)くるふなれば、すぢめ大事也。ひゑたる物のねつき(熱気)するごとし。(同書、336頁)
音曲についての禅鳳の言葉をみよう。彼は、音曲は能の基幹であるという。その音曲においても、彼の風流主義は一貫している。彼は、「音曲の事、浜の真砂のごとくなれば、いゝつくしがたし」(同書、344頁)とも述べ、謡言葉のすべてに亘って心がけなければならない留意点があると、彼は言いたいのであろう。
先ず彼は、謡のその場面や情景を心に把持し、思い浮かべ念じるように謡わなければならないという。
能は音曲より出たる物也。音曲次ならば、能はかならずへた成べし。乍レ去、昔より、能の上手に音曲のへたあるべからず。音曲よくて能をせぬ人は、むかしもおほし。音曲は能のはかせ也。(同書、337頁)
月よ・花よ、海・川・山・里などいふうたひは、心に是を見るやうにうたふ也。神道などは、心を信心にもちてうたふ。あはれ成ことは、心をあはれに、文字をばすぐすぐと、れんぼは恋慕のやうに、かどだちたる事は、其ごとく、幽玄成事は心をゆふに心(得)べし。是秘事也。(同書、338頁)
また彼は「よき声」と「出声」を区別しなければならないという。「よき声」は「其物によりて」、「姿に似合て」自在に出るものでなければならないという。ただ出るばかり張るばかりの声は「出声」と呼ばれ、「わるき水」が溢れ出るばかりのようなものだとして退けられる。
よきこゑといふは、其物々々によりて似あふやうに出るをよしといふ也。ふとくもほそくも、姿に似合て自在にいづるを、よき声といふ也。たゞいかほども出るばかりは、出声(いでごえ)といふ也。わるき水のおほく出るがごとくなり。いでごゑといふ也。(同書、339頁)
上やシオリ(クリ)の謡(甲)を高らかに謡い、下や呂の低い謡をほそぼそと謡うような舞台に出会うことがよくあるが、禅鳳によれば、このような謡い手は「第一のへた」であるという。謡が上がり下がりするからである。謡は機や調子を下げたり、力を入れすぎたりしないで、「すぐすぐ」と、「やすやす」とまっすぐに謡うのがよいのである。これを彼は「すぐなる謡」と呼ぶ。
呂の時は、心をすぐすぐと、機をもさげず、調子をもさがらぬやうにもちて、甲の時は、心をやすやすと、機にちからをさのみ入れずして、やすらかにうたへば、呂・甲・横・竪和合して、うたひのうちに、あがる所もなく、さがる事もなし。調子も又同事也。是をすぐ成うたひと云也。なべてのうたひは、呂とてさぐる所は調子もさがり、あぐる所は調子もつきてあがり、調子も張る也。是、第一のへた也。うたひの肝要・秘事とも云也。(同書、341頁)
調子は文ゝ句ゝに心をつけて、さがりもせず、の(退)きもせぬやうにうたふべし。(同書、348頁)
また、謡言葉ははっきりと、籠もらぬように謡わなければならないという。これを彼は「文字のさばき」と呼ぶ。
文字のさばきとは、いの字はいの字、ろの字はろの字ときこゆるやうに云を申也。何ともきこゑぬやうにうたふをきらふ也。(同書、342頁)
子方の謡を受ける場合や調子外れの謡を受けなければならない場合、謡い手は謡調子を急に変えたりしないで、「其いひはつるてうし(調子)」を受け継ぎながらも能の位が下がらないように、「次第にもとのてうし」に戻るように謡うことが肝要だ、と彼はいう。
おさなき者のてうし(調子)、又はの(退)く声(調子はずれの声)の次に請取こと、大事也。其いひはつるてうしにてうけとりて、次第にもとのてうしゑ(へ)なを(直)るやうにい(言)ひてよく候。大事の物なり。秘事也。(同書、349頁)
次に、舞についての禅鳳の言葉を拾ってみよう。舞においても花やいだ風流を重視する彼の姿勢は変わらず、女の舞、とくに「天女の舞」を「本」とし、これを極めることに舞の成就をみていたものと思われる。他の舞は「本舞」である天女の舞にたいする派生形としてとらえていたのであろうか。たとえば「神舞」は、「天女にかどのあるようにまふなり」と説き、天女基準の見地をつらぬいている。
舞は天女を本とす。五段とてあり。是をくづして色々にまふ也。五段をよくよくならふべし。……女の舞、天女ことにことに大事なり。心をくだきて、かみのすぢのさきまで心を入てまふ也。天女の五段不足ならば、よの舞もふそく成べし。(同書、347頁)
「天女の舞」は、今日「加茂」等で舞われている天女舞とは異なる。禅鳳は、「天女の舞五段」の型附を「佐保山」を例としてくわしく例示しているが(今日の「佐保山」は、神舞または真ノ序ノ舞を舞う)、それが今日の真ノ序ノ舞と「直結するものでないことは確か」だという(同書、補注45、593頁)。もっとも、禅鳳が示す五段舞のおおよその流れは今日の序ノ舞や中ノ舞と近似的であるように思われ、近世の能の変遷のなかでこれらの舞へと変転していったものと推察される。
一番は、たいはい(達拝)をして、左へまるくまはる。二だんは、まゑへよる。左右へ身をやりて、扇取かへす。三だんは、扇をひねりかへして、又左右へ身をやりて、前へ行て、扇を左へ取。四だんは、つづみ打の前にて、右へ扇をとつて、右へまはる。五だんは、かへりて、左右へ手をさしてとむる也。是、舞の五段也。是は天女の五節の心也。此舞をくづしてよのまひにまふなり。(同書、346頁)
ちなみに、世阿弥はこの「天女の舞」について興味深い指摘をしている。「天女之舞、曲風を大こう(大綱)に宛てがひて、五体に心力を入満して、舞を舞い、舞に舞はれて、浅深をあらはし、花鳥之春風に被随するがごとく、妙風幽玄之遠見を成て、皮肉骨を万体に風合連曲(各風曲を一つに総合する意)すべし。返々、大に舞也。能々稽古習学あるべき也。」(『二曲三体人形図』)
なお、禅鳳が舞手の個性について述べていることも注目される。基本(大綱)が習得されていれば、個人による差はくるしからずというわけである。
諸道にも、げう(業)をつたふるといへども、人のきよふによりて、ちとづゝかはることあり。是はさのみあしき事にてはなし。…おやと子のあひだにても、一かゝりかはるなり。くるしからず。(同書、332頁)
2021年11月19日
歌人の夢 ――能の詞花を訪ねて29
能「実方」は長く番外曲であったが、近年になって金春流と観世流によって復曲された曲である。陸奥守として赴任中に非業の死を遂げた実方の亡霊が、陸奥を旅する西行の前に現れ、都を懐かしみ帰郷の思いに狂乱の舞を舞うというストーリーの能であるが、この能が書かれた背景には、稀代の貴公子の辺境の地での死という、都人の興を誘う話題が尾ひれをつけて拡がり、いくつかの伝承物語となって伝えられていた、ということによるのであろう。
藤原実方は平安時代を代表する歌人の一人であるが、その作風には内なる下心(恋心)を情景に託すテクニカルな手法が感じとられる。先ず、多くの人に親しまれている百人一首に収められた歌を見よう。
女に初めてつかはしける
かくとだにえやはいぶきのさしも草 さしも知らじな燃ゆる思ひを
(後拾遺集、百人一首)
* 技巧的な連想ゲームのような歌である。「えやは(いふ)」と「伊吹」は掛詞、「いぶき(伊吹山)」は艾(「さしも草」)の産地、「さしも草」は「さしも知らじな(それほどだとは知らない でしょう)」を導く。また、「さしも草」は艾ゆえ「燃ゆる」の縁語。「思ひ」のひは火につながる。
実方の歌は勅撰和歌集に六十七首入集されているが、次にいくつかの彼の歌を見て、その人となりを探ってみよう。
東宮に候ひける絵に、倉橋山に郭公飛びわたりたる所
五月闇くらはし山の時鳥 おぼつかなくも鳴き渡るかな (拾遺集)
* 秀歌の誉れの高い歌であるが、深更のなかに独り揺蕩う心が、時鳥の闇を裂くような声によってはっと我に返るかのような「鈍い覚醒」が伝わってくる趣がある。
懸想し侍りける女の、さらに返り事し侍らざりければ
我がためはたな井の清水ぬるけれど 猶かきやらむさてはすむかと (拾遺集)
* 愛想のない女の心を「たな井の清水ぬるけれど」と形容した。「ぬるけれど」に熱意がないの意味があるが、次の「すむ」につなげて読めば、濁っていて他所に心が傾いている、という含意が読み取れる。なお、「かきやらむ」には水をかき回すと恋文を書くとが、「すむ」には共に住むの意が掛けられている。
祭の使にて、神だちの宿所より斎院の女房につかはしける
ちはやぶるいつきの宮の旅寝には あふひぞ草の枕なりける (千載集)
* 『源氏物語』「葵」の巻における、斎院となった朝顔にたいする光源氏の恋慕を彷彿とさせる
ような歌である。「ちはやぶる」は「いつきの宮」(斎院)にかかる枕詞。実方は加茂祭の御禊の
十二人の供奉の一人であった。「あふひ」は葵と逢う日とを掛けている。
実方は清少納言との間に密かな恋の関係にあったと云われる。清少納言は実方より少し年下であるが、共に利発で、時の人として周囲の耳目を集める二人が宮中で接近したのも頷ける話である。
清少納言、人には知らせで絶えぬ中にて侍りけるに、久しう訪れ侍らざりければ、よそよそにて物など言ひ侍りけり。女さしよりて、忘れにけりなど言ひ侍りければ、よめる
忘れずよまた忘れずよ瓦屋の 下たくけぶり下むせびつつ (後拾遺集)
* しばらく会わなかった二人が、宮中で出会ったときに清少納言が「忘れてしまったのね」と言ってきたので詠んだ歌である。瓦屋で瓦を焼く煙に咽ぶように、あなたを思って咽び続けてきました、というほどの意。
他方、『実方集』には、この歌に続けて清少納言の返しが載せられている。
返し、清少納言
葦の屋の下たくけぶりつれなくて 絶えざりけるも何によりてぞ (実方集)
* 清少納言の返しは「葦の屋」である。実方の「瓦屋」を受けて返したのであろう。葦の屋の煙はすぐに抜けてしまって咽ぶこともないけれども、そのように何気ないふりをしながら、あなたを絶えず思ってきたのは一体何だったのでしょう、といったところか。このことについて、徳原茂実は、「瓦屋」は瓦葺きの家のことをいうと指摘し、「屋のさま、いとひらに短く、瓦葺にて」と『枕草子』に ある一句(女房たちが控える瓦の建物(朝所)を差している)を引きながら、実方が清少納言の居所を「瓦屋」と暗喩したのにたいし、返しで彼女が自らを「葦の屋」と切り替えして対応した、という。(「清少納言と藤原実方との贈答歌について」、『武庫川国文』vol.76、2012年)
『枕草子』には、実方のことを記した次の文章がある。
小兵衛といふが、赤紐のとけたるを、「これ結ばばや」といへば、實方の中将よりてつくろふに、ただならず。
あしひきの山井の水はこほれるを いかなるひものとくるなるらん
といひかく。年わかき人の、さる顕證(けそう)のほどはいひにくきにや、返しもせず。
* 小兵衛という女房が五節の装束をつけて控えていたが、赤紐が解けたので「これを結びたいの」と隣の女房にいうと、実方の中将がさっと寄ってきて結び直してあげた様子は、ただならぬものだった。
山井の水のように固く凍ったあなたなのに、どうしてひも(紐・氷面)が解けてしまったのだろうか、心が解けたのかしら。
と歌い掛けた。まだ年若い女房だったので、このような人目に立つ処では歌も出なかったのであろうか、返歌をしなかった。
また、『撰集抄』には、次の歌が載せられているが、この話を聞いた藤原行成が「歌は面白し。実方はおこ(馬鹿)なり。」と評したことを、実方が根に持って、殿上で行成の位冠を投げ落とすという不祥事を起こしたという。
昔殿上のをのこども、花見むとて東山におはしたりけるに、俄に心なき雨降て、人々げにさわぎ給へりけるに、実方中将、いとさはがず、木の本に立寄りて
桜がり雨は降きぬ同じくは 濡るとも花の陰に宿らむ
と詠みて、かくれ給はざりければ、花よりもりくだる雨にさながらぬれて、装束しぼりかね侍り。此の事、興あることに人々思ひあはれけり。叉の日、斎信の大納言、主上にかかる面白き事の侍しと奏されしに、行成其時蔵人頭におはしけるが、歌は面白し実方はおこなりと、の給てけり。此詞を実方もれ聞き給ひて、深恨をふくみ給ひしとぞ聞侍る。(『撰集抄』巻八)
この一件によって、実方は帝(一条天皇)より陸奥守に「左遷」させられたのであった。このことについて、『源平盛衰記』は次のように詳しく伝えている。
一条院の御宇、大納言行成の末の殿上人にて御座しける時参内の折節実方中将も参會して小台盤所に着座したりけるが日此の意趣をば知らず実方笏を取直していふ事もなく行成の冠を打落として小庭に抛捨てたりければもとどりあらはになしてけり。殿上階下目を驚かしてなにと云ふ報あらんと思けるに行成騒がず閑々と主殿司を召して冠を取寄せかうがい抜出して髪掻直し冠打ちきて殊に袖掻合はせ実方を敬して云ひけるはいかなる事にか侍らん忽にかほどの乱罰に預るべき意趣覚えす、且は大内の仕出なり且は傍若無人なり、その故を承て報答後の事にや侍るべからんと事うるさくいはれければ実方しらけて立にけり。主上折節櫺子の隙より叡覧あって行成は勇々しき穏便の者也とて即ち蔵人頭になされ次第の昇進とどこほりなし。実方中将を召して歌枕注して進らせよとて東の奥へぞ流されける。(『源平盛衰記』巻第七)
実方の陸奥国赴任をめぐっては諸説があり、左遷とは言えないとする見解もあるが、彼の立場や行状からみれば、行成との確執による左遷とみるのが適切であろう(金沢規雄「藤原実方研究―陸奥守就任をめぐって―」、宮城教育大学国語国文(11)1980年)。彼が陸奥国に旅立ったのは長徳元年(995年)秋の頃であった。業平の東下りは逃避行であったが、実方は任官によって下るのであり、是非もない立場に思いを振り切らなければならかった。何の技巧もない次の歌はかえって哀れを誘う。
実方朝臣、陸奥国に下り侍りけるに、餞すとてよみ侍りける 中納言隆家
別れ路はいつもなげきのたえせぬに いとどかなしき秋の夕暮れ
返し
とどまらむことは心にかなへども いかにかせまし秋の誘ふを (新古今集)
次は、任地到着の歌。
陸奥に侍りけるに、中将宣方朝臣のもとにつかはしける
やすらはで思ひたちにし東路に ありけるものをはばかりの関 (後拾遺集)
* 「はばかりの関」は陸奥国にあったという関(今の宮城県柴田郡柴田町槻木の阿武隈川のほとりか(日本国語大辞典))。陸奥国に着いてみると、思い切って旅立ったときの心もいささか気後れしてしまったなあ、というほどの意。
さて、能「実方」は、西行(ワキ)の陸奥行脚の道行から始まる。西行は陸奥国愛島にある実方の塚に立ち寄ったのである。
ワキ
これは鳥羽の院の北面。佐藤兵衛義清出家し。西行法師にて候。我このほどは都に候いて。洛陽の寺社残りなく拝みめぐりて候。いまだ陸奥を見ず候ほどに。このたび思い立ち。陸奥行脚と志し候。
みちのくはいづくはあれど塩釜の。いづくはあれど塩釜の。
浦吹く風の松島や。雄島のあまをよそに見て。月のためには塩煙。
絶え間がちなる気色かな。たえまがちなる景色かな。
ワキ
さてはこれなるは実方の旧跡にて候いけるぞや。
痛わしや世に名をとどめし歌人なれども。
この遠国の道の辺に。しるしばかりを見ることよと。
思いつづけてかくばかり。
朽ちもせぬその名ばかりを残しおきて。
枯野の薄かたみとぞなる。
西行が口ずさんだ歌は、本曲の主題であり、この能の基調を与えるものである。元の歌は、『新古今和歌集』に上梓されている。
陸奥国へまかりけるに、野中に、目にたつさまなる塚の侍りけるを、問はせ侍りければ、「これなん中将の塚と申す」と答へければ、「中将とはいづれの人ぞ」と問ひ侍りければ、「実方朝臣のこと」となん申しけるに、冬のことにて、霜枯れの薄ほのぼのと見えわたりて、折ふしもの悲しうおぼえ侍りければ
朽ちもせぬその名ばかりをとどめ置きて 枯野の薄形見にぞ見る
* 西行のこの歌によって、塚の辺りにある一叢のすすきは「形見の薄」と呼ばれるようになった。
西行が歌を口ずさんでいると、どこからともなく老翁(シテ)が現れ西行に声をかけた。時代を超えた二人の歌人の対面の場面である。実方は四十歳前後に亡くなったのだが、能作者はこの地に亡霊となって住みついた実方の執心を、行歩もかなわぬ老翁に仕立てたのだ。二人の歌人の間の時代の差、帰洛を果たせなかったという超時制的な執心の業が、この亡霊を二百歳を越える老翁にしたのであろう。次は二人の邂逅の場面。
シテ
のうのう西行はいづくへ御通り候ぞ。
ワキ
不思議やな人家も見えぬ方よりも。老人一人来りつつ。西行と問わせ給うは。いかなる人にてましますぞ。
シテ
さすがに西行の御事は。世にかくれなき有明の。影は雲井に天さがる。鄙人までも何とてか。御名を知らで候べき。
ワキ
たといその名は聞こゆるとも。いまだ向顔申さぬ人の。見知り給うは不審なり。
シテ
いやそなたこそ知しめされね。我は手向けの言の葉の。蔭より見聞く西行の。御弔いをばつくづくと。喜び申し来る身の。
ワキ
これは不思議のことなりと。
物語は、すぐに臨時の祭の場面へと進む。シテは笹をもって登場するが、この笹は加茂の臨時の祭における実方の誉れを表すのである。次は、臨時の祭を回想するシテの語りである。
シテ
そもそも都加茂の臨時の祭りとは。北祭りの御事なり。一条の院の御宇かとよ。
この加茂の臨時の祭りの舞人は。近衛の中将藤原の実方の役なりしが。宮中清涼殿の試楽の折節。実方遅参し。帝より挿頭の花を賜らず。人々いかにと見るところに。実方騒がず東の庭にありし。竹の台に進みより。呉竹の枝を手折りてこれを冠に挿す。優美の姿ならびなし。
それよりしてぞ臨時の祭りの舞人は。今に竹の葉をかざすとかや。
その実方の塚の主。竹の誉れの世がたりに。これまで現れ出でたるなり。
ところが、語るうちにシテの心は加茂の臨時の祭のその場に移り、狂乱の状態となる。都に帰ろうとして「西へゆくべし西へゆくべし」(西行の名が掛けられている)と叫ぶとみえて姿を消した(中入)。
シテ
いかに西行。さてもこのころ都加茂の臨時の舞。実方が役にて候えども。すでに年たけ老衰し。行歩も今はかなわねば。御許されも候えと。辞し申せどもかなわず。嘉例をひける舞なれば。神勅さらに背きがたく。
地
今は都に帰るとて。今は都に帰るとて。
天にあがると見えつるが。
あまの鳥船の心地して。雲の波路をやすやすと。
ゆきすぐる都路の。しるべとなるや有明の。
西へ行くべし。西へゆくべし西行も。
臨時の舞を御覧ぜよ 臨時の舞を御覧ぜよ。
後場では、シテは西行の夢のなかの実方となって現れる。面は三光尉から小尉へと替わる。処の老翁から都の実方に変わるのである。身につけた装束も雲上人の正装となる。初冠をかむり追懸をつけるのは、臨時の舞の舞手であることを表している。夢中の実方は、勅命を受けた舞手の誉れを一身に表している。そして、彼の名を高からしめた挿頭の竹を初冠につけ、竹の誉れを讃えながら舞を舞うのである。次は、クセにかかる部分からの詞章である。
地
さても帝の宣旨には。祭りも臨時の祭りなれば。
臨時の舞を仕れとの御事なり。
シテ
そもそも竹は直にして。
地
七賢もこの林に住み。白楽天は友と云えり。
中にもこの竹は。
即心成仏の粧い。正直の相をあらわし。
御代の春ものどかに。国すなほなる道を見す。
風清翠に音添い。雪白浪に残れり。
賀茂の川淀。濁りなき時ぞめでたき。
ここに実方は。粧い花をおびて。盛り今なかばなり。
君の恵みの時めきて。色香上なき舞の袖。
シテ
花にたわむれ月にめで。
地
雪をめぐらす舞の袖。
げにも妙なる粧い さもみやびたる梅が枝の。
花の顔ばせ。匂やかなりし姿の。
水にうつる 影見れば。
わが身ながらも美しく。
心ならずも休らいて。舞の手を忘れ水の。
御手水に向いつつ かげにみとれてたたずめり。
シテ
夢のうちなる舞のそで。
地
うつつにかえす。由もがな。
御手洗の水に映る自らの影を見て陶酔するのは、まったくのナルシシズムであるが、実方の歌風から覗えば、宜なるかなの感がしないわけでもない。賀茂祭のゆかりなので上賀茂神社の御手洗川の水面がここで謡われているのであろう。ところで、この箇所は、『新古今集』に採られた次の実方の歌に基づいて作詞されたのである。
臨時の祭の舞人にて、もろともに侍りけるを、ともに四位して後、祭の日遣はしにける
衣手の山ゐの水に影みえし なほそのかみの春ぞ恋しき (新古今集)
* この歌は、石清水八幡宮の臨時祭で舞ったときを懐かしむ歌である。山藍に染められた小忌衣の袖が山井の水に映ったことよ。あのときの春がなつかしいことだ。「山ゐ」には舞人の袖が山藍で染められていることを掛けている。また、「山井」には石清水の意も掛けられている。
なお、上賀茂神社には御手洗川の辺りに実方を祀る橋本社が今日も佇んでいるが、この橋本社には実方も祀られているという。『徒然草』六十七段には、次の一節がある。
賀茂の岩本・橋本は、業平・実方なり。人の常に言ひまがへ侍れば、ひととせ参りたりしに、老いたる宮司の過ぎしを呼びとどめて、尋ね侍りしに、「実方は、御手洗に影のうつりける所と侍れば、橋本や、なほ水の近ければと覚え侍る。吉水和尚、
月をめで花をながめしいにしへの やさしき人はここにありはら
と詠み給ひけるは、岩本の社とこそ承りおき侍れど、おのれらよりは、なかなか御存知などもこそさぶらはめ」と、いとうやうやしく言ひたりしこそ、いみじく覚えしか。
* 上賀茂神社の摂社である岩本社と橋本社は、在原業平と藤原実方をまつっている。人がいつもどちらがどちらの歌人を祀っているのか言い間違うので、ひととせ参詣した折、年老いた宮司が通り過ぎるのを呼び止めて尋ねたところ、「実方は、御手洗川に影が映った所と聞いていますから、橋本社がやはり水の流れに近いので、実方を祀ったものと思われます。吉水和尚(慈円)が、
月をめで花をながめしいにしへの やさしき人はここにありはら
とお詠みになったのは、岩本の社と承っておりますが、私などより、あなたがたのほうがかえってお詳しいでしょう」と、たいそう礼儀正しく言ったのは、まことに立派だと思えた。
臨時ノ舞を表すのは、能では序ノ舞である。舞い終えた実方が、御手洗の水をさらに見入っていると、若く華やいだその姿は、老衰し、白髪を乱した、眉鬚も霜のような影の姿に変わるのであった。
シテ
みたらしに。うつれる影を。よく見れば。
地
わが身ながらも。
シテ
美しかりし粧いの今は。
地
昔に変る。
シテ
老衰の影。
地
寄するは老波。
シテ
乱るるは白髪。
地
冠は竹の葉。
シテ
眉鬚はさながら。
地
霜の翁の気色はただ。おどろに雪の降るかと見えて。
払うも舞の。袖とかや。
さて、時も過ぎ、上賀茂神社の神山に住むという別雷の神が迎えに来たのであろうか、とどろとどろと雷鳴が鳴り渡ったかと思えば、実方の姿は消えて、塚の草の枕に臥していた西行の夢は覚めたのであった。
シテ
さるほどにさるほどに。
地
舞楽も時移る糸竹の響き。峯どよむまで。
加茂の神山の。もとより臨時の時ならぬ雷。
とどろとどろと鳴り廻り鳴り廻る。
時もくるまの加茂と思えば。
ありつる野辺の。実方の塚の。草の枕の夢さめて。
枯野の薄。形見とぞなる。
跡とい給えや西行よ。跡弔い給え西行。
実方は、任地に赴いて三年のとき、阿古耶の松を訪れた帰り、笠島の道祖神(今日の佐倍乃神社)の前を通りかかったとき、土地の人から神前を下馬するように教えられたが、それに及ばずと馬上のまま通り過ぎようとした時、突然馬が暴れ、落馬して一命を落とす仕儀になった。都への帰郷を果たさず、遠国で横死したのである。その経緯を『源平盛衰記』から見てみよう。
笠島道祖神の事
終に奥州名取郡笠島の道祖神に蹴殺されにけり。実方馬に乗りながら彼道祖神の前を通らんとしけるに人諫めて云ひけるは此神は効験無双の霊神、賞罰分明なり、下馬して再拝して過ぎ給へと云ふ。…実方、さては此神下品の女神にや、我下馬に及ばずとて馬を打ちて通りけるに神明怒を成して馬をも主をも罰し殺し給ひけり。其墓彼社の傍に今に是有りといへり。人臣に列して人に礼を致さざれば流罪せられ神道を欺いて神に拝を成さざれば横死にあへり。実に奢る人なりけり。され共都を恋しと思ひければ雀と云小鳥になりて常に殿上の台盤に居り台飯を食ひけるこそ最哀れなれ。(源平盛衰記 巻第七)
実方の死が都に伝えられたころ、宮中清涼殿に一羽のスズメが入り台盤の飯を食い荒らすということが起こった。人々はこの雀を実方の霊が乗り憑いたものとして怖れたという。また、このころスズメが農作物を食い荒らすということが起こり、この雀が入内雀とも実方雀とも呼ばれるようになった。今日のニュウナイスズメはこの故事から名前が採られている。また、おなじころ、勧学院の僧観智法印の夢に霊雀が現れ、実方が雀に化身して都に帰ってきたものと憐れみ、その供養のため寺を更雀寺と称したという(今日の左京区更雀寺に実方を祀る雀塚がある)。
さて、西行の塚は宮城県名取市愛島の叢林の中に静かに安らっている。塚は西行の歌によって広く知られるようになったが、奥州を旅した芭蕉は、梅雨のさなかで道がぬかるんだため、塚には立ち寄らなかった。
鐙摺(あぶみずり)、白石の城を過、笠島の郡に入れば、藤中将実方の塚はいづくのほどならんと、人にとへば、「是より遥右に見ゆる山際の里を、みのわ・笠島と云、道祖神の社 、かた見の薄、今にあり」と教ゆ。此比(このごろ)の五月雨に道いとあしく、身つかれ侍れば、よそながら眺やりて過るに、簑輪・笠島も五月雨の折にふれたりと、
笠島はいづこさ月のぬかり道 (奥の細道)
2021年09月21日
流人の歌 ――能の詞花を訪ねて28
流刑は平安時代以来、死罪に次ぐ重い刑である。刑は罪の軽重によって近流、中流、遠流に分かれた。佐渡島、伊豆諸島、隠岐、蝦夷、南西諸島などの遠島が遠流の流刑地としてよく知られている。明治41年の刑法制定によって流刑が廃止されるまで、これらの島々はわが国の政治・文化史の一隅に絶えず登場してきたのである。能との関わりでは、世阿弥が佐渡島に流されたことが能の歴史の一大エポックというべき出来事であった。しかし、世阿弥の佐渡配流の問題は別稿にゆずり、ここでは能「俊寛」における鬼界ヶ島配流の物語を考えてみよう。
〈俊寛〉はさまざまな文学・芸能において広く愛好される題材の一つである。俊寛の物語は、『平家物語』において、藤原成親を中心とする鹿ヶ谷での平家討伐の密議が発覚し、俊寛・康頼・成経の三人が鬼界ヶ島に流された経緯が語られたことに端を発する。二年後、清盛の娘徳子の安産祈願のため、康頼・成経の二名の赦免が行われ、俊寛一人が島に残されたことがその後の人々の文芸意識を大いに触発したのだった。能「俊寛」は、平家物語の原作を踏襲して、独り鬼界ヶ島に残された俊寛の苦悶を描くが、江戸時代にいたると、近松門左衛門が『平家女護島』を著し、千鳥という名の海女を登場させ、成経と祝言をあげたと語るのである(成経が島の海女と契り、一子をもうけたことは『源平盛衰記』で語られている)。ところがその祝言のさなかに赦免の舟が現れたのである。そして近松は、俊寛が島に残ることを条件に康頼・成経・千鳥の三人が船に乗るというストーリーに改変した。物語における「本歌取り」ともいうべき、近松の創意の一例がここに見られるであろう。独り孤島に残るという逆境を俊寛自身の意志によるものと〈逆転〉させ、同時に独り残されるという絶対的苦悶に苛まれるという〈ダブルバインド〉を描きあげたところに近松の面目がある。近世江戸期には、私小説的な文芸意識の興隆のなかで、近松に見られるような葛藤心理を描く創作精神が生まれるにいたったのである。
この変奏がさらに近代にいたって、大正期に一つの「文学的事件」を生起させた。先ず倉田百三が戯曲『俊寛』(1920年)を著した。流人三人の内面的葛藤を信仰における相克と読みとり、彼らの行状を殉教物語のように描きあげた。倉田は、俊寛が赦免の船が着く前に自分独り島に取り残されることを直感し、成経・康頼に「生きるも死ぬるも三人いっしょだ」ということを約束させる。ところが赦免の船を前にしてこの二人は俊寛を残して船に乗り込んでしまう。約束を破った二人の内心葛藤と俊寛の絶望と「わしはこの島の鬼となるぞ!」という苦悶の叫びが戯曲の終焉で描かれる。作家の眼目は人間の内面の軋轢と苦悶を描くことにあったのであろう。彼が描きあげた、悪霊が乗り移ったかのような俊寛最期の絶唱の言葉は、あたかも狂気のリヤ王が荒野にむかって叫んだ絶唱を模したかのようである。
(月をにらみつつ)いかに月天子、汝の照らすこの世界をわしはのろうぞよ。汝の偶たる日論をも呪うぞよ。かつては汝らの名によってこの世界に正しき律法あることを証したこともあったが、今は悪魔の名によって取り消すぞ。あゝ、この世界をわしは憎む。わしが生きている間、わしをいかに遇したか。それをわしは永劫に忘れぬぞ。この世界はゆがめる世界だ。善が滅び悪が勝つ世界だ。あゝ、なきに劣る世界だ。かかる世界は悪魔の手に渡すがいい。悪魔よ来たれ。わしは汝に今こそ親しく呼びかけるぞ。わしは三界に怨霊というもののできる理由を今こそ知った。わしのごとく遇せられて死んだものの霊が、怨霊にならずして何になるのだ。
倉田の宗教的・悲劇的解釈に対抗しようとしたのであろうか、翌1921年に菊池寛が短編「俊寛」を書き、真っ向から対抗する俊寛像――幸福な俊寛――を描いてみせた。なんと、俊寛は島の娘と結婚し、5人の子どもをもうけていたのであった。有王が主人をたずねて鬼界ヶ島に来たとき、帰洛を断る俊寛にあきれかえり、主人の心に物の怪がついたものとしてあきらめるしかなかった。――こうなると俊寛物語もほとんど喜劇である。
別れるとき、俊寛は、「都に帰ったら、俊寛は治承三年に島で果てたという風聞を決して打ち消さないようにしてくれ。島に生き永らえているようなことを、決していわないようにしてくれ。松の前が、鶴の前が生き永らえていたらまた思うようもあるが、今はただひたぶるに、俊寛を死んだものと世の人に思わすようにしてくれ。」
そんな意味をいった。その大和言葉が、かなり訛が激しいので、有王は言葉通りには覚えていられなかった。戯れながら帰って行く一行(俊寛一家)を、船の上から見ていた有王は、最初はそれを獣か何かの一群のようにあさましいと思っていたが、そのうちになんとも知れない熱い涙が、自分の頬を伝っているのに気がついた。
さらに、その翌年に今度は芥川龍之介が短編『俊寛』を著した。彼がこの短編を著したのは、これら二人の俊寛物語を浅薄で一方的な「琵琶法師の嘘」にすぎないと断罪し、彼らの俊寛像に敵愾心を覚えたからであろう。彼は、この物語が絶望の悲劇でも家庭を持つにいたった幸福劇でもなく、俊寛が自らの意志で島に留まり、平静な余生を送ることを選んだのだとする「主体意志説」をかかげたのである。物語は、成経・康頼が赦免された翌年、俊寛のもとを訪れた有王(俊寛の侍童)が後年、回想をするという体裁で語られる。 俊寛は有王を瀟洒な自宅に招き、みずから夕食を饗応したという!そして、食後、涼しい竹縁に移り、俊寛は赦免船の一件を語った。
いよいよ船出と云う時になった。すると少将(成経)の妻になった女が、あの赤児を抱いたまま、どうかその船に乗せてくれいと云う。おれは気の毒に思うたから、女は咎めるにも及ぶまいと、使の基安に頼んでやった。が、基安は取り合いもせぬ。あの男は勿論役目のほかは、何一つ知らぬ木偶の坊じゃ。おれもあの男は咎めずとも好い。ただ罪深いのは少将じゃ。――あの女は気違いのように、何でも船に乗ろうとする。舟子たちはそれを乗せまいとする。とうとうしまいにあの女は、少将の直垂の裾を掴んだ。すると少将は蒼い顔をしたまま、邪慳にその手を刎ねのけたではないか?女は浜べに倒れたが、それぎり二度と乗ろうともせぬ。ただおいおい泣くばかりじゃ。……
芥川も『源平盛衰記』にしたがって、成経に島の女と結婚させている。ところが、彼の描く成経は、すがる妻の手を払い除け、独り船に乗ったのである。これに激高した俊寛が沖に遠ざかろうとする船に向かって必死で返せ返せと手招きしたのである……。
島に残された俊寛が理性を失わなかったとする芥川の解釈は卓見であろう。それにもかかわらず、瀟洒な家に住み、島人から尊敬されるという俊寛像はいささか平板的で、戯曲性に欠ける。俊秀な芥川作品のなかでは残念ながら失敗作といわざるをえないであろう。さて、三者の『俊寛』を並べてみれば、菊池寛や芥川龍之介の作品の「軽率」さに比して、過度の主観的実存的変容がみられるとはいえ、倉田百三のそれに文学的格闘の跡を認めるべきであろう。このことについて、「菊池の底抜けの健康な明るさと芥川の知的諷刺による俊寛像を眺めたあと、再度、倉田の「俊寛」に思いをいたせば、その重厚さがあらためてずっしりと強烈に感じられてくる。それは倉田という個性の深い思索力と苦悩に裏打ちされているからだろう。」という板根俊英の指摘には説得性が感じられる。(『県立広島大学人間文化学部国際文化学科紀要2』、2007年)
ちなみに、倉田百三と菊池寛と芥川龍之介は一高時代の同級生であった。倉田が先陣を切ったが、同窓の三者が反目しあって描き出した『俊寛』のドラマは大正期の文芸における不調和な多元的ベクトルの現れというべき、文学史上に特筆すべき「事件」であったということができるであろう。
さて、能「俊寛」にもどろう。能「俊寛」は『平家物語』の内容をほぼ踏襲しているが、三人の流人の「性格描写」、「心理分析」がきわだって卓越しており、能の作品のなかでは稀な「小説的性格」を有する作品となっている。成経と康頼は小心な性格であるが、三熊野の信仰心が厚く、島に三熊野を勧請し、九十九所の王子まで設けて帰洛を夢見て巡礼を重ねるという日々を送っていた。信仰心を持たない俊寛は、「後の世を。待たで鬼界が島守と。なる身の果の暗きより。暗き道にぞ。入りにける」(生きているうちから鬼のいる世界(冥土、鬼界ヶ島を掛ける)の島守となってしまったわい。我は冥土から出て冥土に帰るばかりの身にすぎないのか。)と嘯き、水を汲んできては康頼らに酒だといって勧める泰然ぶりを見せる。
康頼
いかにあれなるは俊寛にてわたり候か。
シテ
早くもご覧じ咎めたり。道迎いのそのために。一酒を持ちて参りて候。
康頼
そも一酒とは竹葉の。この島の内にあるべきかと立ち寄り見れば。や。これは水なり。
シテ
これはおん言葉とも覚えぬものかな。そもそも酒という事は。もとこれ薬の水なれば。霊酒にてなどなかるべき。
初同の謡は、水で交わす酒宴の場を謡ったものであるが、孤島での哀れな生活を淡々と謡いあげており、聴く者の心を打つであろう。
飲むからにげにも薬と菊の水。げにも薬と菊の水。
心の底も白衣の。濡れて干す。
山路の菊の露の間に。
われも千歳を。経る心地する。
配所はさてもいつまでぞ。
春過ぎ夏たけてまた。
秋暮れ冬の来たるをも。
草木の色ぞ知らするや。
あら恋しの昔や 思い出は何につけても。
あはれ都にありし時は。
法勝寺法成寺 ただ喜見城(1)の春の花。
今はいつしかひきかえて。
五衰滅色の秋なれや。
落つる木の葉の盃。飲む酒は谷水の。
流るるもまた涙川水上は。われなるものを。
もの思う時しもは
今こそ限りなりけれ。(2)
(1)忉利天にある帝釈天の居城で、極楽の地。
(2)今は望みも絶たれてしまった。
そこへ赦免使を乗せた舟が島に到着した。清盛の娘、中宮徳子(後の建礼門院)の出産祈念のため、「非常の大赦」がおこなわれるというのである。ところが赦免状には成経、康頼の二人の名のみが記されており、俊寛の名前はどこにも書かれていなかった。
ワキ
いかにこの島に流され人のわたり候か。都より赦免のおん使い参りて候。
シテ
なにと都より赦免のおん使とや。流され人はこれに候。
ワキ
これは相国より赦免のおん状にて候。これこれご覧候え。
シテ
あら有難や候。いかに成経。ご赦免のおん状拝見あろうずるにて候。
康頼
そもそもこの度中宮ご産おん祈のため。非常の大赦おこなわるるにより。国国
の流人赦免ある。中にも鬼界が島の流人のうち。丹波の少将成経。平判官入道
康頼。二人赦免せらるるところなり。これは夢かや有難や候。
シテ
あら不思議や。なにとて俊寛をば読み落されて候ぞ。
康頼
おん名はあらばこそ。免状の表をご覧候え。
シテ
さては筆者の誤りか。
ワキ
いや某都にて承り候も。康頼成経二人はおん供申せと仰せ出だされて候。
シテ
なにと俊寛一人この島に残し置けと候や。
ワキ
なかなかの事。
シテ
こはいかに罪も同じ罪。配所も同じ配所。非常も同じ大赦なるに。ひとり誓い
の網にもれて。沈みはてなん事はいかに。
さきに読みたる巻物を。またひき開き同じあとを。
くり返しくり返し。
見れども見れども
ただ成経康頼と。書きたるその名ばかりなり。
もしも礼紙にやあるらんと。巻き返して見れども。
僧都とも俊寛とも。書ける文字はさらになし
こは夢かさても夢ならば。覚めよ覚めよとうつつなき。
俊寛がありさまを見るこそ哀れなりけれ。
時がすぎ、舟に搭乗する時刻になった。成経康頼の二人は嘆く俊寛を「ふり捨てて」舟に乗ろうとし、俊寛も舟に乗ろうと康頼の袂にとりすがった。
シテ
僧都も舟に乗らんとて。康頼の袂にとりつけば。
ワキ
僧都は舟に叶ふまじと。さもあらけなく言いければ。
シテ
うたてやな公の私という事あれば。せめては向いの地までなりとも。情に乗せて
たびたまえ。
ワキ
情も知らぬ舟子ども。櫨櫂をふり上げ打たんとすれば。
シテ
さすが命のかなしさに。また立ち返り出で舟の艫綱に取りつき引き止むる。
ワキ
舟人とも綱おし切って。舟を深みにおし出だす。
シテ
せん方波にゆられながら。ただ手を合はせ舟よのう。
ワキ
舟よといえど乗せざれば。
シテ
力及ばず俊寛は。
地
もとの渚にひれ伏して。
松浦佐用姫も。わが身にはよもまさじと。
声も惜しまず泣き居たり。
終曲部のロンギの謡は俊寛独りが島に取り残されるシーンを謡う。舟上の一行は、都に上れば俊寛の帰洛を申し開くから待てよ、と哀れみの言葉を投げかけるが、その声も次第にかすかになり、跡消えて舟は見えずになったのだった。
待てよ待てよという声も姿も。
次第に遠ざかる沖つ波の。
かすかなる跡絶えて
舟影も人影も消えて見えずなりにけり
跡消えて見えずなりにけり。
『平家物語』はその後の物語を、「巻第九」において詳しく語っている。件の話のその翌年、侍童の有王が俊寛の娘の手紙を携えて、大難儀の末鬼界ヶ島の俊寛のもとを訪れたのであった。そのときの再会を描いた一節。
ある朝、いその方よりかげろふなどのやうにやせおとろへたる者よろぼひ出きたり。もとは法師にて有けると覚えて、髪は空さまへおひあがり、よろづの藻くづとりつゐて、をどろをいたゞいたるが如し。つぎ目あらはれて皮ゆたひ(たるんで)、身にきたる物は絹布のわきも見えず。片手にはあらめをひろいもち、片手には網うど(網人)に魚をもらふてもち、歩むやうにはしけれ共、はかもゆかず、よろよろとして出きたり。(『日本古典文学大系 平家物語上』、岩波書店、233〜234頁)
有王から、都の様子、家族の末路を聞いた俊寛は、いまや都に未練もないと自ら食を断ち、命果てたのであった。
2021年06月25日
辺境の歌 その2 ――能の詞花を訪ねて27
能「善知鳥」は、陸奥外の浜(青森市から津軽半島にかけての一帯の地を明治以前には外の浜(外ヶ浜)と呼んでいた。陸奥湾に面している)を舞台にした曲である。文字通り奥地の物語であり、もう一方の最果ての地「鬼界ヶ島」を舞台とする能「俊寛」と好一対をなしている。外の浜は陸地の果て・国の果てを意味する「率土の浜」に由来すると云われ、中世以前には国の果ての地とされていた。国の東の果ては陸奥国の外の浜であり,西の果ては鬼界ヶ島だったのである。ワキ(旅の僧)は東の最果ての地を訪れようと心にかけて旅をしていたのである。
外の浜の歴史は古く、5世紀允恭天皇の世に勅勘を受けた善知鳥中納言安方がこの地に住み、土地の人々に初めて漁猟と耕作を教えたときから始まるという(もっとも、この時期は天武天皇期に制定された官位制以前なので、中納言はありえない)。また彼は、天照大神の子である三女神を祀る祠を建てたが、これが「善知鳥神社」の始まりとされる。「善知鳥神社」は今日の青森市の発祥の地とされるが、この地には「安潟」と呼ばれる湿地が広がり、神社の付近には「善知鳥沼」があったという。またこの地は長く「善知鳥村」と呼ばれていたが、江戸時代に弘前藩二代藩主津軽信枚によって干拓と港湾建設が行われ、それに伴って「青森村」と改名された。
神社の縁起によれば、善知鳥安方が亡くなると、どこからともなく見慣れぬ鳥が飛んで来、その鳥が「ウトウ」と鳴くと、雛鳥が「ヤスカタ」と鳴き、そのことからこの鳥は善知鳥中納言の魂が再来したものとされ、善知鳥という名が付けられたという。また一説によれば、善知鳥の名前は、チドリに似た鳥が、収穫期になると飛んできて農作物を食い荒らすので、悪いチドリ(悪知鳥)と呼ばれたが、また別のチドリに似た鳥は海にいて大群の魚が岸に近づいたことを教えてくれ、村が栄えたので善いチドリ(善知鳥)だと呼ばれたことに由来するともいう。
能「善知鳥」は善知鳥という名の鳥を狩る猟師の物語であるが、そのいささか凄惨な詞章と舞のゆえに、「阿漕」、「鵜飼」とともに三卑賎の一に数えられる。能には殺戮や戦の場面が謡われる曲がいくつもあるが、この曲は善知鳥の狩りの様子をリアルに描くという点では群を抜いている。とくに、カケリとキリの舞は能の世界では異色の所作が演じられる。
善知鳥はウミスズメ科の海鳥であり(鵜とは別種である)、北太平洋沿岸に広く分布する(北海道天売島は世界最大の繁殖地であり、今日でも数百万羽が営巣している)。体長30㎝ほどの大きさの鳥で、背面は黒褐色、嘴は橙色である。頭部に二本の白い飾り羽がある。繁殖期には嘴の上部に角のような突起が現れる(この突起はアイヌ語でウトウと呼ばれた)ことから、鳥の名が善知鳥と呼ばれたのである。集団で潜水して小魚の群れを追い込み捕食するという狩りをする。繁殖地では断崖の上の砂地や草地にコロニーを作り、1メートル余の穴を掘って巣とする。巣立ちまでの期間、親鳥は夜明け前に一斉に飛び立ち、夕方暗くなった頃、イワシやイカナゴを嘴いっぱいにくわえて、大集団を形成し鳴き声を上げながら帰ってくる。外敵から身を守るためだという(ウィキペディアによる)。また、村田隆太郎によれば、「うとう」の名は「うつほどり」から変遷した可能性が無視できないという。* 同趣旨の説明は『日本国語大辞典』にも見られるが、そこでは「善知鳥」の項の釈義の最後に、「ウトウはうつぼであることをいい、鳥名も穴を掘って巣にするところからいわれたか」という一句が添えられている。善知鳥は親子の情が強い鳥として知られ、雛を捕られた親鳥は血の泪を流してあたりを飛んで回るという言い伝えが残されている。能ではそのような「習性」を舞で表現するのである。
*中世の軍記物語『大塔物語』に「陸奥のそとの浜なるうつほ鳥子はやすかたのねをのみぞなく」という歌が存在するという。(「「善知鳥」再考」、東京学芸大学『学芸国語国文学』50巻、2018年)
諸国一見の僧が、越中立山で禅定(山中での修行)を果たし、「みちのくのはてまで行脚せばやと思い」、山から降りてくると、一人の猟師の亡霊と出会った。物語のはじめにいきなり立山が出てくるのは意表を突かれるが、地獄谷での禅定を描いてシテ安方の堕地獄の苦しみを予兆させようとしたのであろう。亡霊は地獄谷で地獄の苦しみを受けていたのである。亡霊は陸奥外の浜にいる妻子に蓑笠を手向けてほしいと頼み、確かなしるしにと身に着けていた着物の片袖を解き、僧に渡した。
シテ
のうのうあれなるおん僧に申すべき事の候。
ワキ
こなたの事にて候か何事にて候ぞ。
シテ
みちのくへおくだり候わば言伝申し候わん。外の浜にては猟師にて候者の。
去年の春の頃みまかりたる。その妻子の屋をお尋ね候いて。それに候簑笠手向けてくれよと仰せ候え。
ワキ
これは思いもよらぬ事を仰せ候ものかな。届け申すべき事は安き間のおん事にて候さりながら。うわの空に申してはやわかご承引候べき。
シテ
げに確かなるしるしなくては。や。思い出でたり在し世の。
今はの時までこの尉が。木曽(着ると掛ける)の麻衣の袖をとき。
地
これをしるしにと涙をそえて旅衣。涙をそえて旅衣。
たち別れゆくその跡は。
雲や煙の立山(立つと掛ける)の木の芽ももゆる遥遥と
客僧は奥へ下れば。
亡者は泣く泣く見送りて ゆきがた知らずなりにけり
ゆき方しらず、なりにけり。
前場は短く終わり、シテは橋掛りで中入の型をし、余韻を残しつつ幕に入る。後場は外の浜が舞台である。辺境の地を描いた次の詞は、辺土の侘しい情景が伝わってくるなかなか味わいがある一句であろう。
所は陸奥や。
奥に海ある松原の。
下枝(しずえ)にまじる汐芦の。
末ひきしおる浦里の(1)
まがきが島の苫やかた。
囲うとすれどまばらにて。
月のためには外の浜(2)
心ありける住居かな
心ありける住居かな。
(1)松原の下枝あたりにまで汐の満ち干するところに列をなして芦がしおれ倒れている様を謡った。
(2)屋根に葺いた苫が疎らで覆われきれていないので、月の光が住まいの中にまで射し込んでいる、
と謡った。
外の浜(外ヶ浜)はまた歌枕の地としても知られ、多くの歌人によって詠まれたが、善知鳥伝説が都に伝えられ、彼らの辺境への思いを掻き立てたことによるものであろう。とりわけ、後シテの出で謡われる次の歌は、一曲の主題を謡ったものであり、藤原定家の歌とされてきたものである(尤も、出典とされる『夫木抄』にこの歌は見当たらず、伝承を謡曲作者が引歌したものかと思われる)。耳の奥に善知鳥のその鳴き声がいつまでも残るような趣のある歌である。
陸奥の外の浜なる呼子鳥 なくなる声は善知鳥やすかた
また、西行は次のような外の浜に所縁のある歌を詠んでいる。
みちのくの奥ゆかしくぞ思ほゆる 壺の石文外の浜風* (『山家集』西行)
*壺の石(つぼのいしぶみ)は、坂上田村丸の手になると云われる石碑であり、宮城県の多賀城史跡にあり、江戸時代初期に発見された。
子を思ふ涙の雨の笠の上に かかるもわびしやすたかの鳥* (西行)
*能「善知鳥」と同趣旨の内容を歌ったものであるであるから、西行の頃までには外の浜の猟師の物語は知られていたのであろう。。
菅江真澄は善知鳥についてのユーモラスな歌を残しているが、皮肉って歌うことによって暗澹とした物語を救おうとしたのであろうか。
のどけしなそとがはまかぜ鳥すらも 世をやすかたとうたう声して (菅江真澄)
さて、中入の間語(あいかたり)が引き、脇座に控えていたツレ(安方の妻)が嘆きの歌を謡うところへ、旅の僧が外の浜に着いた態でツレと問答し、しるしの袖を示し、蓑笠を正先に置く。僧が供養を行っていると、後シテ(安方の亡霊)が面「痩男」、黒頭、水衣に腰蓑を着けた猟師の姿で登場する。猟師は生前、善知鳥を狩って生計を立てており、親鳥が「ウトウ」と鳴くと雛鳥が「ヤスカタ」と鳴くのを利用して、親鳥の鳴き真似をして雛を捕らえていたという。しかもその猟師は生計のために猟を営むにとどまらず、「品かわりたる殺生」の面白さに明けても暮れても狩りをするというあり様であった。
シテ
ただ明けても暮れても殺生をいとなみ。
地
遅々たる春の日も所作たらねば時をうしない。秋の夜長し夜ながけれども。
いさり火白うして眠る事なし。
シテ
九夏の天も。暑を忘れ。
地
玄冬の朝も寒からず。
(クセ)
鹿を追う猟師は。山を見ずといふ事あり。
身の苦しさも悲しさも。忘れ草のおい鳥。
たか縄(1)をさし引く汐の。
末の松山風あれて。袖に波こす沖の石。
または干潟とて。
海ごしなりし里までも。ちかの塩竃身を焦がす。(1)
むくいをも忘れける ことわざ(事業)をなしし悔しさよ。
そもそも善知鳥やすかたのとりどりに。品かわりたる殺生の。
シテ
なかに無慙やなこの鳥の。
地
おろかなるかな筑波嶺の。
木木の梢にも羽をしき 波の浮き巣をもかけよかし。
平砂に子を産みて落雁の。
はかなや親はかくすと。すれど善知鳥と呼ばれて。
子はやすかたと答えけり。
さてぞ取られやすかた。
(1)鳥を捕らえるために縄にモチをつけて高いところに張っておくもの。
(2)嵐で風が強く袖が高波に洗われるようなときも、海越しではあるが里までほど近い干潟で身
を焦がすほどに夢中になって猟をしたものだ。「末の松山」、「沖の石」、「千賀の塩竈」は
いずれも陸奥(宮城県)ゆかりの史跡の名。
亡霊は、無惨な殺生の報いに死後は地獄に堕ちて、化鳥となった善知鳥に責め苛まれ続けていると訴える。そして我が子のところへ歩み寄ろうとするが、横障の雲(妨げの雲)に隔てられて子はかき消えてしまう。そして、僧の前で善知鳥の狩りの様を演じ、成仏の救いを訴えながら、かき消すように失せてしまうのである。この亡霊が救われたか否かは能では語られない。救われることがないまま終曲を迎える数少ない能の一つである。
地
親は空にて血の涙を。
降らせばぬれじと菅簑や。
笠をかたむけここかしこの。
便りを求めて隠れ笠。
かくれ簑にもあらざれば。
なお降りかかる血の涙の。
目もくれないに染み渡るは。
紅葉の橋の。かささぎか。
娑婆にては善知鳥やすかたと見えしも。
善知鳥やすかたと見えしも
冥途にしては化鳥となり
罪人を追っ立て鉄(くろかね)の。嘴をならし羽を叩き。
銅(あかがね)の爪を研ぎたてては眼を掴んで肉(しし)むらを
叫ばんとすれども猛火の煙にむせんで声を
あげえぬはおし鳥を殺しし科やらん
遁げんとすれど立ちえぬは。
羽抜け鳥の報いか。
シテ
善知鳥はかえって鷹となり。
地
我は雉子とぞなりたりける。
のがれがたのの狩場のふぶきに
空も恐ろし 地を走る。
犬鷹にせめられて
あら心 善知鳥やすかた
やすき隙なき身の苦しみを。
助けてたべやおん僧
たすけてたべやおん僧と
いうかと思えば失せにけり。
キリの仕舞は、血の泪を降らせる親鳥から逃げ回り隠れる様子、地獄で一転して怪鳥となった善知鳥によって身を苛まれる様子を描いて、面白尽くの舞であり目が離せない。殺生を所作と詞章によってドラマチックに昇化させた舞台は、「見ても聞いても面白い。名能である。」(謡本『善知鳥』梗概)
2021年04月12日
辺境の歌 その1 ――能の詞花を訪ねて26
辺境という言葉にはあるノスタルジアが伴う。そこには、遥かな空間の彼方への追
想と言おうか、あるいは奥界の地にたいする畏怖と言おうか、たんなる距離感を越え
た精神的な含意が湛えられている。辺境の反対は中心である。人は中心に価値を認め
ようとするが、むしろ周囲世界にこそ大地の広がりがあり、多様の豊かさがあると言
えなくもない。鄙には都に簒奪される諸価値の源泉がある。中心には重力的な求心力
が集積するが、周囲にはいわば加重から放たれた多様な「大地との契約」があるの
だ。人はそれを土着という。
能の世界では、陸奥
は最果ての地、辺土であり、はるかな旅を経てたどりつく地、
白河の関のさらに奥の地であった。この陸奥の地を舞台とする曲が、現行曲にはいく
つかある(さらに番外曲を含めると一つの豊かなジャンルを形成するだろう)。「善知
鳥」、「錦木」、「実方」、「黒塚」、「遊行柳」。これらの曲は辺境の地の面影をそれぞれ
の物語をつうじて私たちに示してくれている。そこには、都や畿内とは異なるある種
の静謐の空間、土着性と呼んでよいような隔絶した生活空間が立ち現れるのを見てと
ることができるであろう。
「錦木」はそのような陸奥の抒情をたたえた世阿弥の珠玉の作品である。開口で、
諸国一見の僧が辺境への慕情に惹かれたのであろうか、陸奥の果てまで行脚しようと
語りだす。作者自身の辺境への想いが謡われたのであろう。多くの能に見られるよう
に、遠国の地を訪れるのは旅の僧(遊行僧)である。彼らは中世の大地をさまよい巡
る遊行者(巡礼者)であり、それどころか所々の土地の霊たちと交感する霊媒人でも
あった。
ワキ
われいまだ東国を見ず候ほどに。ただいま思い立ち陸奥の果てまで行脚せばや
と思い候。
〽いずくにも心とめじと行く雲の。心とめじと行く雲の。
旗手も見えて夕暮れの 空も重なる旅衣。
奥はそなたか陸奥の。
狭布の里にも着きにけり。狭布の里にも着きにけり。
陸奥には、歌や謡で親しまれたゆかりの地、名所が多くある。松島や千賀の塩竈は
名所の花というべく人口に膾炙した地であり、都人のあこがれの地であった。また、
「安積の沼」や「しのぶもじずり」は歌枕として愛好された遠路の地であった。そし
て、狭布の里もまた細布と錦木塚で知られた床しい奥地だったのである。
シテツレ
ここはまた心の奥か陸奥の
狭布の郡の名にし負う。
細布の。色こそ変われ錦木の。
千度百夜いたずらに。
悔しき頼みなりけるぞ。悔しき頼みなりける。
ワキ
ふしぎやなこれなる市人を見れば。夫婦とおぼしくて女性の持ちたまいたる
は。鳥の羽にて織りたる布と見えたり。また男の持ちたまいたるは。薪かと思え
ば美しくいろどり飾れる木なり。いずれもいずれも面白き売り物なり。さてこれ
は何と申したる売り物にて候ぞ。
ツレ
これは細布とて機ばり狭き布なり。
ツレ
これは錦木とて美しく色どり飾れる木なり。いずれもいずれも当所の名物なり
これこれご覧候え
「錦木」は陸奥鹿角の地に伝えられた錦木伝説にもとづいて作られた曲である。ま
づは、伝説を秋田県の資料によって見てみよう。
当時は、男性が好きな女性の家の前に錦木を置き、その錦木を女性が拾って家の中に入れ
た場合は、結婚してもよいという意味の決まりがあった。ある日、若者は市日のときに政子
姫を初めて見て、その美しさにひかれ恋いこがれてしまった。若者は、翌日から毎日毎日、
雨の降る日も風の吹く日も雪の吹雪く日も一日も休まず、政子姫の家の門の前に錦木を持っ
てきては立てた。しかしながら、錦木は一度も拾われて家の中に入れられることはなく、家
の前に立てられたまま増えるばかりであった。そのたびに若者は草木(里の名)へ戻る帰り
道のそばの小川で、涙を流して泣いた。その川は、のちに涙川と言われるようになった。一
方、政子姫は、家の門の前に毎日錦木を立てられているうちに、機織りする手を止め、こっ
そり若者の姿を見るようになっていた。そして、いつの間にか、政子姫も若者を好きになっ
ていた。だが、いくら若者が錦木を立てても、身分が違うことや、もう一つ重大な訳があっ
て結婚の約束はできなかった。その訳というのは、次のようなことである。
当時、五の宮岳の頂上に巣を作っている大ワシが里に飛んできては子供をさらっていた。
あるとき、若い夫婦の小さい子供が大ワシにさらわれて村人がとても悲しんでいたとき、あ
る一人の旅の坊さん、「鳥の羽根を混ぜた織物を織って子供に着せてやれば、大ワシは子供
をさらっていかなくなる。」と教えてくれた。布に鳥の羽根を混ぜて織ることは非常に難し
く、よほど機織りがうまくなければできないものであった。そのため、機織りの上手な政子
姫は皆からお願いされていた。政子姫は、子供をさらわれた親の悲しみを自分のことのよう
に思い、3年3月を観音様に願かけしながら布を織っていたのだった。その願かけのため
に、政子姫は若者と結婚する約束ができなかったのである。
若者は、そういう理由も知らず、毎日せっせと3年もの間、錦木を姫の家の前に立ててい
た。あと一束で千束になるという日に、体がすっかり弱くなった若者は、門の前の降り積も
った雪の中に倒れて死んでしまった。政子姫は非常に悲しみ、それから2、3日後に、若者
の後を追うように死んでしまった。姫の父親の大海は、2人をとっても不憫に思い、千束の
錦木と一緒に、一つの墓に夫婦として埋葬した。その墓が後に錦木塚と呼ばれるようになっ
たものである。(pref.akita.lg.jp、鹿角地域振興局編)
岩井美千子によれば、能因法師の次の歌が都の人々に大きな影響を与えて以来、
「にしき木」と「けふの細布」は陸奥という辺境の地名とともに、悲恋を語る品々と
して多くの歌に詠まれてきたという。「能因の歌が、都の人々に大きな影響を与え
て、「にしき木」は「けふの細布」と組み合された陸奥のもの、という発想ができて
いったと考えられる。こうして、東国から陸奥を旅したごく少数の人たちによる僅か
な報告が、都の人々に遠い国の見知らぬ民の不思議な風習として伝えられると、それ
はかれらの作歌活動に新しい素材を与え、その結果、歌のことばとして定着してゆ
く。その一方で、このよくわからないものどもの正体について、都人はたまたまもた
らされる情報を頼りに推測し続ける。これらの成果が、美しく彩られた木や、鳥の羽
を織り込んだ布のイメージなのであり、さらには「けふの郡」という新しい地名であ
った。」岩井美千子「錦木塚の考察(上)」、Artes Liberalis (岩手大学人文社会科学部紀要)、No.44、
1989)
錦木はたてながらこそ朽ちにけれ 狭布の細布胸あはじとや(後拾遺集 能因法師)
狭布(けふ)の地名は当時の郡名にはないとされるが、南部鹿角毛馬内の錦木塚から
仮想された地名とも、津軽に同名の地があるともいう。「錦木」と「細布」につい
て、彼女は次のような資料を紹介している。
錦木塚は、今鹿角郡花輪村と毛馬内村との間にあり。其所にいひ伝へしは、むか
しそこのならはしにて、思ふ女の門に錦木といふものをたてて、けさうのしるしと
せしとなん。さてむかしおもひかはせる男女ありて、錦木を立しかど逢がたきよし
有て、終に二人ともに身まかりしかば、おなし所に葬りて塚をきつきたりとぞ、其
はこのにしきぎ塚なりとなん。(『南部藩旧蹟遺聞』)
このけふの細布といへるは、これもみちのくにに鳥の毛しておりけるぬのなり。
おほからぬものして織りける布なれば、はたばりもせばくひろも短ければ、上にき
る事はなくて小袖などのやうに下にきるなり。さればせなかばかりをかくして胸ま
ではかからぬよしをよむなり。(『俊頼髄脳』)
さて、この東の果ての、陸奥の奥にあるという「狭布」の里の悲恋の話を、都の
歌人たちは競い合って歌に詠んだのである。そのいくつかを取り上げてみよう。
おもひかね今日たちそむる錦木の 千束にたらであふよしもかな堀河百首・詞
花集 大江匡房)
錦木は千束になりぬ今こそは 人に知られぬ閨の内見め(袖中抄)
錦木の千つかの数はたててしを など逢ふことのいまだただなる(堀河百首 顕仲)
みちのくのけふの細布程せばめ 胸あひがたき恋もするかな(俊頼口伝)
陸奥の狭布のさぬののほどせばみ まだ胸あはぬ恋もするかな(古今和歌六帖)
たてながら数のみつもる錦木の ともにわがなも朽ちぬべきかな(待賢門院堀川)
錦木の千束の数にけふみちて 狭布の細布胸やあふべき(藤原俊成)
細布の胸あはざりしいにしへを 問へばはたおる虫ぞ鳴くなり(西行)
あらてくむ門にたてたる錦木は とらずはとらずわれや苦しき(俊頼髄脳 古歌)
若くして世を去った石川啄木は、まだ二十歳にも届かない多感な日に鹿角の地を訪
れ、抒情的な詩を表した。
鹿角の国を懐ふの歌
青垣山を繞
らせる 天さかる鹿角の国を忍ぶれば
涙し流る今も猶 錦木塚の銀杏の樹
月よき夜は夜な夜なに 夏も黄金の葉と代り
代々に伝へて新らしき 恋の譚
も梭
の音も
風吹きゆけば吹きくれば 枝ゆ静かに
月の光の白糸の 細布をこそ織ると聞け
・・・中略・・・
鹿角の国を忍ぶれば 涙し流るその川に
斎
心の肌浄め 朝な夕なに研かれて
み目も涼しき色白の 鹿角少女が夕づとめ
肩にま白き雲纏ふ 逆鉾杉の神寂びし
根にむら繁る大木の 中に神住む古御堂
壁の墨絵の大牛も 浮きてし見ゆる日暮時
樹がくれ静む秋の日の 黄に曳く摺裳みだれ這ふ
石階ふみて静々と 供御の神米捧げつゝ
伏目に上る麻ぎぬが 藁つかねせし黒髪に
神代の水の香こそすれ かへしの足の小走りに
杉の陰路をすたすたと 露にぬれたる真素足に
行きこそ通へはらゝかす 袖に葉洩れの日を染めて
神の使のダンブリ(トンボ)が いのちの水の源を
告げに来る日をさながらに 青駒かへる背が門へ
その敬虔
さ美しさ 米白川と諸共に
流れ絶えせぬ風流の 錦木立てし若児らが
色にも出る心映え 神代のまゝを目のあたり
見ると思へば涙し流る (三十八年十二月五日夜)
さて、旅の僧の前に現れた夫婦と思しき二人の若い男女は、錦木と細布に込められ
た思いを語り出す。
ワキ
さてさて錦木細布は。恋路によりたるいわれよのう。
シテ
なかなかなれや三年まで。とりおく数の錦木を。日ごとにたてて千束ともよ
み。
ツレ
また細布は機ばり狭くて。さながら身をも隠さねば胸あいがたき恋とも詠み
て。
シテ
恨みにも寄せ。
ツレ
名をも立てて。
シテ
逢わぬを種と。
シテツレ
詠む歌の。
地
錦木は立てながらこそ朽ちにけれ。
立てながらこそ朽ちにけれ。
狹布の細布。胸あわじとやと。
さしも詠みし細布の。
機ばりもなき身にて。
歌物語恥かしや。
なお事の子細を問う僧に、シテは舞台正面に出て下に居、居語りとなる。
昔よりこの所の習いにて。男女のなかだちにはこの錦木を作り、女の家の門に立つ
るしるしの木なれば。美しくいろどり飾りてこれを錦木という。さるほどに逢うべ
き男の錦木をば取り入れ、逢うまじきをば取り入れねば。あるいは百夜三年までも
立てしによって。三年の日数つもるをもって千束とも詠めり。またこの山陰に錦塚
とて候。これこそ三年まで錦木立てたりし者の古墳なれば。取りおく数の錦木とも
に塚に築きこめて。これを錦塚と申し候。
僧を錦塚に案内した夫婦は塚の内に消えてしまった(中入。シテは塚の中に入り、
ツレは後見座にくつろぐ)。中入後、草の枕に安らう僧の夢のなかに、ツレとシテが
現れ、ツレは呼びかけ、シテは塚の中から謡い出す。姿を表し給えと乞う僧の言葉
に、シテは塚から現れ、入れ替わってツレが塚の中に入る。作り物の塚は女が機を織
る屋敷に変わり、男は錦木を手に作り物に向かう。
ツレ
女は塚のうちに入りて。秋の心も細布の機物を立てて機を織れば。
シテ
夫は錦木取り持ちて。さしたる門をたたけども。
ツレ
うちより答うることもなく。ひそかに音する物とては。
シテ
機物の音。
ツレ
秋の虫の音。
シテ
聞けば夜声も。
ツレ
きり。
シテ
はたり。
ツレ
ちょう。
シテ
ちょう。
地
きりはたりちょうちょう。きりはたりちょうちょう。
機織松虫きりぎりす。つづりさせよとなく虫の。
衣のためかな侘びそ おのが住む野の千種の糸の
細布織りてとらせん。
「松虫」などでも謡われる「きり はたり ちょう」は虫の音の擬音であるととも
に、機を織る音をも表している。およそ物の音の形容のなかでももっとも美しいもの
である。男は門に立ち、女はひたすら機を織るという情景を謡うのである。謡はその
ままクリに入り、「千たび百夜」通いのあわれを謡いあげる。深草少将は百夜通いで
あったが、錦木の男は千たびも思いの数を積もらせたのである。次のクセの詞章は
「狭布の細布胸あはじ」の言葉さながらに、行き違いの恋に絶叫する男の心を謡い上
げたものとして、私たちの心を打つ。
地
夫は錦木を運べば。女はうちに細布の。
機織る虫の。音にたてて 問うまでこそなけれども。
互いに内外にあるぞとは。知られ知らるる中垣の。
草の戸ざしはそのままにて。
夜は既に明けければ すごすごと立ち帰りぬ。
さるほどに思いの数も積もりきて。
錦木は色朽ちて さながら苔に埋もれ木の。
人知れぬ身ならば。かくて思いも留まるべきに。
錦木は朽つれども。名は立ち添いて逢うことは。
涙も色に出でけるかや。恋の染め木とも
この錦木を詠みしなり。
シテ
思いきや。しじのはしがきかきつめて。
地
百夜も同じまろ寝せんと。詠みしだにあるものを。
せめては一年
待つのみか。
二年あまりありありて はや陸奥の今日までも。
年くれないの錦木は。千たびになればいたずらに。
われも門辺に立ちおり。錦木とともに朽ちぬべき。
袖に涙のたまさかにも。などや見みえたまわぬぞ。
さていつか三年は満ちぬ。あらつれな つれなや。
* 思ひきやしぢのはしがきかきつめて 百夜も同じまろ寝せんとは(千載和歌集
藤原俊成) なお、深草少将の百夜通いを描いた曲に「通小町」がある。
千束になったその日、男は機織る女に会えるかと狂想し早舞を舞う。亡霊はわれに
還ったのであろうか、わが身を恥じて消えたかと見て、僧の夢は覚めたのであった。
2021年03月01日
「当麻」と曼陀羅 ――能の詞花を訪ねて25
「当麻」は時正の日の物語である。金春安明師はこのことについて次のように指摘
されている。「能《当麻》に、旧暦二月十五日でしかも春分(時正)だというのはそうザラには出逢えないめずらしい現象なのです。……太陽の動きに拠る春分と、月の満ち欠けによる旧暦二月十五日満月が重なるということは、《当麻》の化尼化女の出現に値する、希少な現象なのです」(『金春月報』金春円満井会内金春月報編集部、二〇一三年三月号/五月号)。時正は昼と夜の長さが同じ日、すなわち春分と秋分を指す言葉であるが、「当麻」が物語るその日は釈迦入滅の旧暦二月十五日でしかも春分という稀な日だったのである。しかし、ここに当麻曼陀羅誕生の秘密があることはあまり注目されていない。
シテツレ(老女と女、じつは化尼化女)
こよいしも二月中の五日にて。しかも時正の時節なり。
法事をなさんため今この寺に来りたり。
地法事のために来るとは。そもやいかなる御事ぞ。
シテツレ今は何をかつつむべき。そのいにしえの化尼化女の。
地夢中に現じきたれりと。
シテツレいいもあえねば。
地光さして。花ふり異香くんじみちて。音楽の声すなり。
はずかしや旅人よ。いとま申して帰る山の。
二上の嶽とはふたがみの。山とこそ人はいえど。
まことはこの尼が。のぼりし山なる故に。
尼上のだけとは申すなり。
老の坂をのぼりのぼる。
雲に乗りてあがりけり. 紫雲にのりてあがりけり。
旧暦二月中の日は満月であり、満月のような太陽が西に沈めば、太陽のような満月が東の空から登る。当麻寺は二上山の東方にあり(もっとも、真東に位置するのではない)、この日、寺の近郊からは二上山の雄岳と雌岳のコルに沈む夕陽を拝むことができる。この春分の日に西に沈む太陽に向かって阿弥陀仏を念じつつ祈りを捧げることを日想観という。中将姫は二上山に沈む彼岸中日の入り日を一心不乱に拝み、祈ったのであろう。そしてその時、眩しい残照の光が二上山のそのいただきの間に輝線を放つのを見たのであろう。そして、その残照のなかに弥陀如来のその豊かな顔と上半身が浮かび上がるのをたしかに見届けたのであろう。
折口信夫の『死者の書』は、藤原郎女(中将姫)が二上山に沈む陽光に惹かれるかのように当麻寺にあくがれ 来て、廬 に籠って曼陀羅を織り上げるという幻想的な話を物語る小品である。その一節に、春分の日の夕刻に二上山に沈む入り日を彼女が眺めた一節がある。
(去年の春分の日の事であった。入り日の光りをまともに受けて、姫は正座して、西に向って居た。日は、此屋敷からは、稍 坤 によった遠い山の端に沈むのである。西空の棚雲の紫に輝く上で、落日は俄に転 き出した。その速さ。雲は炎になった。日は黄金の丸 になって、その音も聞えるか、と思うほど鋭く廻った。雲の底から立ち昇る青い光りの風――、姫は、じっと見つめて居た。やがて、あらゆる光りは薄れて、雲は霽 れた。夕闇の上に、目を疑うほど、鮮やかに見えた山の姿。二上山である。その二つの峰の間に、ありありと荘厳な人の俤 が、瞬間顕れて消えた。後は、真暗な闇の空である。山の端も、雲も何もない方に、目を凝して、何時までも端坐して居た。郎女の心は、其時から愈々澄んだ。併し、極めて寂しくなり勝って行くばかりである。
また、彼は他のところで「山越しの阿弥陀像の画」について語っている。この絵は鎌倉時代からいくつかの寺社に残されている阿弥陀像の一つであり、山の稜線から上半身を表した阿弥陀仏を描いたものである。山の外輪に添って立ち並ぶ峰の松原が描かれ、その松原越しに阿弥陀仏が描かれている。彼は、この画には〈日本人が持って来た神秘観の元頭〉があるという。弥陀が山の向こうからぬっと姿を表しだしたその姿はたしかに神秘の極みである。しかも中将姫が入り日を見たのは彼岸の中日である。二上山に向かって日想観を念じていた彼女の心には、まさしく満月のような入り日が沈みゆきその最後の輝線を残すとき、逆に山の向こうから光が指し出で、その光の中から阿弥陀仏の頭、顔、胸が浮かび上がってくるのが見えたのであろう。彼女は煌々と輝く月の下で夜もすがら祈りを捧げ、黎明が帳を破るころ、今度は二上山に沈む丸い月をも拝んだに違いない。
*日想観については「弱法師」でも謡われている(本シリーズの19「盲目のあわれ」)。また、観無量寿経に次の一節がある。「汝及び衆生応 に心を専らにし、念を一処に繋けて、西方を想ふべし。云はく、何が想をなすや。凡想をなすとは、一切の衆生、生盲に非るよりは、目有る徒、皆日没を見よ。当に想念を起し、正坐し西に向ひて、日を諦 らかに観じ、心を堅く住せしめ、想を専らにして移らざれ。日の歿せむとするや、形、鼓を懸けたる如きを見るべし。既に見已 へば目を閉開するも、皆明了ならしめよ。是を日想となし、名づけて、初観といふ。」
能「当麻」の世界は、今日の私たちには思い及ばないほどの宗教的献身の世界が描かれている。祈りということへのこれほどの帰依が語られることに私たちは驚異するのである。たしかに「当麻」は宗教的心性の美しさを描きあげた点では比類のない作品である。
廻国の僧が三熊野に参籠し、それより都に向かう途次当麻寺に参詣していると、老尼が若い女を連れ、弥陀の教えを讃え念仏を称げた。次は前シテの出の謡であるが、念仏を称えれば「ほとけも我もなかりけり。なむあみだぶの。声ばかり。」と謡うその詞章は「当麻」全曲の導入にふさわしいものであろう。
シテ(老尼)
一念弥陀仏即滅無量罪とも説かれたり。
ツレ(女)
八万諸聖教皆是阿弥陀ともありげにさむらう。
シテ
釈迦はやり。
ツレ
弥陀は導く一筋に。
シテツレ
ひと筋にこころゆるすな。南無阿弥陀仏と。
シテ
称うれば、ほとけも我もなかりけり。
ツレ
なむあみだぶの。声ばかり。
シテツレ
涼しきみちは。たのもしや。
シテとツレは、「大和国当麻寺縁起」などで語られる化尼と化女の物語を模したものと思われる。中将姫が「生身の阿弥陀如来を拝みたい」と一心不乱に祈っていたところ、阿弥陀如来が観音を伴い化尼化女となって姫の前に表れた。そして化尼が蓮茎から糸を紡ぎ、化女が観無量寿経の教えを表す曼荼羅を織り、無節の竹を軸にして掛け、去ったという。この説話が中世には、中将姫が五色の蓮糸を用い、一夜にして「当麻曼荼羅」を織り上げたというストーリーに変容して定着するのである。当麻曼荼羅は根本曼荼羅とも呼ばれ、当麻寺の本尊である。観無量寿経に示された十六の観法のうち十三を描いている。曼陀羅は蓮糸で織られたものではなく、絹糸で織り上げられた綴織であり(したがって摺り込みでも刺繍でもない)、天平の時代(天平宝字七年
(763年))に唐から伝えられたものだという。観無量寿経では、頻婆娑羅 王の王妃
韋提希 の物語が語られるが、それが中将姫物語のモデルになったとされる。韋提希が釈尊に極楽浄土を「自力」で見ることを乞うたところ、十六の観法を示されたという。
*十六観法のうち主要な十三の観法は、日想観(落日を観想する)、水想観、地想観、宝樹観、宝池観、宝楼観(極楽にあるという瑠璃池の水面と大地、樹木、地形、楼閣を観想する)、華座観(蓮の花を観想する)、像想観(蓮の花に座している無量寿仏を観想する)、真身観(無量寿仏の真の姿を観想する)、観音観(観音菩薩の姿を観想する)、勢至観(勢至菩薩の姿を観想する)、普想観(自身が往生して蓮の華のなかに坐している姿を観想する)、雑想観(無量寿仏像が池水の上に在すのを、それまでの観想をもとに観想する)。
さて、称讃浄土経を称える長い登場の謡を経て、舞台はワキとシテ・ツレとの問答に移るが、話は中将姫伝説の核心である当麻曼荼羅の誕生に向かう。
ワキ(僧)
いかにこれなる人々に尋ね申すべき事の候。
シテ こなたのことにて候か何事にて候やらん。これは念仏すすむる者にて候。念仏
を御申し候え。
ワキ
念仏は教えのごとく申し候べし。さてあれに見えたるは當麻寺にて候か。
シテ さん候゛あれこそ當麻寺にて候え。この寺をば染寺と申し候。中将姫はすのい
とを染めたまいしによって。そめでらと申し候。
ツレ
またこれなる池は蓮の糸を。染めたまいしその故に。染殿の井とも申すとか
や。
シテ
あれは當麻寺。
ツレ
これは染寺。
シテ
またこの池は
ツレ
染殿の。
シテツレ
いろいろさまざま所どころの。法の見仏聞法ありとも。 それをもいさや白糸の。
唯ひと筋ぞ一心不乱に南無あみだぶ。
ワキ
げに有がたき人の心。それこそ則みだ一教なれ。又是に見えたる花桜。常の色
には変りつつ。是も故ある宝樹と見えたり。
ツレ
げによく御覧じとがめたり。これこそ蓮の糸を染めて。
ツレ
掛けてほされし桜木の。花も心のある故に。蓮の色にさくといえり。
そして舞台は当麻曼陀羅誕生の秘話に進んでいく。寺に籠った中将姫は「正身の弥
陀」を拝ませ給えと一心不乱に祈りを捧げた。さながら韋提希が幽閉された宮殿の牢
のごとく、姫は自ら草庵を牢となし、「称名観念の床の上」に、季節を忘れ昼夜を忘
れて祈ったのである。
地
そもそもこの當麻の曼陀羅と申すは。人皇四十七代の帝。廃帝天皇の御宇かと
よ。横佩の右大臣豊成と申しし人。
シテ
その御息女中将姫。この山に籠り給いつつ。
地
称讃浄土経。毎日讀誦し給いしが。心中に誓い給うよう。
シテ
願わくは生身の弥陀来迎あって。
地
我に拝まれおはしませと。一心不乱に観念し給う。
シテ
しからずば畢命を期として。
地
この草庵を出でじと誓って。一向に念仏三昧の定に入り給う。
続くクセは、中将姫の前に現れた老尼と若い女が化尼化女(弥陀如来と観音)であ
ることを謡うが、舞台のシテ・ツレは弥陀如来と中将姫であるようでもあり、もっぱ
ら中将姫の秘話を謡う。次はクセの詞章である。
地所は山陰の。
松吹く風も涼しくて。さながら夏を忘れ水の。
音も絶えだえに心耳を澄ます夜もすがら。
称名観念の床の上。座禅円月の窓の内。
寥廖とある折ふしに。一人の老尼の忽然ときたりたたずめり。
これはいかなる人やらんと。尋ねさせ給いしに。
老尼答えて宣わく。
誰とはなどやおろかなり。呼べばこそ来りたれと。
仰せられけるほどに。
中将姫はあきれつつ。
シテ 我は誰をか呼子鳥。
地 たつぎも知らぬ山中に。声たつる事とては。
南無阿弥陀仏の称えならで。又他事もなきものをと。
答えさせ給いしに。
それこそわが名なれ。声をしるべに来れりと。
宣へば姫君も。さてはこの願成就して。
正身の弥陀如来。げに来迎の時節よと。
感涙肝にめいじつつ。
綺羅衣の御袖も。しおるばかりに見え給う。
化尼は、自らが出現したのは「こよいしも二月中の五日にて。しかも時正の時節なり。」と、法事をなすべき特別の日であることを示して、紫雲に乗り尼上の岳に上がり消えていった。化尼化女を呼び出したのは中将姫の常軌を超える祈りの力であった。しかし、「その時」に現れたのは二月中の日の時正という時節の符号によるものであった。ところで、化尼と化女は弥陀如来と観音であるが、ワキの前に現れたのはシテとツレ、老尼と若い女である。弥陀如来である老尼が中将姫に代わって身の上を語るのはやや違和感を招き、またツレは一般に観音とされているが、中将姫とみなすことも可能であり、能のストーリーが二重重ねとなっていると言うべきであろう。むしろ神秘感を漂わせようとする世阿弥の蠟化作戦によるものであろうか。 後場のシテは老尼に代わって中将姫その人の精魂となる。
シテ
(中将姫) 唯今夢中に現れたるは。中将姫の精魂なり。
われ娑婆にありし時。
称讃浄土経。朝暮おこたらず。信心誠なりし故により。
微妙安楽世界の衆となり。
本覚真如の円月に坐せり。
しかれども。ここをさること遠からずして。
己身却来
(1)の法味をなす。
地
ありがたや。盡虚空界 の荘厳は。眼雲路にまよい。
シテ
転妙法輪の音声は。聴宝刹
にみてり。(2)
地 蕭然とある暁のこころ。
シテ まことに涼しき。道に引かるる光陰のすえ。
地 おしむべしやな。おしむべしやな。
時は人をも待たざるものを。
すなわちここぞ。唯心の浄土経。
いただきまつれや。いただきまつれや。攝取不捨。
(1)我が身をこの娑婆の世に現すこと。
(2)源信『往生要集』の「盡虚空界之荘厳、眼迷雲路、転妙法輪之音声、聴満宝刹」を引い
た。弥陀の浄土の空一面を覆い尽くす飾りは見とれてどれがどうと見分けがつかぬほど、
弥陀説法の妙音は、聴くに国中に充満している。(伊藤正義『謡曲集 中』(新潮日本古典
集成)の訳による)
舞台はこの先、称讃浄土経を称える神妙な大ノリの謡に続いて早舞となる。早舞ではあるが、中将姫がこの経典に捧げる歓喜の舞であるから、優雅に舞うべきであろう。シテが祈りの舞を舞ううちに能は終わる。小林秀雄は「当麻」なる少文を残しているが、後シテのこの舞について次のような言葉を残している。
(中将姫のあでやかな姿が、舞台を縦横に動き出す。それは、歴史の泥中から咲き出でた花の様に見えた。人間の生死に関する思想が、これほど単純な純粋な形を取り得るとは。僕は、かういふ形が、社会の進歩を黙殺し得た所以を突然合点した様に思つた。要するに、皆あの美しい人形の周りをうろつく事ができただけなのだ。あの慎重に工夫された仮面の内側に這入り込むことは出来なかつたのだ。世阿弥の「花」は秘められてゐる、確かに。(「当麻」)
地
地 後夜の鐘の音。鳧鐘
の響。
称名の妙音の見仏聞法いろいろの法事。
げにもあまねし。
光明遍照十方の衆生をただ西方に。むかえゆく。
御法の舟の水馴れ棹。
御法の舟の。さを投ぐる間の。
ゆめの。夜はほのぼのとぞ。なりにける。
『死者の書』から、郎女が曼陀羅を描き上げる場面の文章を引いておこう(物語では中将姫が曼陀羅を描いたことになっている)。弥陀の姿を間近に見た郎女は、侍女たちの集めた蓮茎の糸を夜すがら織り続け、織り上がった布に無心でその影向した姿を描きあげる、と物語は進んでいく。
女たちの噂した所の、袈裟で謂えば、五十条の大衣 とも言うべき、藕糸 の上帛(はた)の上に、郎女の目はじっとすわって居た。やがて筆は、愉しげにとり上げられた。線描 なしに、うちつけに絵具を塗り進めた。美しい彩画 は、七色八色の虹のように、郎女の目の前に、輝き増して行く。姫は、緑青を盛って、層々うち重る楼閣伽藍の屋根を表した。数多い柱や、廊の立ち続く姿が、目赫 くばかり、朱で彩 みあげられた。むらむらと靉 くものは、紺青の雲である。紫雲は一筋長くたなびいて、中央根本堂とも見える屋の上から、画きおろされた。雲の上には金泥の光り輝く靄が、漂いはじめた。姫の命を搾るまでの念力が、筆のままに動いて居る。やがて金色の雲気は、次第に凝り成して、照り充ちた色身――現し世の人とも見えぬ尊い姿が顕れた。 郎女は唯、先の日見た、万法蔵院の夕の幻を、筆に追うて居るばかりである。堂・塔・伽藍すべては、当麻のみ寺のありの姿であった。だが、彩画の上に湧き上った宮殿楼閣は、兜率天宮 のたたずまいさながらであった。しかも、其四十九重の宝宮の内院に現れた尊者の相好は、あの夕、近々と目に見た俤びとの姿を、心にとめて描き顕したばかりであった。
2020年12月15日
松虫追想 ――能の詞花を訪ねて24
「松虫」は不思議な曲である。綾をつくした趣のある詞章の土台をなすはずの筋の展開が明確な輪郭を為さず、曖昧さとおぼろ感から逃れることができないのである。
難曲である。まずは詞章から見よう(松虫は今日の鈴虫であるが、近世に入ってその名が逆転した)。
とある酒屋に男連れが夜な夜な訪れるところを、主人が不審に思い問えば、男は次のように語った。
昔二人の男が阿倍野を通りかかったとき、一人の男が松虫の声に惹かれて原に分け入って消えたが、いま一人の男がやや久しく待っていても戻ってこないので、探し求めて原を分け行けばその男は草露に伏していた、男は嘆き悲しんでその亡骸を土中に埋めたが、松虫の音を聞くとその友のことが偲ばれるのだという。
そして亡霊となった今も友を偲んで現れたのだと言って消えてしまった。後段は、主人が弔っていると亡霊がふたたび現れ、友を忍び酒を讃えて、松虫の音に舞い遊ぶうちに、朝の原に消えていった……。
「松虫」は、男の友情、そして酒を讃える曲として愛好されているが、曲の重心はそれらにあるのではない。全曲に松虫の音が響き渡るなかで、一人の男が松虫の鳴く原に行き倒れになるという不可解な事件が闇箱となって、その周りを茫洋とした言葉と謡の雲が漂い、幽玄の心象空間を現出させるところにこの曲の精髄があるのだ。
この事件については何も語られないまま、今は亡霊となったもう一人の男が酒屋の主人と往時を忍ぶのである。
友情が讃えられ酒が酌み交わされるという静かな時が過ぎ行き、そして松虫の音が冥々に響く夜もいつしか明けて、阿倍野の原にはなお虫の音ばかりが残っていた、と謡われるのである。
この能は物語る曲ではなく、松虫の音が浮かび上がらせる茫漠とした風情と情感を言表すべく詩作されたものなのであろう。
むしろその茫洋さが夢幻能のその名にふさわしく、そこにはいかなる事実経過の説明も不要なのであろう。あるいは松虫の音に心を奪われた市人の一夜の夢だったのかもしれない。
ところは大阪市の阿倍野、今では大阪きっての繁華街であり、往時の面影は見る影もない。一人の市人が屋形を出して酒を売っていた。
この酒売りのシーンを描く冒頭の謡にはなかなかの趣がある。次は、次第からサシまでのその詞章である。
(次第)
シテ・立衆もとの秋をも松虫の。もとの秋をも松虫の。音 にもや友をしのぶらん。
(サシコエ)
シテ秋の風ふけゆくままに長月の。有明寒き朝風に。
シテ・立衆袖ふれ続く市人の。伴ないいずる道のべの。草葉の露も深緑。
立ち連れ行くやいろいろの。簔代衣.日も出でて。阿部の市路に出ずるなり。
(下歌)
遠里ながら程近き。昆陽(こや)住の江の。浦伝い。
(上歌)
潮風も吹くや岸野の.秋の草
立衆吹くや岸野の秋の草。
シテ立衆松もひびきて沖つ波。聞こえて声ごえ友誘う。この市人のかずかずに。
われも行き人も行く。阿部野の原はおもしろや。阿部野の原は.おもしろや。
(サシコエ)
ワキ伝え聞く白楽天が作りし酒功賛の琴詩酒の友。今に知られて市屋形に。
樽をすえ杯を並べて。寄り来る人を.待ちいたり。
いかに人びと酒召され候え。
(1)昔の秋がふたたび訪れないかと待つかのように松虫が鳴いているよ。その音は亡き友を偲んでいるのだろうか。
(2)蓑の代りの雨衣。市人たちが色々な雨衣を着て、陽が昇った阿倍野の市路にやって来ていることだ。
(3)遠里
小野からは程も近く、この住ノ江の浦伝いに(昆陽は伊丹市にある地名だが、これやに掛けた)阿倍野の原がある。
(4)白楽天が讃えたと伝えられてきた酒をこの市場の屋形で、酒樽を置き杯を並べて、客人を待っているのだ。
次は、友人が松虫の音を慕って原に分け入ったまま不可思議の死を遂げた一件を、シテが語る場面である。
松虫の音は「友を忍びて待つ」者の心の反響と受けとめられているのであろう。
シテ昔この所に住みし者。二人伴ない或る夕暮れにこの松原を通りしに。
おりふし松虫の声いとすさまじく聞こえしかば。一人の者かの虫の音を慕い尋ね行きしに。
今一人の友やや久しく待てども帰らざりしほどに。心もとなく思い尋ね行き見れば。かの者草露に臥して空しくなる。
死なば一所とこそ思いしに。こはそも何といいたる事ぞとて。泣き悲めども.かひぞなき。
地そのまま土中に埋れ木の.人知れぬとこそ思いしに。
朽ちもせで松虫の。音に友を忍ぶ名の.世に漏れけるぞ悲しき。
今その友を忍びて.松虫の。
友を忍びて松虫の。音に誘われて市人の。
身を変えて亡き跡の亡霊ここに来たりたり。
恥ずかしやこれまでなり。
立ちすがりたる市人の。人影に紛れて。
阿部野のかたに.帰りけり。阿部野のかたに.かえりけり。
(1)すがるには終わり際になるという意味がある。市が終り、店じまいをして帰る市人。
中入前のこの箇所で他の男たち(立衆)は幕に入るが、シテは主人に呼び止められてなおしばし留まってなお言葉をかわすという小段がつけ加わる
(「敦盛」ではツレの草刈り男たちは初同の謡で幕に入りシテひとり残る。また、「鞍馬天狗」ではワキと子方たちが花見の場に先客の山伏が居るのを見て幕に入り、牛若丸一人残るという演出がある)。
シテおりふし秋の暮。
松虫も鳴くものを われをや待つ声ならん。
地そも心なき虫の音の。われを待つ声ぞとは まことしかならぬ言葉かな。
シテ虫の音も。虫の音も.
忍ぶ友をば待てばこそ。言の葉にもかからるめ。
地げにげに思い出だしたり。古き歌にも秋の野に
シテ人松虫の声すなり。
地われかと行きて。いざ弔むらわんと。おぼしめすか人びと。
有難やこれぞ真の友を。忍ぶぞよ松虫の音に。
伴ないて帰りけり.虫の音に連れて.帰りけり。
(1)私を呼びとめたのは私を待つ虫の音かしら。
(2)虫の音も亡き友を偲んでなくから、歌にも詠まれるのだ。
(3)秋の野に人まつ虫の声すなり 我かと行きていざとぶらはむ(古今和歌集 読人知らず)
本曲はこの歌を機縁として作られたものである。この歌には女のもとに行くという色好み
が隠されているが、謡曲作者は松虫の声の居場所を死所に置き換えたのである。
そして市屋形の主人の弔いに呼び戻された幽霊はなお友との酒宴を讃えて謡い舞い、暁の鐘の響くころ、「ぼうぼうたる朝の原」に消え、虫の音ばかりが残ったのであった。
「千種にすだく虫の音」は、さまざまな草の間に群れ集まって鳴く虫の音の意味であり、松虫だけでなく群れいる虫が錦の彩をなして鳴き誇っているさまが謡われる。
虫の合奏が機織りになぞらえられ、その様が美しい言葉で奏でられる。愛すべき詞章である。
シテ面白や。千草にすだく。虫の音の。
地機織るおとは。
シテきりはたりちょう。
地きりはたりちょう。
つずりさせちょうきりぎりすひぐらし。
いろいろの色音の中に。別きてわが忍ぶ。
松虫の声りんりんりんりんとして夜の声。めいめいたり。
すはや難波の鐘も明けがたの。あさまにもなりぬべき.
さらばよ友人名残の袖を。
招く尾花のほのかに見えし。跡絶えて。
草ぼうぼうたる朝の原の。草ぼうぼうたる朝の原。
虫の音ばかりや。残るらん虫の音ばかりや。残るらん。
(1)きり・はたり・ちょうは機織の擬音。併せて機織のような虫の鳴き声。
(2)つずりさせは衣の綻びを縫おうよの意、併せてきりぎりす(こおろぎ)の擬音。同種の謡が「錦木」の次の詞章に見られる。
ツレひそかに音する物とては。
シテ機物の音。
ツレ秋の虫の音。
シテ聞けば夜声も。
ツレきり。
シテはたり。
ツレちょう。
シテちょう。
地きりはたりちょうちょう。きりはたりちょうちょう。
機織松虫きりぎりす。
つづりさせよとなく虫の。
衣のためかな侘びそ.おのが住む野の.
千種の糸の細布織りて.とらせん。
(3)めいめいたりは冥々たり。漆黒の暗闇(冥々)のなかに松虫の声がりんりんと響いているよ。
「夜の声」は鶴の夜声を意味するという。
松虫は秋の物悲しさを象徴するものとして多くの歌の題材となってきた。
今日人々は鈴虫(本稿での松虫)の音に澄みきった清楚な美しさを感じるであろうが、古来多くの歌人は哀愁、孤独、侘しさを感じ取ってきた。
とくに待つの連想から、一人わびしく待つ者の耳元に寄り添う虫の音として、多くの歌人によって謳われてきたのである。『古今和歌集』には数首の松虫の歌が収められている。
君しのぶ草にやつるるふるさとは 松虫の音ぞ悲しかりける (読人知らず)
秋の野に道もまどひぬ松虫の 声する方に宿やからまし (読人知らず)
秋風のややふきしけば野をさむみ わびしき声に松虫ぞなく (紀貫之)
なお、松虫の歌を四首。いずれの歌にもしみじみとした悲哀の情が流れている。
秋の野の尾花が袖に招かせていかなる人を松虫の声(山家集 西行)
跡もなき庭の浅茅にむすぼほれ露の底なる松虫の声 (新古今集 式子内親王)
寝覚めする袖さえ寒く秋の夜の 嵐吹くなり松虫の声 (新古今集 大江嘉言)
乱れおつる萩のまがきの下露に 涙色あるまつむしのこゑ (拾遺愚草 定家)
西行は松虫と特定していないが、次の歌は印象的である。
秋の夜に声もやすまずなく虫を 露まどろまできゝ明かす哉
能「松虫」の作者もこれらの歌人たちの感性と同じものを共有している。
松虫の音には人を呼び寄せる媚態を感じさせるものがある(サイレーンの歌声を思い起こさせる)とともに、寂寥感の底に引き込むような超俗的な遠隔性が感じられるというのである。
「松虫の声りんりんりんりんとして夜の声。冥ゝたり。」このような、虚空に響く松虫の音と、謎の死を遂げた友人への追想とが不可思議な符号によって重ね合わされているのを看て取ることができるであろう。
松虫が陰であるなら、鈴虫は陽である。平安朝から室町末期の時代にかけて鈴虫の音はチンチロリンである。
愛らしく、人に寄り添うようで、親近感がある。
古来、りんりんと鳴くのは松虫鈴虫のいずれか、という論争が続けられてきたが、チンチロリンと鳴くのは鈴虫であるということは、『源氏物語』によるかぎり動かないものと思われる。
『源氏物語』には「鈴虫」の巻がある。この巻で、源氏が出家した女三の宮の許を訪ねる場面が描かれるが、そのなかで鈴虫と松虫との対比が語られる。
源氏五十歳の夏、八月十五夜に、出家した女三の宮の持仏開眼供養か営まれた。
その年の秋、源氏は女三の宮の御殿の庭を野の風情に造らせ、秋の虫を放たせた。
十五夜の夕暮に女三の宮の許に赴いた源氏は、「虫の音、いとしげう、乱るる夕かな」と嘆賞していると、鈴虫が華やかに鳴きだした。
「げにこゑごゑ聞えたる中に、鈴虫のふり出たるほど、はなやかにをかし」と源氏は言う。
そして松虫について次のように言う。
「秋のむしの声、いづれとなき中に、松虫なむすぐれたる」とて、中宮(秋好中宮)の、はるけき野辺をわけて、いとわざと尋ねとりつゝ、はなたせ給へる、しるく鳴きつたふるこそ、すくなかなれ。名にはたがひて、命の程、はかなき虫にぞあるべき。
心にまかせて、人きかぬ、奥山・はるけき野の松原に、声、をしまぬも、いと、へだて心ある虫になむありける。
鈴虫は心やすく、今めいたるこそらうたけれ。
*「秋の虫の音ななかで、松虫が一番すばらしい」と、中宮はおっしゃって、はるか遠くの原にまでわざわざ採りにやらせて、庭に放たれましたが、今でははっきりとした音を伝えてくれる松虫は少なくなりました。
松という名前があるのに、その命ははかない虫ですね。
思う存分に、人のいない奥山やはるかな松原で、音を高くあげて鳴くということも、松虫は人から離れたところが好きな虫なのですね(松虫は人里離れた里でしかあまり鳴かないといわれた)。
それに対して鈴虫は気軽で、華やかに鳴く所がかわいいですね。
鈴虫に言寄せて女三の宮の気を引こうという源氏の策略であろう。
夕べの風情のなかで、女三の宮と源氏との間で鈴虫をめぐる歌が交わされる。
女三の宮 おほかたの秋をば憂しと知りにしを ふり捨てがたきすゞ虫の声光源氏 心もて草のやどりをいとへども なほすゞ虫の声をふりせぬ
(1) あなたは自分の意志で世を捨てられましたが、それでも若々しくてお美しい。
この巻では鈴虫が中心に語られるが、鈴虫が「心やすく、今めいたる」虫と評せられるのに対して、秋好中宮の口を借りて、松虫は秋の虫のなかでも「すぐれたる」と評され、「命の程、はかなき虫」で人里離れた「奥山・はるけき野の松原」にしか鳴かないので、「へだて心ある虫」と紹介される。
鈴虫が身近で華やかな虫とされるのに対し、松虫は奥ゆかしくはかない虫として、一目置かれた虫と見られていたことが分かる。
(松虫鈴虫転換説については、武山隆昭「『源氏物語』の「すゞむし」考――鈴虫・松虫転換説再評価」(椙山国文学24、2000年)が参考になる。)
ちなみに、仙台市近郊にある拙宅は林や畑の残る地にあるが、近年秋になっても虫の音がほとんど聴かれなくなった。
少年時代は大阪の郊外の地で育ったが、近くの堤防に上ると空間を満たして天から降ってくる虫の音に驚き、耳をそばだてたものであった。
虫の鳴かない秋の夜を経験するなど空恐ろしいことである。
友人に聞くと、私のところではまだ鳴いていますよ、という返事を聞いて少し胸をなでおろした昨今である。
2020年10月17日
祝言の歌 ――能の詞花を訪ねて23
能はなぜ脇能から始まるのかを考えてみたい。脇能の前には「翁」がある。「翁」は能の始まりであるとともに、その母型である。芸能であるとともに、神事である。
「翁」は人に向かって舞うのではなく、天の神・地の神に向かって舞うのである。先ず白式尉をかけた大夫が荘重な舞によって天下泰平国土安寧の祈りを捧げ、次いで黒色尉をつけた三番叟が大地を踏み鎮めつつ勇壮な舞を舞う。「翁」が儀礼的な構成をもつ神事能であるがゆえに、すべての能に先立つ「予祝」の意味を有することは容易に分かる。神への寿ぎが祝言であり、これがすべてに先立ち、ここから万事が始まるという神話時代からの思想が序破急の考え方を生み出し、さらには能の番立てをも導いたのであろう。
脇能は祝言を本旨とする。一日の能を寿ぎ、舞台を寿ぐのである。一日の能の終りにも祝言の能が上演される(祝言能)。今日ではこちらは簡略化されて「高砂」などの一節を謡う「付祝言」が通例となっている。してみれば、能は祝言で始まり、祝言で終るというわけだ。祝言に対応するものが影向である。影向とは、神がこの世に仮の姿をとって現われることであり、この世界への神の来臨である。神がそのままの姿で現れるのではなく、何らかの自然の事物に自らの影を映し出す(影向する)という形であらわれるのである。能舞台の鏡板に描かれる老松は春日大社の「影向の松」を型どったものであるから、能は舞台にまで神を迎え入れているわけだ。神が影向する自然の諸態は松に限らない。梅や桜や滝などもまた神が宿るものとして謡われ、春霞までも女神の影向とされることがある。これらは自然宗教の名残であろうが、むしろ日本的感性が自然の内に崇高神聖なものを感じとったとき、そこに神の影向を思い描いたのだと理解したい。
世阿弥は、祝言はものごとの初めだという。初めはものごとの基本を与える。初めは序である。「序者、初めなれば、本風の姿也」(風姿花伝)。本風は「直なる姿」と説かれるが、これらは「本来」、「生来」の意味であり、自然の聖性ないし善性を表す言葉である。この「直」なるものが人の世に下ると、「曲」になる。人の世は曲の世界である。この直から曲への転化が人事の始まりであり、そして芸能の始まりである。世阿弥はこの曲の世界に序破急の「破」を重ねたのであろう。人は曲の世界にあって、本来のもの、自然の根源に目を向ける。あるいは、人は地にあって天を仰ぐ。これが開聞・開眼であって、耳を開き眼を開いてものごとの本風を覗おうとするのである。そして眼を開いて天を仰ぐものに神は影向するのである。
翁と脇能とは、このような経緯から能の開眼としてその始まりに据えられたのであろう。そして、祝言の能はこの開眼を喜び讃えるために生まれたのであろう。次に、このことを脇能の詞章を見ることによって確かめてみよう。
「弓八幡」は、一人の老翁(実は高良の神)が男山にある岩清水八幡宮に桑の弓を捧げるという話を一曲に仕立てたものであり、その内容は簡単明瞭である。後宇多院の宣旨を受けた臣下が八幡宮に参詣したところ、一人の老翁が弓を収めた錦の袋を携えて現れた。不思議に思った臣下が問えば、神慮により桑の弓を君に捧げるために来たのだと答えた。
シテ 今日当社御参詣に。桑弓を捧げ申すこと。これこそ則ち神慮なれ。
ツレ その上聞けば千早ふる。
シテ・ツレ 神の御代には桑の弓。蓬の矢にて世を治めしは。すぐなる御代のためしなり。よくよく奏し。給えとよ。
桑の弓蓬の矢を捧げるのは「泰平の御代のしるし」だという。桑の弓では射られず、蓬の矢では飛ばず刺さらない。不戦のシンボルなのである。祝言が天下泰平国土安穏を寿ぐことをそのまま舞台に直訳した観がある。ちなみに「桑の弓」は中国の故事「桑弧蓬矢」に由来する。昔、男児が生まれたとき、桑の弓に蓬の茎ではいだ矢をつがえて四方に射て将来の立身出世を祝ったのである。さて、この曲には神の影向が謡われている箇所がある。
月の桂の男山。さやけき影は所から。
畜類鳥類鳩吹く松の風までも。皆神体と現れ
げにたのもしき神ごころ。
示現大菩薩八幡の 神徳ぞ豊かなりける
神徳ぞ豊かなりける。
*鳩吹くは、猟師が狩のとき獲物に気づかれないように手を組合わせて吹く笛のこと。転じてホウホウと吹く西風を指し、秋の季語
一切の衆生ばかりでなく松風もまた神体の現れであり、示現
大菩薩八幡の威徳を表していると謡われる。八幡大菩薩は中世以来軍神として讃えられる神であるが、世阿弥はこのことを逆手に取って、軍神でさえも泰平を讃える御代であると謡ったのであろうか。
さて、この「弓八幡」の「直」に比べれば、「高砂」はかなり手の混んだ「曲」が施されている。松を讃え、和歌を讃え、そしてそれらの共通の源であるとされる高砂住吉の神を讃えるのである。前シテ(尉)・ツレ(姥)は、下掛では住吉・高砂の神の化身、上掛では松の精と異なるのは興味深いが、松を神の影向と考えれば、両者の差異は解消するであろう。金春流はシテもツレも杉箒を持って登場するが、松の葉を掻くのは神の身許を清めるためである。しかしそれは同時に、松の葉が言の葉と重ね合わされ、松の葉を掻くことは言の葉を集めることと解されることによって、歌を読むことを暗示している。松と歌とが見事に融合する。
松とはつきぬ言の葉の。
さかえは古今あい同じと。
み代を崇むる譬えなり。
「つきぬ言の葉」は万葉集を、「古今あい同じ」は万葉集から古今集までみ代が連綿として栄えることを謡うのである。こうして松の影向は歌の影向となり、松を讃える曲は歌を讃える曲となる。祝言は松を謡い和歌を謡う。両者が混然としているところに、作者は影向の不思議と神妙を表そうとしたのであろう。次の詞章は万物が歌を唱っていると讃える箇所であるが、「和歌のすがた」を「神のすがた」と置き換えることができる。
有情非情のその声。みな歌にもるる事なし。
草木土砂。風声水音まで萬物をこむる心あり。
はるの林の。東風に動き
秋の虫の。北露になくもみな。
和歌のすがたならずや。
中にもこの松は。萬木にすぐれて。十八公のよそおい。
千秋のみどりをなして。古今の色をみず。
*十八公は、三国時代の呉の政治家であり、礼節あった人物である丁固が尚書であったときに、松の木が腹の上に生える夢を見て、「松の字がは十、八、公からなる。十八年後、私は三公になっているであろう」と悟ったという故事によっており、松の別名であるが、立派な太子であることをも表す。また、和漢朗詠集に「十八公栄霜後露一千年色雪中深」という詩句がある。「古今の色をみず」は「見す」が正しく、昔と変わらない色を表しているの意。
影向の歌は、後場では住吉の神が神体で現れ、舞楽を舞って、御代の千秋万歳を寿ぐという顛末にいたる。影向が仮の姿から本体の姿に移るという展開は複式能の基本に適うが、本体が神であるところに脇能としての面目がある。次のキリの詞章にも、神の影向と住ノ江の情景とが混然と一体になった陶酔的な美しさがある。
有難の影向や。有難の影向や。
月すみよしの神あそびみかげを拝むあらたさよ。
げにさまざまの舞びめの。声もすむなり住の江の。
松かげもうつるなる青海波とはこれやらん。
「老松」は、菅原道真左遷にまつわる飛梅・追松の伝説を題材とした曲であり、前二者にたいして物語的な性格を有している。道真が大宰府に左遷された折、彼が「東風吹かば匂いおこせよ梅の花 主なしとて春な忘れそ」と歌を詠んだことに基づく伝承であるが、都の館にあった梅の花「紅梅殿」が歌が詠まれたその夜の内に「この国に飛び来たり。神木とな」ったという。また、傍らの老松(後シテ)は「天神の愛で給う木にて、共に此所の末社として祭られあり」と謡われるが、間語で梅の後を追いかけて筑紫まで来たゆえに追松と名づけられたと紹介される。次は松梅二木を讃えたクセの詞章である。
諸木の中に松梅は。ことに天神の。ご自愛にて
紅梅殿も老松もみな末社と現じたまえり。
さればこの二つの木は。
わが朝よりもなお。漢家に徳を現わし。
唐の帝のおん時は。国に文学
さかんなれば。
花の色を増し。匂い常より勝りたり。
文学すたれば匂いもなく。その色も深からず。
さてこそ文を好む。木なりけりとて梅をば。
好文木とは付けられたれ。
後場では、老松の神霊が現れ、舞(序ノ舞)を舞い、神託を告げるが、「紅梅天女」の小書が付くと、天冠に梅の花を挿頭した天女が出て舞を舞い、舞台が華やかになる。
千代に八千代に。さざれ石の。
巌となりて。苔のむすまで。
苔のむすまで松竹。つるかめの。
齢を授くるこの君の。行く末守れとわが神託の。
告を知らする松風も梅も。
久しき春こそめでたけれ。
*松竹鶴亀は長寿のシンボルとされる。
神の影向の姿は他にもさまざまに謡われる。その中から三つの影向を訪ねてみよう。「嵐山」では、咲き誇る嵐山の桜の木々の間を子守勝手の神が戯れ舞い遊ぶ。嵐山の桜は吉野より植え移されたという。そのため吉野水分神社の子守神・勝手神が訪れるというのである。そればかりではなく蔵王権現まで現れ、栄ゆく春を寿いだと謡われる。
三吉野の。三吉野の。
千本の花の種植えて。嵐山あらたなる。
神遊びぞ目出たき。
いろいろの。いろいろの。
花こそまじれ。白雪の。
子守勝手の。恵みなれや松の色。
青根が峰ここに。小倉山も見えたり。
向いは嵯峨の原。下は大堰川の。
岩根に波かかる亀山も見えたり。
万代と。万代と。
囃せ囃せ神遊び。
「養老」は養老の滝を讃えた曲。松かげに落ちる滝の水音を「拍子を揃えて。音楽を奏し。」と聴き、「滝つ心」を謡い上げた。滝の水音を神の影向と謡うのは「翁」と重なるが、まことに清冽である。
みねの嵐や。谷の水おと。とうとうど。
拍子を揃えて。音楽を奏し。
滝つ心を。澄ましつつ。
諸天来現の。影向たり。(神舞)
松かげに。千代をうけたる。みどりかな。
さもいさぎよき。山の井の水。
山の井の水。山の井の。
みずとうとうどして。
波いういうたり。
ユニークな神の影向に「氷室」の神がある。氷も神となって現われることがあるのだ。後シテ(氷室の神)は一畳台の上に置かれた山(引廻しを掛け、氷室を表す)の中にて謡い、氷を割って表れる風情で、作り物より出て舞働を舞う。手には氷(金春流では、いびつの六角形の木板)を持つ。
谷風水辺。冴えこおりて。
月もかかやく。氷のおもて。
万境をうつす。鏡のごとく。
清嵐梢を。ふきはらって。
かげも木深き。谷の戸に。
雪はしぶき。あられは横ぎりて。
岩もる水も。さざれ石の。
深井の氷に。とじつけらるるを。
引きはなし引きはなし。
うかびいでたる氷室の神風。
あら寒や。ひややかや。
祝言の曲は、それぞれに雄渾、爽快であり、おおらかさと気高さを湛え、滞ることがない。美しさと気品が備わっていなければならないのである。ただし、その気品は直ぐなる自然の営みの清冽さから生まれるものであり、技工や作為が生みだすものではない。年のはじめを迎えればおのずと気が改まる思いがするであろうが、人はその思いを「めでたい」と言い表す。正月は序であり、「すぐ」なのである。祝言の心が私たちの魂にも住みついていることがよく分かるであろう。
2020年8月19日
修羅と煉獄 ――能の詞花を訪ねて22
能に修羅物と呼ばれる一群のグループがある。多くは西海に沈んでいった平家の公達の悲哀の物語を描いた能であり、「負修羅」ともいう。「敦盛」「生田(生田敦盛)」「清経」「忠度」「経政」「知章」「通盛」など。また「実盛」や「景清」は平家の武将を描いた能であるが、負修羅の真骨頂ともいうべき作品である。平家負修羅以外にも「頼政」(源氏の武将である)「八島(屋島)」(源義経を描く)「田村」(坂上田村丸の東方征伐)などがあり、いずれも戦を描いた作品(「八島」「田村」を勝修羅ということがある)である。修羅とは戦いや争いの場を指すとともに、そのために身に受ける苦患を表す言葉でもある。
もともと修羅は仏教の六道思想のなかで語られる言葉である。それは輪廻転生するものが通過する六つの世界(道)――天道、人間道、修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道――の中間に位置し、現世(人間道)における悪業の報いとして死後に堕とされる冥界のなかで「最良」の境界に該当する。地下の世界は修羅―畜生―餓鬼―地獄と四層になっており、悪業の度合いに応じて堕ちる階梯が異なるというわけだ。六道の下部の三つ(畜生道、餓鬼道、地獄道)は三悪道といわれ、悪の結果の世界であるが、修羅道は悪道に決するとは限らず、善悪未決の世界である。闘う心から離れず、争闘の精神的境涯の者が住む世界である。戦いは悪であるが、しかし人は正義の為に戦うと思っているから必ずしも悪意があるわけでもないのである(修羅道の神、阿修羅は正義の神でもある)。
修羅道(阿修羅道ともいう)は冥土の中間世界であり、およそ現世で争い戦うものの行き先である(とすれば、およそ争わない人はいないから人はせいぜい良くて修羅道に堕ちるわけである)。尤も、六道は輪廻転生という時制の回転のうちにあるから、たとえ地獄に堕ちたとしても上昇(救済)の可能性がある。芥川龍之介が語るように、地獄でさえ「蜘蛛の糸」が下りてくる可能性があり、修羅道に堕ちた者も人間界や天の世界に再生する可能性は大いにあるのである。
修羅道は阿修羅神の統べる世界である。阿修羅は初めは善神であったが、帝釈天と抗争を繰り返すことによって悪神になったという。「阿修羅の如く」とは、帝釈天と激しく闘争する阿修羅の勢いを言い表している。「阿修羅道は、「瞋・慢・痴」すなわち〈いかり〉〈おごり〉〈おろかさ〉の三つの心を原因として生ずる世界である」といわれる(木村宣彰、www.otani.ac.jp/yomu_page)。仏教は人間の煩悩の根源を、貪欲、瞋恚、愚痴の三つと見、これを三毒と呼ぶが、修羅道の教えは瞋恚に煩悩の核心を見るのである。瞋恚は憤怒の感情であり、怒り、憎しみ、怨みとなって表れる。瞋は、自分の気に入らないものにたいして目を吊り上げて怒ることを意味する字なのである。瞋恚の害は猛火よりもはなはだしいともいわれる。
修羅は畜生にまで堕ちることを免れ、なお「人間」の体裁を失わずにすんだ、したがって「人間以下の人間」と判定された者の世界である。人の心はあるのであろうが、悪心に駆られ、そのために互いに苛め合い自ら苦患する世界である。私には、このような修羅の世界はこの現世そのものの姿を言い当てているように思われる。人の行う行為はおよそ「修羅の行為」であることを否めないであろう。この世は一定修羅ぞかしである。赤色の世界に住むものは世界を赤いと思わないように、修羅の世界に住むものはみずから自覚しないまま世界を憤怒に染め上げている。われわれは争いの矛をことさら振り回すわけではなくとも、周りの差異のことごとくに「刃向か」い、けっして「善」に向かわない行為に「身を粉に」している。人を貶めていると思わずにエゴの角を振り回している。修羅道の思想は人間の本性を見定めているのである。それゆえ、次の源信の言葉は修羅を説得的に言い当てている。
雷鳴がなりわたると、これを天の鼓だと思って怖れ、あわてふためいて、心はおののき、かなしむ。またいつもさまざまな天によって侵害され、あるいは身体をそこない、あるいは若くしてその生命をおとす。また毎日、朝も昼も夜も苦しみが自然に迫ってきて害ない、さまざまな憂苦は一々説明することができない。(源信『往生要集』石田瑞麿訳、平凡社東洋文庫)
修羅道の教えに比肩されるものに、カトリックにおける「煉獄」の思想がある。煉獄は、天国には行けなかったが地獄にも堕ちなかった人間の行く中間的な所であり、苦罰によって罪が浄められるとされる世界である。キリスト教では地獄は永遠の責め苦の場である(したがって救済がない。おそらく「終末」のその日まで。)が、煉獄は救済のための「道場」のような場である。煉獄は浄罪界とも称せられ、そこでの苦患は「浄めの火」と呼ばれる。人が行う死者のための祈りは、煉獄に苦しむ霊魂のための祈りなのである(地獄に堕ちたものは救われないのだから、祈りようがない)。死者が煉獄に堕ちたのは神から離反したからであるが、祈りは死者が神の方に「向き直る」ように祈るのである。山田晶は煉獄の苦しみについて次のように述べている。
(煉獄の)時間とは、われわれのこの世の時間とは違う時間、おそらく次元の違った時間でしょうけれども、とにかくそれは永遠ではない。いつまでも果てしなくつづくのではなくて、やはり一つの終末に向ってだんだんと浄化されてゆく。その苦しみもまた有限の苦しみである。ですからその苦しみはいつか尽きることがある。その時には、この世の中で完全に果し切れなかった罪の償いを完全に果して、浄化されて天国にゆく。それゆえ煉獄にいる魂は非常に苦しんでいるけれども、その苦しみは絶望の苦しみではなくて、希望を内に含んだ苦しみである。浄化の苦しみであるといわなければなりません。(山田晶『アウグスティヌス講話』新地書房、1986年)
ダンテは、煉獄を地獄の反対側の地底から天国にまで聳える山(煉獄山)に喩えた(あたかも須弥山のようであるが、須弥山は人間界の上界に聳える聖なる山である)。彼は、煉獄に堕とされた者がこの山を登ることによって浄化され(浄化の登高)、天国へと登りつめる様を描いた。煉獄の亡霊たちは、「神に仕えるでもなく、そむくでもなく、ただ自分たちのためにだけ存在した邪悪な天使の群とまじりあっている。天はこうした奴が来ると天国が汚れるから追い払うが、深い地獄の方でも奴らを受け入れてはくれぬ」といった手合である(われわれ凡人を語っているようだ)。この亡霊たちが追い立てられ責められしながら、天に届く高峰を登らなければならないのである。登山道は高慢、嫉妬、憤怒、怠惰、貪欲、暴食、愛欲という七つの「冠道」(煉獄山の登山道は螺旋状に七周して登る)から成る。亡霊はこの「冠道」を経めぐり、高く高く登らなければならないのである。しかし、その厳しさは登高の最初にあるという。
この山の格好は、下の登り口に近ければ近いほど登りづらく、上がれば上がるほど苦が減ずる。だからしまいにはまことに快適で登りがいとも軽妙になり、いわば舟で流れを下るようになる、そうなればこの径の終わりに着いたことになる、そこで疲れを休めるよう心づもりをするがいい。私がいまいったことは事実だ、これ以上はもう答えぬ。(『神曲 煉獄篇』、平川祐弘訳)
さて、修羅道に堕ちた平家の公達を謡った曲に「清経」がある。西海の海に身を投げた平清経が亡霊となって妻の前に現れるという一幕物の能であるが、平家の末路を描いてこれほど悲しい曲はないであろう。平家一門は都を落ちて大宰府に御所を構えようとしたが、源氏方に寝返った緒方惟栄に破れ、豊前国柳に逃れた。平家は宇佐八幡に安全祈願の参詣をし、神馬、金銀の捧げものをし、一生懸命にお祈りをしたが、神殿の御戸張から神の声が響いたという。
世の中の憂さには神もなきものを 何祈るらんこころづくしに (神歌)
憂さは宇佐に、づくしは筑紫に掛けた言葉である。つれなくも平家を突き放した歌である。平家は、神仏にも見捨てられたかと気力を失い、力を落として足弱車のようにすごすごと立ち去ったと云う。
さりともと思うこころも虫の音も 弱りはてぬる秋の暮れかな
(『千載集』藤原俊成の歌を引く)
清経は平家の前途に絶望して、波に月が映るある夜、舟の舳板に立ったのであった。クセでは敗北に怯える清経のさまが謡われるが、追いつめられた人間の諦念の思いが高い透明度を持って描かれている。
げにや世の中の。うつる夢こそまことなれ。
保元の春の花 寿永の秋の紅葉とて。
ちりぢりになり沈む。一葉の舟なれや。
柳が浦の秋風の。追手顔なるあとの波
白鷺のむれいる松見れば。源氏の旗をなびかす。
多勢かときもをけす。
そして詞章は清経が入水する場面へと進む。
月にうそむく気色にて。舟の舳板に立ちあがり。
腰より横笛抜きいだし。
音も澄みやかに吹きならし、今様を謡い朗詠し。
こし方行く末をかがみて。ついにはいつかあだ波の。
返らぬはいにしえ。止まらぬは心づくしよ。
この世とても旅ぞかし。あら思い残さずやと。
よそ目にはひたふる。狂乱と人は見るらん。
よし人は何とも、みるめをかりの夜の空。
西に傾く月を見れば。いざやわれも連れんと。
南無阿弥陀仏弥陀仏。
迎えさせたまえと。ただ一声を最後にて。
舟よりかっぱと落ち潮の。
底の水屑と沈みゆく 憂き身のはてぞ悲しき。
清経入水の話は『平家物語』にも触れられている。
小松殿(平清盛の嫡男)三男左の中将清経は、もとより何事もおもひいれたる人なれば、「宮こをば源氏がためにせめおとされ、鎮西をば維義(惟栄の諱)がために追出さる。網にかかれる魚のごとし。いづくへゆかばのがるべきかは。ながらへはつべき身にもあらず」とて、月の夜心をすまし、舟の屋形に立出でて、やうでうねとり朗詠してあそばれけるが、閑かに経よみ念仏して、海にぞしづみ給ひける。男女なきかなしめども甲斐ぞなき。 (『平家物語』巻第八)
また、『源平盛衰記』巻三十二は清経の最期を次のように語り、悲哀この上ない。
竜頭鷁首ノ船ヲ海上ニ浮テ出サセ給へハ、浪路ノ皇居静ナラス、都ヲ落シ程コソナケレ共、是モ遺ハ惜カリケリ。棹ノシツクニ袖濡テハ、古郷軒ノ忍ヲ思出テ、月ヲ浸潮ノ深愁ニ沈、霜ヲオホへル芦ノ脆命ヲ悲ム。洲崎ニ騒ク千鳥ノ声暁ノ恨ヲ添、傍居ニカヽル楫ノ音夜半ニ心ヲ傷シム。白鷺ノ遠樹ニ群居ヲ見テハ、東夷ノ 旌ヲ靡スカト肝ヲ消シ、夜雁ノ遼海ニ啼ヲ聞テハ、兵ノ船ヲ漕カト魂ヲ失フ。青嵐膚ヲ破テ、翠黛紅顔ノ粧ヤウヤウ衰ヘ、蒼波眼ヲ穿テ外土望郷ノ涙難押。
いずれの文章も敗北の修羅を描いて見事である。西海に漂う平家の末路こそ修羅そのものであった。清経は武人のなかでも管弦を嗜み、心優しい武将だったのであろうが、死の前も後もこのような修羅の苦患から免れることができなかったのであろう。修羅とは責苦に身が拉げるさまを意味するだけでなく、悲哀と絶望という心の裂傷をも受けることでもあることを、この作品は語っているのである。
さて修羅道に落ちこちの。さて修羅道におちこちの。
立つ木は敵雨は矢先。月は清剣山は鉄城。
雲の旗手をついて。驕慢の剣をそろえて。
じゃけんのまなこの光。愛欲とんいちつうげん道場。*
無明も法性も。乱るるかたき。打つは波引くはうしお。
これまでなりやまことは最後の十念乱れぬみ法の舟に。頼みしままに疑いもなく。げにも心は清経が。げにも心は清経が。
仏果を得しこそ有難けれ。
*ここに描かれた修羅道の様子は地獄のそれと大差ないが、愛欲貪瞋(愛欲とんいち)は修羅道の罪過を意味しており、清経が修羅道に堕ちたことが分かる。なお、つうげん道場は不明(佐成謙太郎は痛患闘諍のことではないかという。『謡曲大観』第二巻「清経」)
キリの終わりで清経が修羅道から突如救われると謡われることは、唐突感を免れないであろう。そこには仏教的救済感が窺え、救済(成仏)ということがすべての罪に優先するという「日本的罪障免罪」の思想が読みとれるであろう(もっとも「善知鳥」のように救われないままに終わる曲もある)。そこに安堵があるとともに、責任倫理の薄弱も見られると思うのは私だけであろうか。
2020年6月21日
水のあはれ ――能の詞花を訪ねて21
能には水の情緒をたたえた曲がいくつもある。桜花が流れる水面や(「桜川」)、紅葉に埋め尽くされた川(「立田」)の風情は能の描く風景のなかでも特筆すべきものであろう。緑の蔭にとうとうと流れる山の井の水の清冽さも印象的である(「養老」)、等々。しかし、数ある水の風景のなかでも「松風」で謡われる桶の水に映る月の描写ほど余情を湛えた詩句は他にないだろう。
見れば月こそ桶にあれ。
これにも月の入りたるや。うれしやこれも月あり。
月はひとつ。影は。ふたつ。みつ汐の夜の車*に月をのせて。
うしとも思わぬ。汐路かなや。
*汐汲み車のこと
水には人の心を和らげ、鎮める霊気がやどり、そして心の奥に潜む想いを映し出す
不思議な力が宿っているのであろうか。西洋中世社会に普及し人口に膾炙した「サレルノ養生訓」は「朝には山を見、夕べには泉の水を見よ。」と説いたが、人生の要を的確に押さえた箴言である。水面は夕辺に見るのがふさわしい。なぜか。水がそれを見るものに追憶を誘うからであろう。水には生命の源としての固有の内実があるmatter。湧き出す水は留まることなく流れlive、そして水面を見るものにはその姿を映し出すreflectからである。水は一切の生命の根源であるが、同時に人の心の元素でもあるという思いがそこには込められている。
さてここでは能「檜垣(桧垣)」に表わされた水の抒情を辿ってみることにしよう。「檜垣」は三老女物の一であり、「関寺小町」に次ぐ秘曲と目されるが、「水の因果」を説き、「水のあはれ」を讃えた曲としてはあまり理解されていないかも知れない。この曲に流れる水の通奏低音は、流れ去るという生の無常への詠歎と流れ着いた老いの無慚の心境を代示している。ここには往く川の流れに人生を重ねるという仏教的諦観の手法が受け継がれている。「老い」という主題にはある特別の過酷さが秘められているが、それをただただ嘆く言葉ばかりでは詩境に外れる。老は有終であり、有終は美で包まれなければならないのだ。
「檜垣」は九州肥後国岩戸(熊本市の西方)の寺(今日の蓮台寺)を前半の舞台とし、白河(阿蘇を源とし熊本市を流れる川)を後半の舞台とする曲である。岩戸の観世音にしばらく逗留していた僧のもとに毎日閼伽の水を運ぶ老女があった。ある日僧がその名を問うと、老女は「年ふればわが黒髪も白河の水はぐむまで老いにけるかな」と詠んだ檜垣の女と明かし、消えた(中入)。僧が白河の辺りに赴き跡を弔っていると、檜垣の女の霊があらわれ、熱湯を汲み猛火に身を焼かれる苦しみを受けていたことを明かした(女は邪淫の罪により次獄に堕ちていた)。そして僧のとむらいによって猛火は去り、成仏できたことを感謝し、なお罪障の滅却を僧に求めるのであった。――むしろ典型的な夢幻能であり、大きな変哲のない地味な筋書きの能であるというべきであろう。
シテの登場から、水の縁を拾いながら老女の心の世界を紐解いてみよう。シテの老女は右に杖をつき、左に水桶を持ち登場、橋掛り一の松で次第を謡う。
かげ白河の水くめば。影白河の水汲めば。月もたもとやぬらすらん。
老女は、月の影が白く映っている白河の水を汲もうと謡い出す。彼女は白河の井の水を釣瓶で汲んでいたのである。汲む袖が濡れることを桶に映る月が袖を濡らすことだと謡った。老女は続けて謡う。
ながるる水の哀れ世の。そのことわりを汲みて知る。
ここは所も白河の。ここは所も白河の。
水さえ深きその罪を。浮かびやすると……
流れる水の泡のようにはかない人生を思うにつけても、その水を汲んでみれば、人の世のあはれのそのわけが身に伝わってくることだ、と老女は人生の無常を流水の流れに喩えて謡う。水のあはれとは、すべてははかなく過ぎ去るという無常とその果てにある老いと死(漆黒の海)の「ことわり」のことだったのである。
名をたずねる僧に、老女は『後撰集』に詠まれた自らの歌を引き、その縁を語った。
かの後撰集の歌に。
年ふればわが黒髪も白河の。水はぐむまで老いにけるかなと。
詠みしもわらわが歌なり。
……
その白河のいおりのあたりを。
藤原の興範通りし時。
水やあると乞わせ給いしほどに。
その水汲みて参らするとて。
水はくむとは。詠みしなり。
そも水はくむと申すは。そも水はくむと申すは。
ただ白河の水にはなし。
老いてかがめる姿をば。水はぐむと申すなり。
ここで語られた『後撰集』の雑三には、次のように当の歌が取り上げられている。
つくしのしらかはといふ所にすみ侍りけるに、大弐藤原おきのりの朝臣の、
まかりわたるついでに、水たべむとて、うちよりてこひ侍ければ、水をもて
いでてよみ侍ける人*
ひがきの嫗筑前国
年ふればわがくろかみもしら河の みづはぐむまで老にけるかな
*檜垣の女は筑紫の白河という所に住んでいた。大宰大弐・藤原興範(844年 - 917年)が通り
かかった折に水を所望したが、女は水を持ってきて次の歌を詠んだ。
また、『大和物語』第一二六段にもこの歌の本歌になる歌が掲載されている。筑紫に檜垣の御という伝説的な遊女が住んでいた(実在した遊女であり、彼女には『檜垣嫗集』という歌集がある)。藤原純友の乱(932年)の騒動の中で家を焼かれ、その後零落して惨めな生活を送っていたが、小野好古(小野道風の弟)が追補使となって筑紫に下った折、檜垣の御を探し求め、会おうとしたが彼女は恥じて姿を見せず、歌を贈ったという。
ぬばたまのわが黒髪はしらかはのみつはくむまでなりにけるかな
ちなみに、一二八段では歌人としての彼女を偲ばせる話が紹介されている。「すきものども」が集まって檜垣の御を試そうとして奇妙な上の句を与え、下の句を付けさせようとした。その上の句は、
わたつみのなかにぞ立てるさを鹿は
という難句であったが、女は
秋の山辺やそこに見ゆらむ*
と返したという。
*上の句は「海のなかに牡鹿が立っているよ」ほどの意味で、唐突な無理難題である。女はこれに対して「秋の山が水底に映っている」という下の句をつけて、水辺に立つ牡鹿の姿が水面に写っていると詠み返したのである。
また檜垣の女の伝承には、彼女は清原元輔(清少納言の父)と親交を結び、彼が肥後守の任期が終わって帰京するさい、「白川の底の水ひて塵立たむ 時にぞ君を思い忘れん」と詠んで彼を送ったという話があるという。
(ウィキペディア DA06567390 NDL: 00269642 VIAF: 67785387)
さて、檜垣の女の歌に表れる「水はぐむ」という言葉は本曲全体の要となる語である。「水はくむ」と「みつはぐむ」という別表記の語も用いられており、それぞれ微妙に意味の転換があるようである。「水はくむ」が白河の水を汲むを意味することは自明であるが、「そも水はくむと申すは。ただ白河の水にはなし。老いてかがめる姿をば。水はぐむと申すなり。」と謡われる。この語が「老いてかがめる姿」を表すというのである。『日本国語大辞典』によれば、「みずはぐむ」あるいは「みつはぐむ」の語は、きわめて年をとる、はなはだしく年老いるということを意味するが、それは足腰が三重に折れかがまり三輪を組んだような状態になることを形容したからだという。また、身がかがまって水汲みのような状態になったことを意味するともいう。年老いて関節ががたがたになることを意味するのであろう。
ところがこの語にはもう一つの意味が隠されており、むしろそれが本義だという。同辞典によれば、この語は「老人に瑞歯がはえる意か」という。瑞歯とは「一度抜け落ちてから、ふたたびはえた老人の歯」をいい、長寿をあらわすめでたいものとされたという。「ぐむ(くむ)」はめぐむ(芽ぐむ)を意味している。それゆえ、この語には瑞歯が生えるほどとびきり高齢だという意味がある。なお、『源氏物語』夕顔巻には「惟光が父の朝臣の乳母に侍りし者の、みづはぐみて、住み侍るなり。」という用例がある。
藤原興範に歌を送った一件を語った老女は藁屋に中入する。後半でシテ(檜垣の女)は紅大口長絹姿に前折烏帽子をかむり、水桶を手にして、引廻しのかかった藁屋の中で静かに老残の身を嘆く歌を謡いだす。僧に乞われて現れ出でた姿は、
涙ぐもりの顔ばせは。
それとも見えぬ衰えを。たれ白河のみつはぐむ。
老いの姿ぞはづかしき。
というものであった。老いの様子を見事に言い表した一句である。女は冥界で邪淫の罪により猛火の釣瓶を下げて熱湯を汲み身を焼くという責めを受けていたが、僧の念仏により猛火は去ったと感謝した。汲む水は「因果の水」であり、因果晴れて猛火の水は閼伽の水に転じたのである。
このかけ水を汲み乾さば。罪もや浅くなるべきと。
思いも深き小夜衣の。袂の露の玉だすき。
かげ白河の月の夜に。底澄む水を。いざ汲まん。
つるべの水に影おちて。袂を月やのぼるらん。
「袂を月やのぼるらん」の一句は前場の次第の結句「月もたもとやぬらすらん」に対応しており、作者はこのような二重の句によって水を汲む女の反復的な姿を重層的に描きあげている。繰り返し釣瓶の掛け縄を繰る女は水面に映る代わり果てた老衰の影に嘆きながら、次第に昔の回想のなかに滑り込み、興範とともにした日々を懐かしみ、「狭布の細布胸あわず」という白拍子の悲しい宿命を思い起こすのであった。
つるべのかけ縄くり返し憂きいにしえも。
紅花の春の朝紅葉の秋の夕暮れも
一日の夢とはやなりぬ。
紅顔の粧い舞女の誉れもいとせめて。
さも美しき紅顔の。
翡翠のかづら花しおれ。桂の眉も霜ふりて。
水にうつる面影老悴かげ沈んで。
緑に見えし黒髪は土水のもくず塵芥。
変りける。身の有様ぞ悲しき。
水面は老衰の面影と若き日の華やかな姿とを二重写しにするが、水面を見て回想の世界に沈んでいくのは檜垣の女だけではない。江口の君は船から見た水面に映る月影に「流れの女」の悲哀を見、紅花の春の朝が一日の夢になり果てたことを嘆いた(「江口」)。藤原実方は御手洗の水面に臨時の舞の誉れの姿を見て恍惚となったが、いつしか老衰の影にかき消されたのだった(「実方」)。これらに共通しているのは水面が「紅花の春の朝」と「紅葉の秋の夕べ」、人生の朝と夕暮を映し出すということである。思うに回想こそは人生の最後の「仕事」ではないだろうか。そして揺蕩う水面は月を映し、人の過去を映して、人を回想の世界に誘うのである。
舞い終えた老女は「水のあはれ」を受け入れたのであろう。「昔にかえれ」と謡う。
水むすぶ。
つるべの縄の。つるべの縄の。
くりかえし。
昔にかえれ白河の波。白河の波。
白河の。水のあわれを知る故に。
老残の身にとっては過去の紅花の日々へとくり返し誘う回想のみが生の証であろうが、その過去の華やかさが人を罪へとすべらせ、老残の苦しみを招いたのである。人は因果の報いに苦しむ。「水のあはれ」とはそのような因果を水面に映すことによって、人の心に「生の反復」を想起させることにあるのであろう。そして流れる水にはそのような因果をも流し去らせるという名伏し難い「生の流転」の働きがある、ということを作者は伝えようとしたのではないだろうか。
2020年4月23日
都鳥の歌 ――能の詞花を訪ねて20
「角田川(隅田川)」は能のなかでも屈指の人気曲である。かつては「関寺小町」「道成寺」と並んで秘曲に数えられたこともあった。
謡や語りの妙もさりながら、主題の訴える「物のあはれ」と結末の神韻とした悲哀がこの曲を比類ないものにしているのであろう。
他の狂女物が親子再会などの安堵の結末で終わるのに対し、この曲はたんなる死別ならぬ最愛の死者との再会という、悲痛のなかに一抹の歓喜を漂わせるというエンディングが印象的である。
この場面において子方を出すことをめぐっての、作者の観世元雅と父世阿弥との間でかわされたやりとりは興味深い。親子の間でありながら、幽玄性をより重視する世阿弥と場面構成を重く見る元雅との芸術観の差がよく現れているのである。件の箇所を『申楽談儀』は次のように伝える。
隅田川の能に、「内に子もなくて殊更面白かるべし。此能はあらはれたる子にてはなし。亡者也。ことさら其本意を便りにてすべし」と世子申されけるに、元雅はえすまじき由申さる。かやうのことは、して見てよきにつくべし。せずば善悪定がたし。
*『隅田川』の能について、「子(子役)を出さない方が面白いね。この能は、現存する子ではなく、失せてしまった亡者が物語の本意であることを旨として演じるべきだね」と世阿弥が云われたけれども、元雅は「子方を出さないことは納得できません」とお答えした。世阿弥はそこで、「このような問題は実際にやってみて面白い方を採るのがよかろう。やらなければどちらが良いかわからない」と応じられた。
このやり取りには元雅の確固とした信念が表れていて興味深い。やや飛躍して評定するなら、この曲の終末部には、アリストテレスの云う「逆転(ペリペテイア)」と「苦患(パトス)」が集約的に表現されていると見ることができる。母の唱える念仏の中から死者が仄かに蘇り、しかし夜がほのぼのと明けゆけばそれは塚の上の草にすぎなかったと謡われる。死者との再会はこのようなものなのであろう。私たちは物語のこの情景に触れて心が洗われるのを覚えるのである(浄化(カタルシス))。元雅はこのことのゆえに子方を出すことに固執したのであろう。しかし、筆者の師匠である金春安明師は問題の所在を次のように指摘されている。(『金春月報』2008年11月号)
(行方の知れぬ我が子を尋ねる狂女物の能は、その結末が母子再会のハッピーエンドとなるという)定式を敢えて壊し、子供が死んでいた形にした十郎元雅の構想は、「幽霊を実際に出すか出さぬか」などという枝葉の問題以上に世阿弥にとってはショックだったと考えられます。親子には時々、決定的な対立は回避して家族関係を円滑な物にしようという気持ちが働くことがあり、「子方を出す出さぬ」の裏に世阿弥の「子供が死んでいたなどとはもっての他」という、言うに言えなかった世阿弥のショックが隠されていたと考えるのは私の思い過ごしでしょうか?
子役を出すか出さぬかという舞台技巧的な問題以上に、能作者の人間観、さらには親子関係をめぐる実存的問題が根底にあるのではないかという指摘は、およそ表現者にとって何を描くことが内心の赦しにかなうのかという本源的な問題に触れていると思われる。この後、元雅が1432年に伊勢で急逝したことを思えば、親子のこのやり取りはいっそう意味深い問題を私たちに投げかけていると思われる。
さて、物語は旅の男が隅田川の渡しで船に乗るところから始まる。後方で賑わいの様子が見えたので船頭が男に何事かと聞けば、男は女物狂いがやってきたのだという。船頭は興を感じて、この狂女を船に乗せる前にからかってみようとするが、逆にやり込められる。都鳥のくだりである。
シテ(狂女)かの業平もこの渡りにて。名にしおわば。いざこと問わん都どり。わが思う人は。ありやなしやと. のう舟人。あの沖に白き鳥の見えて候は。京にては見ぬ鳥なり。あれは何と申す鳥にて候ぞ。
ワキ(渡守)あれこそ沖の鴎という鳥よ。
シテよし浦にては千鳥ともいえ鴎ともいえ。この隅田川の白き鳥をばなど。都鳥とは答えたまわぬ。
業平の歌を引くことなく隅田川の白い鳥を鴎と答えた船頭の無粋をなじったのである。当意即妙の返答ができぬとはなんと東人(あずまひと)(田舎者)なというわけである。この箇所が、次に記した『伊勢物語』第九段「東下り」を下敷きにしていることはよく知られている。
猶行き行きて、武蔵の国と下つ総の国との中に、いと大きなる河あり。それをすみだ河といふ。その河のほとりにむれゐて、思ひやれば限りなくとをくも来にけるかなとわびあへるに、渡守、「はや舟に乗れ。日も暮れぬ。」といふに、乗りて渡らんとするに、皆人物わびしくて、京に思ふ人なきにしもあらず。さるおりしも、白き鳥の嘴と脚と赤き、鴫の大きさなる、水のうへに遊びつ繰りつゝ魚をくふ。京には見えぬ鳥なれば、皆人見知らず。渡守に問ひければ、「これなん宮こどり」といふをきゝて、
名にし負はばいざ事問はむ宮こどり わが思ふ人はありやなしやと*
とよめりければ、舟こぞりて泣きにけり。
*この歌は『古今和歌集』にも収められている。ちなみに『新古今和歌集』には次の歌が詠まれている。
おぼつかな都に住まぬ都鳥 言問ふ人にいかが答へし (宜秋門院丹後)
狂女と船頭の掛け合いは初同「都鳥の歌」へと高まっていく。美しい仕舞と謡の小段である。
われもまた。いざこと問わん. 都鳥。
いざこと問わん都鳥。
わが思い子は東路に。ありやなしやと。
問えども問えども答えぬはうたて都鳥。鄙の鳥といいてまし。
げにや舟競(きお)う。堀江の川の水際に。来居つつ鳴くは都鳥。*
それは難波江これはまた. 隅田川の東まで。
思えば限りなく。遠くも来ぬるものかな。
さりとては渡守. 舟こぞりて狭くとも. 乗せさせたまえ渡守.
さりとては乗せ. たまえや。
* 舟競(きお)う堀江の川の水際に 来居つつ鳴くは都鳥かも(『万葉集』巻二十)
難波の堀江の川は舟が先を争うように行き来して賑わっているが、その舟の間にやってきて鳴いているのは都鳥だ。
渡船の周りには都鳥が群れて鳴いていたのであろう。都鳥は在原業平のゆかりの鳥であるが、作品の中ではある密かな意味がこの鳥に託されているように思われる。都鳥は物語の鍵というべき役割を担わされた、いわば影のシテのような存在なのである。都鳥は狂女の水先案内人である。狂女は都鳥に問う。「わが思い子はありやなしや」と。しかし舟に乗ろうとするこのとき、人の耳には都鳥はみゃあ、みゃあと鳴くばかりで一向に答えてくれそうにない(「みゃぁ」と鳴く小鳥だから「みや小鳥」と呼ばれたのだという駄洒落がある」。私はひそかに思うが、都鳥はそのとき「現れる(あり)、しかし亡霊となって(なし)」と答えていたのであろう。さて、一行が船に乗ると川向うから念仏の声が聞こえてきた。船頭はこれについてあわれな物語があるといい、語り始める。「ワキの語り」の場面である(ワキの重い習いである)。一人の少年が人商人に連れられてこの地まで来たが、病に倒れ置き去りにされたまま命果てたという話であった。狂女はその子が自らの一子梅若丸であることを知る。次はその「ワキの語り」である。
さても去年三月十五目。や。しかも今日の事に候。都より人商人。年の頃十二三ばかりの幼き者を買うてくだる。かの幼き者習わぬ旅の疲れにや。路次よりも以ってのほかに違例し。今はひと足も引いつべくもなく候と申す。なんぼう世には不得心なる者も候ぞ。かの幼き者をばこの所に捨ておき。商人は奥へ通りて候。
さるほどに所の面面不びんに存じ。いろいろ看病つかまつり候えども。ただ弱りに弱り。すでに末期に及び候ほどに。かの者の国はいずく。名字はいかなる人ぞと尋ね候えば。われはこれ都北白河に。吉田の某と申しし者のただ一子にて候が。父にはおくれ母ひとりに添い参らせ候いしを。人商人にかどわされ。この所までくだり候。われむなしくなるならば。路次の土中に築きこめてたまわり候え。それをいかにと申すに。都の人の足手形までも懐しう候。ただ返す返すも母上こそおん名残おしう候え。生年十二才。その名は梅若丸と申し。おとなしやかに念仏四五へん唱え。ついにむなしくなりて候。
さるほどに遺言にまかせ。路次の土中に築きこめ。しるしに柳を植えおきて候。今日はかの者の一周忌に当りて候ほどに。所の面面寄り合い。大念仏を申し跡を弔い申し候。また船中を見申せば。都の人も少少こ座ありげに候。今日はこの所にご逗留あって。大念仏の人数に入りたまい。かの者の跡を弔うておん通り候え。
次は一子の末期を知って狂乱し、そして茫然自失に陥った狂女の絶唱である(シテと地謡の至難の謡所である)。
シテ今まではさりとも逢わんの頼みにこそ。はるばる尋ね下りしに。
さてもむざんや死の縁とて。
生所を去って東のはての。道のほとりの土となって。
春の草のみ生い茂りたる。この下にこそあるらめ。
さりとては人人。
地この土を。返して今一度。
この世の姿を. 母に見せさせ. たまえや。
残りてもかいあるべきはむなしくて。かいあるべきはむなしくて。
あるはかいなき帚木の。見えつ隠れつ面影の。定めなき世の習い。
人間憂いの花ざかり。無常の嵐音添い。
生死長夜の月の影. 不定の雲おおえり.
げに目の前の浮世かな. げに目の前の. 浮世かな。
帚木は遠くからそれと見られても近づくと見えなくなるという木である(能「木賊」を参照)。この木の「見えつ隠れつ」は「ありやなしや」に対応している。塚を目の前にしても狂女の前にはなお面影が「見えつ隠れつ」しており、狂女の心は我が子の生死不詳の雲の中にいるのである。泣き崩れる狂女に渡守はともに念仏に加わるように諭し、鉦鼓を渡す。狂女は母の念仏を子は喜ぶかと、参会者とともに一心不乱に念仏を唱える。印象的な祈りの場面である。
南無阿弥陀仏の声は低く高く隅田川に漂っていく。金春流では南無阿弥陀仏が十五回繰り返される。三つの南無阿弥陀仏が一組になり、変調していくのである。始めはゆったりと、そして次第に高揚した謡になっていく。一同の祈りの声が高らかに虚空を満たしていくさなか、異声(ことこえ)が聞こえてきたのであった。
シテ月の夜念仏もろともに。
ワキ心は西へとシテ一筋に。シテ・ワキ南無や西方極楽世界。三十六万億。同号同名阿弥陀仏。
シテ南無阿弥。 地陀仏南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。
シテ隅田川原の。波風も声立てそえて。
地南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏。
シテ名にしおわば.都鳥も音を添えて。子方・地南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏。シテいかに人人。今の幼な声はいずくのほどにて候ぞ。
ワキ正しくこの塚のほとりにて候。
シテ今のはわが子の声なりけるぞ。今一声こそ聞かまほしけれ。南無阿弥陀仏。
子方南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏。
地声の内より。幻に見えければ。
あれはわが子か。母にてましますかと。
互に手に手をとり交わせばまた 消え消えと失せければ。
いよいよ思いは増鏡。
面影もまぼろしも。見えつ隠れつするほどに.
東雲の空もほのぼのと。明け行けばあと絶えて。
わが子と見えしは塚の上の草 ぼうぼうとしてただ.
しるしばかりは浅茅が原と.なるこそ哀れなりけれ.
なるこそ哀れ. なりけれ。
異声は、はじめは念仏の声にあわせて隅田川の波風も声を立て添えて南無阿弥陀仏と唱和しているように伝わってくる。しかし見よ!都鳥も「音を添えて」南無阿弥陀仏と唱えている。都鳥の声はしかし同時に亡霊の声でもあった。この箇所は、「都鳥も音をそえて。南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏.南無阿弥陀仏。」と謡われるが、都鳥の「音」は亡霊(子方梅若丸)の謡と化して狂女の耳に届く。そして声の内より幻に亡者は現れるのである。見えつ隠れつ、そして消え消えと。舞台では白装束に身を包んだ子方が塚の後ろから現れ、母の懐に駆けよるが、そのまますり抜け、ふたたび塚のなかに消える。そして、東雲の空がほのぼのと明けるころ、すべては夢幻となって草におおわれた塚が残ったのであった。元雅が意図した「ありやなしや」の演出である。
都鳥は、亡霊が帚木のように「見えつ隠れつ」し、有りかつ無し(「ありやなしや」)という茫漠とした様で現れることを教えたのであろう。都鳥は生者と死者を仲立ちする彼岸の使者なのであろう。
2020年2月24日
盲目のあはれ ――能の詞花を訪ねて19
盲目の人物を取り上げた能に「蝉丸」、「弱法師」、「景清」がある。これら三つの作品は三者三様の盲目の姿を描いているが、ここではそれらの作品を取り上げて、それらの作品において、「見る」ということがどのように表現されているかをたどってみることにしよう。
能と盲目の世界との関係が浅くないことは、修羅物の多くの作品が盲目の琵琶法師の語りによって伝えられた『平家物語』から採られていることを思い起こせば容易に理解されよう。また他の多くの曲でもシテたちは、帳を降ろされた深夜に、あるいは件の相手以外の他の衆人には見えない姿で、または声ばかりして姿はおぼろげにしか見えない形で、登場する。明明とすっかり見えるということは能の世界ではほとんど無縁なのだ。もとより、能面はいわば視界を奪う装置であり、能面のシテは「半盲目」の状態に置かれることによって演技の世界に入るのであるから、能そのものが盲目と親近性を有しているのである。たなびく雲の合間からほの見えるということが日本美の典型ですらあったのだ。「見えない」ことはその背後にある「非可視的なもの」が浮かび上がることであり、能はそのような非可視的なものを追求する芸術でもあったのである。そして見えない世界の極みが盲目である。
ところが、「見えない世界」は視野的なものにとどまらない。精神的な不明ということもあるのだ。能の多くの主人公たちは、その不明のゆえに運命に翻弄された人物として描き出され、いわば「心の盲目」の持ち主であると言われてもあながち外れていないであろう。盲目にも肉眼の盲目と「心の盲目」とがあったのだ。いずれの盲目も人間がこうむる大きな苦患の一つである。苦患は人の心に深い溝を刻む。能はそのような苦患のなかに置かれた人間の生きざまに着目してきた。修羅物、執心物、狂女物など、人の苦しみの描かれることが何と多彩なことか。テーマとしての苦患にことさら向かおうとするのが、能の着眼であり見識である。そして盲目はそのような苦患の一つの極みでもあったのである。
「蝉丸」を見てみよう。ツレの蝉丸は醍醐天皇の第四の皇子であり、生まれながらの盲目である。「いま皇子とは成りたまえども。襁褓 (おしめ)のうちよりなどやらん両眼しいましまして。蒼天に月日の光なく。闇夜に灯火暗うして。五更の雨も。やむことなし。(暗闇の涙も乾くことがない。五更は午前四時ころの時刻をいう。)」 ところが、成長した蝉丸は宣旨によって逢坂山に捨てられるのである(名ばかりの出家という形で)。山中で行われる「出家」をめぐる悲しい悲歌が心を打つ。さて、逢坂山にひとり取り残された蝉丸は、日々琵琶をかき鳴らしながら涙にくれる日々を送った。
たまたまこと訪うものとては。
峰に木伝ふ猿の声。
袖をうるおす村雨の。音にたぐえて琵琶の音を。
弾き鳴らし弾き鳴らし。
わが音をも泣く涙の。
雨だにも音せぬ。藁屋の軒のひまひまに。
時時月はもりながら。目に見ることの叶ねば。
月にも疎く雨をさえ。聞かぬ藁屋の起き臥しを。
思いやられて痛わしや。
ここで謡われるのは聴覚の世界である。猿の声、琵琶の音。涙とともにいつまでも弾き鳴らす琵琶の音は雨の音と競いあうようである。ところが藁屋ゆえ雨音も消え、やがて差し込む月光も盲目ゆえに見ることができない。――無音の寂寞に沈みゆく盲者を謡う悲歌である。
物語は、姉宮の第三の皇女逆髪の宮(シテ)の登場によって劇的な展開を遂げる。彼女もまた狂乱のゆえに宮中を追われていたのである。彼女は「辺土遠境」をさ迷っていたが、逢坂山に辿りつき姉弟の再会となる。
さて、能では姉と弟の再開、ひとときの会話、そしてやがて訪れる別離が語られるばかりであるが、むしろそこに私たちは日常を絶した悲痛の空間を感じ取る。作者は、皇子の姉弟という雲上と、狂気と盲目という地底を二つながらに結合させ、高貴と苦患とが隣接し相互に浸透しあうことを、しかもそれは血を分けた情愛によって救われることを描こうとしたのではなかったであろうか。盲目は人を襲う負の境涯であるが、救われないその生のなかにも一条の光が届き、その生を灯し続けることを描くのは、実に能作者の使命でさえあるだろう。盲目の蝉丸はその出会いの光をひたすら琵琶の音に転化させることによって救済されるべく定位されたのであろう。
この能は、逢坂山の歌で知られ、平家琵琶の礎を築いたと云われる平安期の伝承的人物蝉丸を下地に置いている。盲目は創造の撥条であるが、作者はこの盲目の歌人であり琵琶法師である人物の苦患を語ることによって音の世界に「讃歌」を捧げようとしたのではないだろうか。
「弱法師」は「しんとく丸」(能では俊徳丸)という伝承説経をもとに作られた曲である。この「しんとく丸」は、「小栗判官」や「山椒大夫」とともに室町から江戸の時代にかけて流行した「説経節」の一つである(能では「自然居士」が説教節の様子を伝えている)が、継母の呪いによって盲目にされたしんとく丸が観音の化身かと思われる乙姫のひたむきな愛によって救われるという物語である。
能の「弱法師」は伝承の物語を少々変更している。俊徳丸(シテ)はある者の讒言により家を追放され、盲目の乞食となり、差別の逆境のなかを生きていたが、天王寺に流れつき、そこで施行を受けて身命を保つ日々を送る身となっていた。そこに、自らの不明を悔い、施行を行うことによって罪を贖おうとした父の左衛門尉通俊がやってきた。
ワキ(通俊) や。これに出でたる乞丐
人。いかさま例の弱法師な。
シテ(俊徳丸) また我らに名をつけて。皆弱法師とおせあるぞや。
げにもこの身は盲目の。足弱車のかたわながら。よろめきありけば弱法師と。
名づけたもうは.ことわりや。
ワキ げに言い捨つる言の葉までも。情ありげに聞こうるぞや。
まずまず施行を受けたまえ。
シテ 受け参らせ候わん。や。花の香のきこえ候。
ワキ おうこれなる籬の梅の花が。弱法師が袖に散りかかるぞとよ。
シテ うたてやな難波津の春ならば。ただこの花とおせあるべきに。(1)
今は春べもなかばぞかし。梅花を折つて頭にさしはさまざれども。
二月の雪は衣に落つ。(2)あら面白の梅の匂いやな。
ワキ げにこの花を袖に受くれば。花もさながら施行ぞとよ。
(1)「難波津に咲くやこの花冬籠り今は春辺と咲くやこの花」を引いて、梅ではなくこの花と言うべきだ、と詰った。
(2)『和漢朗詠集』の「折梅花而挿頭 二月之雪落衣」によった。同じ歌が「高砂」にも引かれている。二月の雪は梅の花の形容。
物語は、互いに気づかぬ親子の淡々とした問答によって進展するが、まずその日が彼岸の中日(如月時正の日)であることが示される。天王寺ではこの日、「日想観」という行を行うために人々が集ったのである。「日想観」とは、春と秋の彼岸の中日に真西に沈む入り日に向かって正座し、西方浄土を拝む祈りの修行をいう。天王寺では西門石の鳥居に向かって座すと難波の海に沈む太陽を拝むことができたのである(長く途絶えていたようであるが、近年復活して入り日を拝む信者で賑わうという)。西方から届く陽光は救済の光である。彼岸の中日のこの日、盲目の弱法師は救済の光を受けて断然世界が見えたのである。海の彼方の淡路島、須磨明石、紀の海までも見えたのである。それどころか住吉の松原や浅香山、長柄橋まで見えた弱法師は浮かれて歩き出す。しかし、盲目の彼は往く人に当たり、足元もよろよろとまろび漂うばかりであった。
住吉の。松の木間より。眺むれば。
月落ちかかる。淡路。島山と。
眺めしは月影の。眺めしは月影の。
今は入り日や落ちかかるらん。
日想観なれば曇りも波の。
淡路絵島.須磨明石。紀の海までも.
見えたり見えたり。
満目青山は.心にあり。
おう.見るぞとよ見るぞとよ。
……
長柄の橋のいたずらに.かなた。こなたとありくほどに。
盲目の悲しさは。
貴賎の人に 行きあいの。まろび漂い難波江に。
足もとはよろよろと。
げにも真の弱法師とて。人は笑い給うぞや。
思えば.恥かしや。
今は狂い候わじ.今よりはさらに狂わじ。
さて、「見える」とはどういうことであろうか。盲者もある刹那には見えたのである。「満目靑山は心にあり」。彼の心の目に、肉眼の目よりも、ありありと見えたのである。弱法師の心にはその祈りの瞬間、帳が開かれて世界が開示されたのであろう。見えるとは世界が開示されることだったのである。その限りでは、見えるのは肉眼であるか心眼であるかは問われない。世界が開かれ、見る側からも心が開かれるとき、「見る」という営みが成立するのである。
ここには「見る」ということの根源的な意味がある。見ても意がそこになければ見えず、目を閉じていても心が働けば「見える」。見ることはたんに感覚的なことがらなのではなく、精神的な、そういってよければ魂の衝動的な営みである。対象となる物と「対面的に」向かい合うことによって、心と物とのあいだに一条の光が通ったとき、人は見るのである。そのとき何が「見えた」のであろうか。人は或るものを見るときに形象を通してそのものの「意味」、そのものとの「関わり」、そして「己の鏡像」を見ているのである。「日想観」はこの意味で「見る」ことの類まれな救済の祭礼だったのである(見ることの究極は西方浄土を見ることだという)。
「景清」は、平家の武将悪七兵衛景清の盲目の晩年を描いた能であり、平家滅亡ののち頼朝を狙った一件を物語る「奈良詣(大仏供養)」と対になる曲である。また、景清は多くの伝承を残し、歌舞伎等でも「景清物」として謳われた人物である。各地に景清や人丸の伝承が残されており、塚や墓が大切に保存されている。「平家物語」によって親しまれ、晩年の不遇のゆえに後の世のあわれの共感を引いたのであろう。
晩年盲目となった景清は、日向国宮崎に流され、所の人々の世話になりながら不遇をかこっていた。
松門ひとり閉じて。年月を送り。
みずから.清光を見ざれば。
時の移るをも。わきまえず。
暗々たる庵室にいたずらに眠り。
衣寒暖に与えざれば。肌は髐骨
と衰えたり。
そこへ鎌倉からはるばる娘の人丸が訪ねてきた。宮崎についた人丸はとある盲人の住む草の庵に立ち寄り、景清のことを問えば知らぬとの答え。ところが里人に問えば、その盲人こそ景清であるという。里人に伴われて再び訪れた人丸に対して、景清は始めはしらを切っていたが、里人の一計によって親子であることを認め、親子再開となった。彼は親が罪人であることが知られると娘の身に不都合が起きるかも知れないと包み隠していたのであった。
今までは包み隠すと思いしに。
現れけるか露の身の。置き所なや恥ずかしや。
おん身は花の姿にて。
親子と名のりたもうならば。ことに我が名も現わるべしと。
思い切りつつうち過ごす。
われを怨みと。思うなよ。
全曲に盲人の悲痛と苛立ちが漂う曲である。彼の心を支えていたものは昔の武勇と高名だけだったのであろう。戦語りを頼まれた景清は往時に戻ったかのごとく滔々と語りだすのであった。
この曲でも、盲人特有の感覚の鋭さが語られている。長い年月を経て娘が訪ねてきたことも出会いの当初から見抜いていた。庵での孤高の生活にあっても彼の五感は研ぎ澄まされている。武勇から感性の繊細へ、そして寂滅の世界へ――景清のたどった道である。
目こそ暗けれど。
目こそ暗けれども。
人の思わく。一言の内に知るものを。
山は松風。すわ 雪よ
見ぬ花の。覚むる夢の惜しさよ。
さてまた浦は荒磯に。寄する波も
聞こゆるは。夕汐もさすやらん。
*目こそ暗いが、その一言を聞けば人の心はわかるもの。
山に吹く松風を聞けば雪の到来がわかるもの。
見ることもない花を楽しんでいれば、その夢が覚めるのが惜しい。
荒磯に打ち寄せる波の音が高くなっているのが聞こえるが、夕潮がさしてきているのであろう。
2019年12月26日
草木讃歌 ――能の詞花を訪ねて18
「芭蕉」に次のような一節がある。
今宵は月もしろたえの。
氷の衣。霜のはかま。
霜の経。露の緯こそ。弱からし。
草のたもとは。
ひさかたの。ひさかたの。
天つ乙女の羽衣なれや。
これも芭蕉の葉袖をかえし。
かえす袂も芭蕉の扇の風
ぼうぼうとものすごき古寺の。
庭の浅茅生女郎花刈萓。
面影うつろう露の間に。
山おろし松の風。吹き払い吹き払い。
花も千草もちりぢりに。花も千草も.ちりぢりになれば。
芭蕉は破れて.残りけり。
何と哀れな詩情のことよと思う。この能の作者禅竹の枯淡の心がよく現れた曲である。冷え冷えとした月光のもと、庭は白一色の世界である。草のたもとは「氷の衣。霜のはかま。」にまとわれ、「霜の経。露の緯。」に飾られている。彼は、寒風に乙女の羽衣ならぬ葉袖をなびかし、ちりぢりに裂け乱れる芭蕉のさまに心を通わせているのである。
能「芭蕉」は秋の半ばに季節が設定されており、中秋の月のもとで僧(ワキ)と女(シテ)とが法の教えについて語り合うという筋書きであるが、月光が芭蕉の葉を白々とさすなかで、女はいつしか雪の芭蕉に想いを寄せるようになる(唐の詩人王摩詰が雪中芭蕉の画を描いたという故事によっている)。そして女は自らが芭蕉の精であることを明かし、月のさやかな光も初冬の寒々とした山おろしに変わり、月光と雪明かりとが二重写しになって、すべてが大地に帰るという生命の冬へと心を滑らせていく……。あるいは、このような幻想の世界はすべて僧の心のうちに生じた夢想にすぎなかったのかもしれない。
「遊行柳」は観世信光の作であるが、「芭蕉」に相通じる終焉の趣を描いている。これもいまにも死を迎える枯木を描いた作品であるが、描かれた柳の精にはおのれの末期の生を見とどけようという気骨があり、「芭蕉」に見られる幻想性とはやや異質の趣がある。
今年ばかりの。風やいとわんと。
ただよう足もとも。よろよろよわよわと。
倒れふし柳。
かり寝の床の。草の枕の。一夜の契りも。
他生の縁ある。上人の御法。
西吹く秋の風うちはらい。
露も木の葉も。散りぢりに。
露も木の葉もちりぢりになり果てて。
のこる朽木と。なりにけり。
いずれの曲からも生命の残照を見届けようという作者の思いが伝わってくる。この残照は暮色であり、薄明であるが、救済(成仏)に迎えられた反照でもある。終末は滅亡ではなく、再生への眠りであることをこれらの植物は教えているのである。ところで、「芭蕉」には『法華経 薬草喩品』に触れた箇所がある。
薬草喩品現れて。
草木国土有情非情も。
皆これ諸法実相の。
峰の嵐や。谷の水音。
仏事をなすや. 寺井の底の。
心も澄める. おりからに。
「薬草喩品」は『法華経』二十八巻のうちの一であるが、この経典ほど日本人の生命観と宗教的心性に深い影響を与えたものはないであろう。そこでは仏による人間の救済(衆生済度)が雨露と草木との関係の喩えによって語られている。山川国土悉皆成仏の教えである。およそ植物に霊性と成仏をみとめ、崇拝の思いを寄せた他に例を見ない経典である。少し長いが引用しておこう。
譬えば、大雲の
世間に起りて 遍く一切を覆うが如し。
恵みの雲は潤を含み 電光は晃曜き
雷声は遠く震いて 衆をしてよろこばしめ
日光を掩い蔽して 地上を清涼にし
たなびくくもは垂れ布きて 承とるべきが如し。
その雨は遍く等しく 四方に倶に下り
流澍ぐこと無量にして 率土に充洽す
山川・険谷の 幽邃に生ずる所の
卉木・薬草と 大小の諸の樹と
百穀・苗稼 甘蔗・葡萄とは
雨の潤す所 豊足せずということ無し。
乾ける地は普く洽い 薬木は並び茂り
その雲より出ずる所の 一味の水に
草木・叢林は 分に随って潤を受く。
一切の諸の樹は 上中下等しく
その大小に称いて 各、生長することを得
根・茎・枝・葉と 華・果との光色は
一雨の及ぶ所 皆、鮮に沢うことを得て
その体と相と 性とは大小に分かれたるが如く
潤す所は、これ一なれども しかも各、滋茂するなり。
私たちによって受け継がれた感性遺伝子には植物讃歌の心がある。草木の生きざまは人間のそれとはずいぶん異なるが、それでも人間にとって模範であり、手本である。草木は慈雨を呼び、そのうるおい(潤、洽、沢)によって繁茂し、自らの潤いを周りの自然におし広げ、いっさいの大小異種がそれぞれの姿のままに共存する。太古より人々はそのことを熟知し、畏怖の想いとともに草木と共生してきたのだ。
万物に遍く等しく降る雨によって、一切の生ある草木がそれぞれの性に応じて、それぞれの仕方で潤いを受け、それぞれの個性にしたがって生育するという思想は、生命の本質を言い表してみごとである。古の日本人は、この経典に出会い、満空の喜びとともにその思想を受け入れ、彼らの信仰の拠り所としてきた。そして草木のこのような生きざまをを自らのこととして了解し、自己の内なる心を外なる山川草木に通い合わせ、山川の景観を自らの内なる思いの具象と理解したのである。夕陽に一切が赤く染め上げられるように、内なる心が周りの色調によって染め上げられ同期化する。己の内奥の思いが外なる世界(自然世界であって「社会」という世界ではない)と一体になることが彼らにとって救済だったのである。
これが悉有に仏性があるということの具体的な意味である。この悉有仏性の思想は平安期の仏教、とりわけ天台宗の根本教義に磨き上げられていった。天台はこの教えを本覚思想として「体系整備」した。一切の衆生、一切の存在そのものがその現実存在において仏性を持っており、すでに悟りを開いている。この世界そのものが仏の真如の現れである。草木は清浄純粋であり、いわば法身であると法華経は説いた。それゆえ草木は真如本覚をえており、それどころか仏そのものであり、その繁茂する世界は仏国土である。天台は人間における自己と世界との一体性を壮大な体系にまで仕上げ、一方では自然存在に霊性を認め、他方では自己の存在があらゆる他者と不二一体であることを説く。この融合が仏の教えの真諦であり、それはすべての言葉を超えて「法性不思議」と称せられた。
天台のこのような教えが平安末期にいたれば、民衆の信仰に浸透していき、浄土宗の教えとなって野火のように広がり、鎌倉期の宗教改革を呼び起こしたことについては今は触れないでおこう。ただ、天台本覚思想、およびその民衆への浸透としての浄土宗は一切の存在にはじめから仏性(一切衆生悉有仏性)を認めるゆえに、本来の釈迦の教えからいささか離れていると言わざるをえないかもしれない。釈迦の教えは徹底した求道と煩悩からの脱却としての懺悔を基底とするからである。日本仏教はこの至難道と悉有仏性の安楽道との二極を矛盾相克としてとらえることなく、そのまま物ごとの表裏のように整合しないまま張り合わせ融合させたのであった。
さて能に話を戻そう。「芭蕉」は草木の「法性不可思議」を伝えるべく構想された曲であり、「薬草喩品の能」と呼ぶにふさわしい作品である。後場では、芭蕉の精はその本体を現し、草木成仏の理を説いて謡う。
それ非情草木といつぱ。
まことは無相真如の体。
一塵法界の心地の上に。
雨露霜雪の形を見す。*
しかれば一枝の花を捧げ。
み法の色を現わすや。
一花開けて四方の春。
のどけき空の日影を得て
楊梅桃李. かずかずの。
色香にそめる心まで。
諸法実相。隔てもなし。
*非情の草木も本当の姿は形を超えた真実の存在そのものですが(生命そのものと読むこ
とも可能であろう)、一塵にも仏が宿るという教えのとおり雨露霜雪によって形ある草木となったのです。「見す」は現すの意味。
能には草木の精霊が登場する作品が他にいくつかある(「老松」「杜若」「西行桜」「六浦」「遊行柳」。また「高砂」は男神物であるが、シテは松の精でもあるから精霊物としての面も有している)。それらに見られるのは植物に生命の本然手本をみる思想であり、大地に根を張り、自然の巡りに順応し、風雪に耐える姿を描いた讃歌である。いずれの作品においてもシテ(草木の精霊)は自律心と矜持の心の持ち主であり、誇り高く、記念すべき思い出や由来を心の支えにしている。これらの曲の作者は、大地に根ざして動かず、あるいは花を咲かせ、また長寿をまっとうする生命の力に圧倒されたのであろう。そのいくつかの詞章を訪ねてみよう。
「老松」は、太宰府の安楽寺に生える松と梅を讃えた曲であり、「諸木の中に松梅は。ことに天神(菅原道真)のご慈愛にて紅梅殿も老松もみな末社(小さな神の意味か)と現じたまえり。」と謡う。
梅の花笠. 春も来て.
縫うちょう鳥の.梢かな。
松の葉色も時めきて。
十かえり深き.緑かな。
風を追ってひそかに開く。
年の葉守*の松の戸に。
春を迎えてたちまちに。
うるおう四方の草木まで神の恵に靡くやと.
春めきわたる盛りかな。
*年の葉守は、年の端と葉守の神を掛けた言葉。
「西行桜」は、西行の庵に生える老桜の気概を謡った曲である。西行が詠んだ歌、「花見にと群れつつ人の来るのみぞ あたら桜の科にはありける」をめぐって、桜の精と西行とが戯れのやり取りをし、また四方の桜を讃えるうちに夢が覚めるという筋である。西行の一夜の夢を描いた曲であるが、軽妙さのうちに春の夜の優艶へと誘う馥郁とした余情をただよわせている。
まことは花の精なるが。
この身もともに老木の桜の。
花ものいわぬ草木なれども。
とがなき謂れを木綿花の。
影唇を。動かすなり。
恥かしや老木の。
花も少なく枝朽ちて.
あたら桜の。
とがのなきよしを申し開く花の。精にて候なり。
およそ心なき草木も。
花実のおりは忘れめや。
草木国土まで.成仏のみ法.なるべし。
「六浦」は、相模国六浦の称名寺に生える楓の精の物語である。旅の僧が六浦称名寺にやって来ると、周りは紅葉が盛りなのに一本の楓のみが紅葉せず青々としていた。そこに現れた女にそのことについて問えば、女はこの地にやってきた鎌倉中納言為相が、周りの木々はまだ紅葉していないのにこの楓一本のみが美しく紅葉しているのを見て、「いかにしてこの一本にしぐれけん 山にさきだつ庭のもみじ葉」と歌を詠んだ故事を語った。歌を寄せられたその楓は大変名誉に思い、「功成り身退くは天の道」と心得て紅葉を封印し、それ以来紅葉することを止めて常盤木のように青い葉のまま秋を迎えたというのである。次は四季の移り変わりを謡った一節である。四季折々に咲き、紅葉する草木の姿こそが仏国土を現していると謡うのである。
それ四季おりおりの草木.
おのれおのれの時を得て。
花葉さまざまのその姿を.
心なしとは.たれかいう。
まず青陽の春の始め。
色香妙なる梅が枝の。
かつ咲きそめて諸人の.心や春になりぬらん。
または桜の花盛。
ただ雲とのみ三吉野の。
千本の花に.しくはなし。
月日経て.移れば変わる眺めかな。
桜は散りし庭の面に。
咲きつづく卯の花の垣根や雪にまごうらん。
時移り夏暮れ秋もなかばになりぬれば。
空定なきむら時雨。
昨日はうすきもみじ葉も。
露時雨もる山は.下葉残らぬ色とかや。
*いつもお読みいただきありがとうございます。次回より隔月(偶数月)に寄稿します。
2019年11月12日
六条御息所考 ――能の詞花を訪ねて17
六条御息所をシテとし、彼女の苦悩の物語を描いた能に「葵上」と「野宮」とがある。しかしこれら二曲は同じ人物を描いたとは思えないほど、曲想も性格も著しく異なる。方や御息所が物の怪(鬼女)となって怨念に打ち狂い病床の葵の上に襲いかかるという狂乱の能であり、方や嵯峨野野宮の月下の静謐のもとで光源氏との別れを描いた幽玄抒情の能である。
六条御息所という題材をどのように舞台化するかという問いには、このように対極的な答えが存するのであろう。そこには能とはなにかという問題に迫るための一つのヒントが潜んでいるように思われる。能は物語そのものをたどることに関心があるのではない。御息所の物語は、前坊の死という語られない暗部から始まり、死後も六条院の地下の霊として暗躍し、紫上に物の怪となって取り憑き彼女を死に陥れるまでの、本編の全体を覆う長大な、そして秘密とサスペンスに溢れた叙事詩なのである。能はこのような御息所の極限的な内的心情に注目し、その断面を舞台に映現させることに興味を持つ。そのとき御息所のような最高位の貴女が情念の錐揉みに苦しむさまが格好の題材となるのだ。
世阿弥は鬘物の能について、「貴人の女体、気高き風姿」の「幽玄無上の位」を描くことが「舞歌の本風」であると説くが、同時にこのような「貴人妙体の見風」の上に六条御息所の物の怪が葵上に付祟るような場面は「見風の便りある幽花の種、逢ひがたき風得なり」という。(世阿弥『三道』、本稿3の「能と物語」を参照)彼は、幽玄の芸術が誕生するためには苦悩や懊悩が不可欠だと考えたのであろう。
こうして御息所の能は、能における「幽玄」とは、たんなる神韻とした情感的な美を意味するのではなく、物の摂理(宿世)とそのまえに翻弄される人間の心情のあわれを知らしめるためのキーワードなのだということに気づかせてくれるであろう。とりわけ物の怪はたんなる怪異としてあるのではなく、それが貴女と結びついたときには幽玄の位をいっそう際立たせ、さらに得がたい「幽花の種」を与える題材になるとされるである。
それでは能は御息所の物の怪をどのようなものとして描こうとしたのであろうか。この時代の人々の生き方を枠づけし、彼らの心をとらえたものは、ものごとの背後にはたらく不可思議で超越的な作用力であった。いわば表の世界(現実世界)の裏面に「背後世界」(地霊ともいうべき隠密な働きの世界)があり、表の世界のさまざまな出来事には陰の地下的な作用が働くと考えられたのである。夢幻能の発想にはこのような背後世界の存在者が現世に(一時的に)帰還するというイデーが基底にあったことは言うまでもない。この作用力がふたたび内化され、人間の情念によって引き起こされると考えられたとき、怨霊や物の怪が誕生する。幽霊も物の怪もこのような背後世界の作用力の具体像であるが、物の怪は実力を行使する(幽霊は悪事を働かない)という点で幽霊よりも「強力」である。このようなより強力な異界存在者に「見風の便り」を求めるのは、能作者が情念世界の畏怖的な威力にある種の「超越美」を認めたからであろう。情念はそれが「受苦の思想」(御息所は多重苦の受け手であった)と結びついたとき、主観をその思惑を超えた宿命的な軌道へと投げ込むのだ。自己の裁量や判断で動くかぎり、そこには「超越的なもの」はない。宿世に苦しむ人間が不可思議な力によって翻弄されるとき、本物の「物語」が始まる。
私たちもまた、物の怪に襲われる主人公たちと同じように、恋慕やあわれの情に駆られることがあるが、それらが昂じて極限的状況にまでいたれば、精神の特異点というべき自失に陥るであろう。精神が突然に折れるのである。人間には自分では処理することのできない絶対的情念(これが狂気というものであろう)が潜んでいるが、そのような情念にいったん心が占拠されれば、日常の惰性的な宿念は一掃され、彼はいわば異常心理の虚空に放り出されるのである。般若面をつけた御息所(の物の怪)はこのような「限界情念」を姿態化させた公案であろう。人の心は葉末におく露のように儚いものであが、自然の不意のそよぎにその反照の色を変え、ときにはあおられて舞い散るものだ、ということを、作者は物の怪を介して伝えようとしているのではないだろうか。
能は物語ではなく、「曲」である。この曲が描く世界は自然描写ではなく、人の心の描写である。心という目に見えないものを可視化するのである。およそ文芸のフィールドには「物語の世界」と「情趣の世界」とがあるが、能は後者に属する。物語は不可思議の脈絡を追いかけ、能はその不可思議の一断面を切り取る。能のこのような性格によってその題材となった原作(『源氏物語』)はある意味で換骨奪胎されるが、いわば原作から新しい芽が生まれ、物語ゆかりの新たな「美的空間」が誕生する。能はいわば情念の黙示録を求める芸術である。とすれば御息所はその不可思議さゆえに格好の題材である。高貴であると同時に怪奇であるという二重性が彼女の内的世界を特異なものにしているのだ。能はこのような御息所の内面を怨念衝動と有情幽玄という二つの舞歌的映像に変換した。こうして狂女物と本鬘物の能が誕生した。御息所の二つの能は情念世界の二つの相にそれぞれが特化することによって、相互に共振関係を醸し出しているのである。
御息所の能を印象的なものにしているもう一つの要因は「宿世」の働きである。前世の宿業や「血の連接」が主人公たちの運命を導いていく。自らの自覚ではどうすることもできない負荷の連鎖が人から人に引き継がれていくのである。『源氏物語』は、いわば宿世の連鎖を描きあげた作品であるが、能はその宿世を主人公(シテ)の詞章と舞のうちに想起させる営みだと言えるであろう。観客は舞台に現れた技巧の美に目を奪われがちであるが、能のより深い興味はなぜ御息所の物の怪が葵上に取り憑かざるをえず、また彼女が伊勢に赴かざるをえなかったかというその心的要因に迫ることにある。そしてそこに宿世の連鎖を感じ取ったときに、能は一段と輝きを増したものとして受け取られるであろう。
能『葵上』は、生霊となった六条御息所の物語である。御息所は物語に登場する女性のなかでも、特異な性格と宿命を負った人物である。彼女は桐壺帝の弟前坊の正妻であり、斎宮となり後に冷泉天皇の中宮となった秋好中宮の母である。前坊は不慮の死を遂げた皇太子であり、その無念の心が御息所のなかに染みついていることが源氏や葵上たちの運命にも影響した。彼女は高い教養と品格をもち、源氏に見初められるが、その内向的な性格と気位の高さのゆえであろうか、次第に疎んじられるようになり、やる瀬ない想いに煩悶するのであった。その恨みは生霊となって、源氏の正妻である葵上に取り憑いた。次は物の怪となって光源氏の前に現れた御息所の歌である。
「物思ふ人のたましひは、げに、あくがるる物になむありける」と、なつかしげにいひて、
嘆きわび空にみだるる我がたまを 結びとどめよしたがひのつま(3)
との給ふ声・けはひ、その人にもあらず、かはり給へり。「いと怪し」と思しめぐらすに、ただ、かの御息所なりけり。 (葵巻)
*「思いに苛まれる魂はほんとうに肉体を離れて彷徨うものです」と、(御息所の物の怪は源氏に)親しげに言って、次の歌を詠んだ。
私の魂は嘆きに苦しんで空にさまよい出ようとしていますが、着物の褄を前紐で結ぶようにしたがひの紐で閉じ込めてください。
(したがひは着物の前を合わせたときに下になる部分)
と語る声も気配も葵上その人ではなく、別人であった。
源氏が「大変あやしい」と思いめぐらしてみればその声は御息所であった(葵上に御息所の物の怪が乗り移ったのである)。
嫉妬が全曲のテーマとしてこれほど強く押し出された曲は他にあるまい。およそ嫉妬はさまざまな情念のなかでも図抜けて強固なものであり、人は嫉妬の衝動から容易に抜け出ることができないであろう。人の心は嫉妬に侵されると怨恨に連鎖し、魂の自失にまでいたりかねないのだ。「枕の段」では、葵上の枕元に立った御息所の生霊がそのつらい思いを謡う。
思い知れ。
怨めしの心やあら、怨めしの心や。
人の恨みの深くして。
うきねに泣かせ給うとも。
生きてこの世にましまさば。
水くらき。沢辺のほたるの影よりも光る君とぞ契らん。(1)
わらわは蓬生の。
もとあらざりし身となりて。
葉末の露と消えもせば。(2)
それさえことに怨めしや。
夢にだに。かえらぬものをわが契り。
昔語になりぬれば。
なおも思いは増鏡。
その面影もはずかしや。
枕にたてるやれ車(3)。
うち乗せ隠れゆこうよ。うち乗せ隠れゆこうよ。
- 私のこの深い恨みは、そなたがどんなに苦しみ泣こうとも、生きているかぎりは光源氏と契るであろうから、晴れないのだ。
- 私はもとあらの(根本がすけすけの)蓬に置く露のように消えてしまっても、
- 破れ車。車争いのときの無残な姿を思い起こしているのである。
能「葵上」における嫉妬を表現する演出は卓越している。般若面と鱗尽しの装束もさりながら、唐織をかずいて床にうずくまる所作は意表を突く。嫉妬を描いてこれにまさる演出はないであろう。悲痛ゆえに「あくがれでた」物の怪はたんなる攻撃者ではないのだ。むしろ物の怪の抗う姿は苦患の姿を表しており、その苦悩は悲運の宿世に絡め取られた亡者のそれと重なるであろう。
他方、能「野宮」は善竹の作品であり(伊藤正義の説による)、御息所と光源氏との別れのシーンを描いた能である。源氏のもとから去ることを決心した御息所は、娘が斎宮となり、「野宮」(斎宮が伊勢に赴く前に潔斎をする宮)で潔斎をするのに付き添い、伊勢まで同行したのである。それでも彼女の心は揺れ動き、振り切りたいという思いと未練とが縺れあって身に纏わりつくのだった。彼女は「釣りする海人のうけ(浮き)」のような精神状態となって足が地に着かなかった。いよいよ伊勢下向が迫ってきた晩秋の月の夜、源氏が野宮に訪ねてきた。次の一節は晩秋の野宮の抒情を謡ったものであるが、その風情は能「野宮」にそっくり写し取られている。
はるけき野辺を、分け入り給ふより、いと、物あはれなり。秋の花、みな衰へつつ、浅茅が原も、かれがれなる虫の音に、松風すごく吹きあはせて、そのこととも、聞きわかれぬ程に、ものの音(楽器の音)ども、たえだえ聞えたる、いと艶なり。…物はかなげなる小柴を大垣にて、板屋ども、あたりあたり、いと、かりそめなり。黒木の鳥居どもは、さすがに、神々しう見渡されてわづらはしき(気が引ける)気色なる…。火焼屋(神饌を調理する建物)かすかに光りて、人げなく、しめじめとして、ここに、物思はしき人の、月日隔て給へらん程を、おぼしやるにいと、いみじうあはれに、心苦し。 (賢木巻)
能「野宮」では全曲にわたって晩秋の月下の夕べの物寂しい情景が謡われる。御息所の憂愁と晩秋の野宮の寂寞とが重なり合い渾然一体となって描かれているのである(幽玄の真骨頂である)。旅の僧が秋の末の夕べ、嵯峨野の里の野宮を訪ねた。黒木の鳥居に佇んでいると、一人の女が忽然とあらわれもの悲しげな歌を謡った。そして野宮は神事をなすところだから立ち去れという。僧がその神事のいわれを聞けば、女は御息所と源氏との月下の再会の物語を語り、黒木の鳥居のもとでふと姿を消した(中入)。僧が跡を弔っていると、御息所の霊があらわれ、賀茂の祭で葵上と車争いをしたときの無念を語ったが、それも月光の清浄に心が洗われたのか、御息所は静寂のうちに序ノ舞を舞い、キリを舞い収める。その抒情には他曲の追随を許さない美しさがある。
善竹は、源氏と御息所との別れの場面(キリ)を美しい言葉で描き出している。その趣は、生霊の激越な様を描いた『葵上』とまったく対称的であり、鎮魂の祈りを思わせる。
野の宮の。
月も昔や。思うらん。
影さびしくも。
森の下露。森の下露。
身のおき所もあはれ昔の。
庭のたたずまい。よそにぞかわる。
気色も仮なる。小柴垣。
露打ち払い訪われしわれもその人も。
ただ夢の世とふり行く跡なるに。
誰まつ虫の音は。りんりんとして。
風茫々たる。野の宮の夜すがら。
あわれなり。
ここはもとより忝なくも。
神風やいせの内外の鳥居に.
いで入る姿も生死の道を。
神はうけずや思うらんと。
また車にうち乗りて.
火宅の門をや.いでぬらん 火宅
シテの舞はどこまでも静かであるが、「いせの内外の鳥居にいで入る」の謡に合わせて、黒木の鳥居を伊勢の鳥居に見立て、重要な型を舞う。御息所は斎宮となった娘(後の秋好中宮)に同行して伊勢神宮に向かうが、それは源氏との関係を断つという行為でもあった。鳥居に出で入るとは、現世(光源氏)への執着を断つという思いと都に留まりたいという思いの板挟み状態をあらわしているのであろう。舞台正面に置かれた小柴垣の鳥居は物語の全編をつうじて流れる怨念と諦観という二つの情念の結節であると同時に、源氏のいる都での生活と伊勢という孤高の世界の結界をも表しているのであろう。「舞台は清浄な野宮、時はもの寂しい秋、人は恋を失った貴婦人、すべての条件を具備した幽玄な曲柄」(佐成謙太郎)は、じつに幽玄のランドマークのような作品である。
なお、任を終えて都に戻って来た斎宮は御息所の死後、源氏に引き取られ、ほどなく冷泉帝の中宮(秋好宮)として入内し、栄華の道を歩むようになる。六条院(源氏は御息所の館跡に壮大な邸宅を建てた)をわが里とし、源氏によって父親のように庇護された彼女は母の苦しみの代償であるかのようだ。
2019年10月14日
白拍子と乱拍子 ――能の詞花を訪ねて16
「道成寺」と聞けば誰しも「乱拍子」のことを思い浮かべるだろう。そして、なぜあれほど激越した所作が能の世界に存在するのか訝るであろう。
「乱拍子」は、今日では「道成寺」のみに存在するが、かつては他の曲にも存在した。それらが退転し、「道成寺」の乱拍子のみが残り、今日見られる破格の型になった。足遣いを主とした特殊な舞事であり、シテは小鼓と対峙し(小鼓はシテの方に座り直す)、小鼓による長い間合いと鋭いかけ声と鼓の打音にシテの足遣いが対応する。極度の緊迫感を漂わせながら、長い時間をかけて正面から少しずつ鱗型に左に回り、再び正面を向くと、テンポが変わり、一転して「急々ノ舞」となる。舞手は白拍子(前シテ)である。白拍子が乱拍子を舞う――そこにはどのようなルーツがあるのだろう。
白拍子の興りについて『徒然草』第二百二十五段は次のように伝えている。
多久資が申しけるは、通憲入道(1)、舞の手の中に興ある事どもを選びて、磯の禅師(2)といひける女に教へて舞はせけり。白き水干に、鞘巻(3)を差させ、烏帽子を引き入れたりければ、男舞とぞ言ひける。禅師が娘、静と言ひける、この芸を継げり。これ、白拍子の根元なり。仏神の本縁を歌ふ。その後、源光行(4)、多くの事を作れり。後鳥羽院の御作もあり、亀菊(5)に教へさせ給ひけるとぞ。
- 藤原信西入道で知られる。後白河院の腹心であったが、平治の乱で捕らえられて処刑された。
- 最初の白拍子とされる女性である。静御前の母。
- つばのない刀。
- 後鳥羽院に仕え、多くの白拍子舞を作曲した。河内本『源氏物語』の校訂者でもある。
- 後鳥羽院が寵愛した妓女であり、院が隠岐に流されたとき自ら同行した。
これによると、藤原信西が磯禅師に男装をさせ、拍子にのり勢いのある白拍子舞を工夫したのであろう。白拍子舞は、その娘静御前の代になって彼女の名声とともに急速に広まった。しかし、白拍子という舞女の芸はその後長く続かず、表舞台から消えていった*が、一方では曲舞や幸若舞などに受け継がれ、他方ではセメの拍子が乱拍子となって翁猿楽を作り上げていったと考えられている。
* 服藤早苗によれば(「傀儡女の登場と変容」埼玉学園大学紀要人間学部篇10、2010年)、後鳥羽院が隠岐に流されて以降、十三世紀になると傀儡女や白拍子は急速に消滅の一途をたどったという。「鳥羽院崩れさせ給ひて、物騒がしき事ありて、あさましき事出て来て、今様沙汰も無かりし」(『愚管抄』)。
伊藤正義は乱拍子について、「元来は能の以前から独立して存在した雑芸の一で、『梁塵秘抄口伝集』十三に「乱拍子と云今様を才男子あこ丸うたひにき…楽の常拍子なり…乱拍子に打て一句ごとにあつるなり」と見え、謡の一句ごとに拍子を打ち、所作を伴うらしく、《道成寺》の乱拍子謡の部分も基本的には同様である」と伝えている(『謡曲集』中、一九八六年、新潮日本古典集成)が、もともと今様の一句当りの拍子法がこの物語の特異性に合わせて特化し、現今の極限的な拍子法になったらしい(才男子あこ丸は男装をした傀儡女)。当該の『口伝集』の原文を引いておく。
松殿殿下御宅中御門東洞院信房公参りぬ。朗詠・今様うたひて夜ふくるまでぞあそびぬる。乱拍子と云今様を才男子あこ丸うたひにき。ことめづらしく皆々かん心しぬ。秘蔵むねなり。私もならひたく聞しに、早歌のさきの首とろとの拍子に合て楽の常拍子なり。乱拍子に打て一句ごとにあつるなり。そのふりおもしろくて心とび立ばかりなり。そのふり稽古ありたしと。
また、沖本幸子は乱拍子に関する数少ない研究を展開しているが、彼女によれば、乱拍子は白拍子と同じく、鼓の手に合わせて舞う舞のことを意味したとして、次のようにいう。乱拍子は拍子に合わせて足拍子を踏むところに特徴があり、当時の今様や朗詠が「拍子合わず」のゆったりと伸ばした唱歌法をとっていたのに対して、拍子に合わせて足拍子を踏むリズミカルな舞歌は当時の人々の意表をつき清新な印象を与えた。その後、乱拍子は宮廷や寺社で多様に広がったようであるが、能にも取り入れられた。しかし、「道成寺」が成立するに及んで、一転したという。「道成寺」では、白拍子舞における鼓の拍子に囃されて舞台を無言で一周するという型(セメ)が、乱拍子の鼓に乗ることによって道成寺乱拍子になったという。「白拍子の後半、セメの部分を極端にデフォルメした」のが今日の乱拍子だというのである(『乱舞の中世 白拍子・乱拍子・猿楽』、二〇一六年、吉川弘文館)。
彼女はまた、「白拍子・乱拍子の声 : 歌声の脱雅楽化をめぐって」(「日本文学」、2004年、53巻7号 online ISSN:2424-1202 )において、 白拍子も乱拍子も拍子をはっきりと刻み、その拍子に合わせて歌うことに特徴があるが、白拍子が淡々とリズムを刻んでいくのに対し、乱拍子は乱れた間合いでリズムを刻んだものであるという。ともに五節の舞が淵酔におよび乱舞となった際などに歌われて、白拍子芸を専門とする遊女が登場することによって広く愛好されていったという。平安時代には、天にすみのぼる声こそが天地感応を招くと信じられ、理想とされたが、これに対して、武家が勢力を伸長していく時代のなかで、男装をして媚態を示しながら歌い舞う遊女が演じる白拍子は「哀れ」であり、とくにその「哀し」みを帯びた声は不吉とさえいわれたという。『続古事談』巻二には、「しかるを世間に白拍子といふ舞あり。その曲を聞けば、五音の中には、これ商の音なり。この音は亡国の音なり。舞の姿を見れば、たちまはりて空を仰ぎて立てり。その姿、はなはだ物思す姿なり。詠曲、身体ともに不快の舞なり」という記述が見られる。商の音には西、秋、死のイメージがあったのである。
さらに彼女は白拍子と能との関係についてもコメントしている。「〈翁〉の全体が白拍子や乱拍子の影響を受けながら成立してきた」。翁も三番叟も父尉も白拍子を基本とし、乱拍子をつけ足して、足拍子を鳴らして終わるという形が基本であるという。平安後期から鎌倉期にかけて、それまで貴族たちによって歌われてきた、雅楽をふまえた美しく長く節を引く歌謡にたいして、今様や猿楽の流行とともに喧騒と猥雑(少なくとも当時の貴族の目にはそう映ったであろう)をともなう音楽と舞踊が都鄙の音響空間を塗り替えていった。その一番の特徴は拍子に合わせて「数える」ように舞うところにあったという。白拍子の謡の最大の特徴は、それまでの催馬楽(さいばら)や今様などが文字どおり「歌ふ」歌謡であったのに対して、「かぞふ」歌唱を取り入れたことである。拍をとりながら物事を数え上げるように歌い進めるのである(物尽くし)。「歌う」芸能から「数える」芸能に変身する時代が訪れたのである。
とりわけ、今様の流行とともに中世初期には即興的な舞、乱舞が一世を風靡した。そしてその中から男装を纏い、腰には刀を佩き、足踏を続けながら謡い舞うことを専門とする白拍子が現れ(彼らは傀儡女に由来し、その特化した形だという)、世間の耳目を驚かせたのである。乱舞の時代の幕開けである。白拍子とは本来は拍子の名称である。彼らは物尽くしの歌を得意としたらしい。拍子をとりつつ、次々を物を数えつつ謡い舞ったのであろう。「白拍子はまさに拍を「かぞふ」ようにして歌われた曲だったのだ。これが、物尽くしの、物事をかぞえあげるように並べていく歌詞にふさわしいものだった」(『乱舞の中世』)。
白拍子たちが次第に高揚する謡とともに、大地を踏み舞う姿は民衆のリズム本能を目覚めさせたのであろう。乱舞の流行とともに民衆は創造的なリズムを次々と生み出し、大地を踏み鳴らして舞ったのである。「後に至りて踏み旋る 音声妙にして耳を驚かす」(『普通唱導集』)という白拍子の舞は、リズムの世界を時代の表舞台に躍り出させたのである。じつに中世の幕開けはリズムの時代の幕開けでもあった。
それは、中世にあって、足を踏むこと、踏み鳴らすことがいかに重要だったかを物語るものである。乱舞の前の今様の時代には声、しかも、天に澄み登ってゆくような細く高い美声が重視されていた。乱舞の時代になると、天から地へと、その到達点が一八〇度転換し、しかも、強く高らかに足を踏み鳴らすことに力点が置かれていく。思えば、あらゆる価値が転倒し乱れてゆく時代のなかで、大地の荒ぶるエネルギーを自らの身体を通して転換させていくような舞が好まれたのも当然かも知れない。(『乱舞の中世』)
白拍子は世阿弥らの時代にはすでに滅んでいたが、彼らが舞った乱拍子が能の要所に決定的な影響を与えたことは疑いないであろう。白拍子はまず、能の根源でもある「翁」の誕生に深く関わっている。とくに乱拍子は翁の骨格を与えたものと思われる。翁は平安時代後期に各地に広まり(民俗芸能の翁)、各地に多くの伝承が残されているが、十二・三世紀頃に翁猿楽が形成され、これが母体となって能の翁が生まれたとされる。その過程で、白拍子・乱拍子が翁猿楽に取り入れられることによって、足踏を基本とする三番叟の舞(とくに「揉ノ段」)が生まれ、乱舞の謡や舞は滝の水の象徴的な詞章を誘い出し、「やれことうとう」という乱拍子の囃子詞に代わって「ありうどうどう」という言葉が生まれたと思われる。「安宅」のキリにおいて、弁慶が「男舞」を舞い、「鳴るは滝の水。日は照るとも絶えずとうたり」と謡うが、「翁」と共通するこの詞章は、今様の一節「鳴るは滝の水、日は照るとも、たへてとうたへ、やれことつとう」から取られたものであり、乱拍子との類縁性が明らかである。
他方で、山中玲子は、白拍子の芸能が序ノ舞の原型になったという(『能の演出』1998年、若草書房)。「序ノ舞」では、はじめの序においてシテが特殊な足遣いをするが、本来は鼓に合わせて足拍子を踏みながら舞台を一周する型のデフォルメであるという。足踏が簡略化され象徴化されたのであろう。さらにアゲワカは白拍子舞の和歌に相当しており、白拍子舞の流れを汲んでいることがうかがえるという。
また、「邯鄲」、「白髭」、「唐船」などで舞われる「楽」にも乱拍子の影響が見られる。「楽」は、ゆるやかなテンポに始まって次第にテンポが速まり、足拍子を多用する。乱拍子のセメは、「楽拍子に拍子の当たりて、早き歌なり」(『朗詠注秘抄』)とされる。それは白拍子舞の「キリ」のようなものであり、鼓と足踏みのせめぎあいが急の位となって高揚することを意味している。沖本幸子は、「卓越した鼓とせめぎあうようにして足を踏み込み舞う芸能。それが白拍子舞の醍醐味だったのだ。」(『乱舞の中世』)というが、この「醍醐味」がそのまま楽の足拍子に移り住むようになったのであろう。
さて、今日では乱拍子はあまりにも「道成寺」の舞事として定着している。その激しさが能の中にかろうじて残っていた他の乱拍子を吹き飛ばしてしまったのであろう。室町期には、金春が「道成寺」、観世が「檜垣」、宝生が「草紙洗」、金剛が「住吉詣」などで乱拍子を取り入れていたとされるが、後に各流儀とも「道成寺」で乱拍子を舞うようになったのである。
「道成寺」の前シテは白拍子である。能の物語は「道成寺縁起絵巻」(後に安珍清姫の物語として知られるようになった)を下敷きにしているから、シテは「まなごの庄司娘」の亡霊でなければならないが、白拍子に仮託されているのは、彼女が乱拍子を舞うことと無関係ではないであろう(女人禁制となった寺へ侵入するため白拍子となって社人たちを油断させる策である)。白拍子は「花のほかには松ばかり。花のほかには松ばかり。暮れそめて鐘やひびくらん。」とのどかな謡(白拍子舞か)を謡いながら舞い、一同を眠らせて、鐘に近づく。乱拍子の足遣いは鐘楼の階段を一歩ずつ登る構えにも見える。足踏をしながら次第に左へ鱗状に回るのは乱拍子舞を踏襲しているのであろう。その乱拍子は舞台芸術のいかなる舞事をも超絶して破格である。本来抑制された芸術である能がその抑制の極限にまでいたることによって、一転激越した暴発であるかのような世界(鐘入)に移行するさまに、日本的精神の極限的表現を感じるのは私だけであろうか。
2019年9月14日
采女と菟名日処女 ――能の詞花を訪ねて15
能には愛とひたむきな思いの果てに身を滅ぼした女性を描いた能がある。『采女』、『求塚』、『砧』、『浮舟』などである。 『采女』は時の帝に恋したばかりに猿沢池に身を投げた女の物語であり、『求塚』は同時に二人の男の求愛を受けて板挟みになった末に生田川に身を投げた女の物語である。 『砧』は三年におよぶ夫の無思慮な不在(単身赴任?)に疑心を抱き憂き身に苛まれ命果てた女の物語である。『浮舟』も求愛の板挟みを描いた能であるが、 シテは宇治川に入水を試みようとするが横川の僧都に助けられ、出家するという展開である。いずれも死にいたる主人公の心の動きを主題としており、 観るものはしばしその悲話に呆然とさせられるであろう。
采女は上古の時代の宮廷女官の名称である。宮中に仕え、帝の日常周辺の世話をした。その一人の采女の物語が『大和物語』第一五〇段で語られている。全文を引用しよう。
吾妹子が寝くたれ髪を猿沢の 池の玉藻と見るぞかなしき(4)
とよめる。時に帝、
猿沢の池もつらしな吾妹子が 玉藻かづかば水ぞひなまし(5)
とよみ給ひけり。さてこの池に墓せさせ給ひてなむ帰らせおはしましけるとなん。
『大和物語』第一五〇段
- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
采女のこの物語を題材とし、舞台作品とされたものが能『采女』である。南都一見の僧が春日の里に着いたところ、一人の女が木を植え、神に祈りを捧げていた。 僧が不審すると春日の地はもともと木陰のない山里であったが、人々が営々と木を植えることによって、このような木深い森になったのだと語り、さらに猿沢の池に案内した。 そして昔の悲話を語るのであった。
- シテ
初めは叡慮にかない御恵みあさからず。
ほどなくおぼしめしすてけるを。
及ばずながらうらみまいらせ。
この池に身を投げむなしくなりしなり。
- ワキ
みかどあわれとおぼしめし。この猿沢にみ幸なって。
- シテ
- ワキ
- シテ
ひすいのかんざし 嬋娟 の鬢。(1)
- ワキ
- シテ
- ワキ
- シテワキ
- 地
ねくたれがみを猿沢の。
池の玉藻と。みるぞ悲しきと叡慮にかけし御情。
かたじけなや下として。君をうらみしはかなさは。
たとえば及びなき。水の月とる.猿沢の。
いける身とおぼすなよ。
われは采女の幽霊とて。
池水に入りにけり.池水の底に入りにけり。
(1)つややかで美しい鬢の毛
(2)三日月のような眉
私には、采女の美しく長い髪と鮮やかな裳裾が池の玉藻に絡んで広がる光景は、オフィーリアが狂気の果てに流れに落ち、 「裳裾は大きく広がって しばらくは人魚のように川面に浮かびながら 古い歌をきれぎれに口ずさんでいました」という光景と重なって、二重写しになる。
白い葉裏を流れに映しているところに、
オフィーリアがきました、キンポウゲ、イラクサ、
ヒナギク、それに口さがない羊飼いは卑しい名で呼び、
清純な乙女たちは死人の指と名づけている
紫蘭の花などを編み合わせた花冠を手にして、
あの子がしだれ柳の枝にその花冠をかけようと
よじ登ったとたんに、つれない枝は一瞬にして折れ、
あの子は花を抱いたまま泣きさざめく流れに
まっさかさま。裳裾は大きく広がって
しばらくは人魚のように川面に浮かびながら
古い歌をきれぎれに口ずさんでいました、
まるでわが身に迫る死を知らぬげに、あるいは
水の中に生まれ、水のなかで育つもののように。
だがそれもわずかなあいだ、身につけた服は
水をふくんで重くなり、あわれにもその
美しい歌声をもぎとって、川底の泥のなかへ
引きずりこんでいきました。
『ハムレット』第四幕第七場、小田島雄志訳、白水uブックス
他方で、能『求塚』は生田川に散った菟名日処女の物語である。神戸の街には菟名日処女にまつわる三つの塚がある。 処女塚 、 東求女塚 、西求女塚であり、本来は4,5世紀の古墳であった。真ん中の処女塚を挟んで二つの塚が向かい合っていることから、 いつの頃からか菟名日処女の物語が生まれたと推測される。そして、万葉の歌人たちによって美しい悲話が歌われたのであった。 『万葉集』には三人の歌人によって菟名日処女の物語が歌われているが、ここでは大伴家持の歌(四二一一・四二一二)を引いておこう。 墓に生え出た木を処女の黄楊小櫛が生い出で枝を伸ばしたものと見立てた歌である。
処女墓の歌に追同する一首
古に ありけるわざの くすばしき 事と言ひ継ぐ 千沼壮士 菟原壮士 のうつせみの 名を争ふと たまきはる 命も捨てて 争ひに 妻問ひしける 処女らが 聞けば悲しき春花の にほへ栄えて 秋の葉の にほひに照れる あたらしき 身の盛りすら ますらをの 言 いたはしみ 父母に 申し別れて 家離り 海辺に出で立ち 朝夕に 満ち来る潮の 八重波に なびく玉藻の 節の間も 惜しき命を 露霜の 過ぎましにけれ 奥つ城を ここと定めて 後の世の 聞き継ぐ人も いや遠に 偲ひにせよと 黄楊小櫛 然 刺しけらし 生ひてなびけり
* 昔あったことで、珍しい話だと言い伝えられているが、千沼壮士と菟原壮士が人の世の名誉にかけ、命を捨てて争ったという処女の話を聞けば哀れだ。 春の花のように美しく香り、秋の紅葉のように赤く映える惜しむべき身の盛りに、二人の丈夫の言葉を気の毒に思い、父母に別れを告げて、 家を離れ、海辺に佇み、朝夕に満ち来る潮の波になびく玉藻の節のように短い惜しい命を、露霜のように消え去らせてしまった。その墓をここと定め、 後の世に聞き伝える人も末永く偲び草にせよと、形見の柘植の櫛をさしておいたのだろうか、黄楊の木が生えて茂っている。
菟名日処女の後のしるしとした黄楊小櫛が木となって生え、枝をなびかせていることだ。
能『求塚』は、菟名日処女の霊が旅の僧の前に現れ、地獄の苦患に苛まれていると訴える筋書きである。 都一見の僧が西国より生田の里に来てみれば、若菜を摘む女たちに出逢った。舞台では里女(シテとツレ)の長大な若菜摘みの歌が繰り広げられる。
僧が求塚の所在を聞けば、里女たちは知らないと答え、なおしばし菜摘歌を歌いながら若菜を摘んでいたが、 一人を残して帰ってしまった(『敦盛』や『鞍馬天狗』と同趣)。僧が訝っていると、求塚に案内するという。そして求塚の故事について語りだした。
- シテ
さらば語って聞かせ申し候べし。昔この所に菟名日乙女のありしに。またその頃 小竹田男 。 血沼 の 大丈夫 と申しし者。かの菟名日に心をかけ。同じ日の同じ時に。わりなき思いの玉章を贈る。 彼の女思うよう。一人になびかば一人の恨み深かるべしと。左右なう靡くこともなかりしが。あの生田川の水鳥をさえ。 二人の矢先もろともに。一つの翅にあたりしかば。その時わらわ思うよう。無慚やなさしも契りは深緑。水鳥までもわれ故に。 さこそ命は鴛鴦の。番い去りにし哀れさよ。住みわびつ。わが身捨ててん津の国の。生田の川は.名のみなりけりと。
- 地
菟名日処女の物語は『源氏物語』にも影響を与えている。物語の最終部、宇治十帖では浮舟の物語が語られるが、 浮舟が二人の男(薫と匂の宮)の板挟みにあって次第に窮地に陥り、自死の坂を転がり落ちるさまが長大な叙事詩として語られるのである。
(1)子どもっぽくておっとりしてなよなよと見えるが、
(2)少々恐ろしく見えること
森鴎外もまた『生田川』という短編の戯曲を書いている。
- 処女
- 母
- 処女
『生田川』、1910年、『鴎外全集』第6巻、岩波書店
鴎外は事態をディレンマと捉えているのである。「絶望のディレンマ」に陥ったとき、処女はそれを神の試練と受けとめて、 死を受け入れざるを得なくなったというのである。人間には「人間の力の及ばない事」が訪れることがあり、 そのときにはその運命に従わざるをえないという事情を菟名日処女は受け入れたのだと、鴎外は解釈したのであろう。
さて、能の後半は死を選んだ処女が地獄に落とされ、あらゆる責め苦に苦しむさまが描かれる。その詞章は激烈であり、 私たちはあまりの凄惨さに言葉を失うが、能にはことさら好んでこのような「残虐シーン」が描かれることがあるのだ。 ところが抽象度の高い能の舞台では、そのようなシーンが蠟化され象徴化されて、心を打つ美しい場面に変容されるから不思議である。
- シテ
恐ろしやおことは誰そ。なに 小竹田 男の亡心とや。また此方なるは 血沼 の大丈夫。 左右の手をとって。来れ来れと責むれども。三界火宅のすみかをば。何と力に.出づべきぞ。また恐ろしや飛魄飛び去り目の前に。 来るを見れば鴛鴦の。鉄鳥となって 黒鉄 の。 嘴足 剣の如くなるが。頭をつつき髄を喰う。 こはそもわらわがなせる科かや。恨めしや。のう御僧この苦しみをば。何とか助け給うべき。
- ワキ
- シテ
- ワキ
- シテ
- ワキ
- シテ
- ワキ
- シテ
- ワキ
- シテ
- 地
進退きわまって死を選んだ女性を地獄に落とし責め苦を及ぼすさまを描くことに、私たちは理解に苦しむであろう。これを時代相の違いと捉える解釈があるが、それでは時代と文芸思潮との緊張関係を見失うことになるだろう。中世の武家の支配と戦乱の時代には根本的な人間理解が崩落することがあるのだ。暗黒の時代状況のなかでは暗黒の人間像が暗躍するのである。とりわけ弱者である女性はいっそうの窮地へと追いやられるのだ(女人不浄や女人禁制など)。『求塚』はそのような暗黒性をそのまま舞台に俎上させ、それでもその暗黒を美的に彫琢しようとする暗い時代の芸術であることを象徴しているのではないだろうか。
2019年8月15日
遊女と普賢菩薩 ――能の詞花を訪ねて14
「江口」は、西行が江口の遊女妙と一夜の宿をめぐって交わした歌を題材として作られた能である。当の歌は『山歌集』や『撰集抄』等にも収められているが、ここでは『新古今和歌集』巻第十から引用してみよう。
天王寺へ詣で侍りけるに、にはかに雨の降りければ、江口に宿を借りけるに、
貸し侍らざりければ、よみ侍りける 西行法師
世の中をいとふまでこそ難からめ 仮の宿をも惜しむ君かな
返し 遊女妙
世をいとふ人とし聞けば仮の宿に 心とむなと思ふばかりぞ
江口は古来からの淀川下流の交通の要所であり、都から鳥羽に下り、宇治川、桂川、木津川が合流する淀津から舟で淀川を下ればほぼ一日の行程の所にある。西行は、天王寺への旅の途中、江口でにわか雨にあい、宿を借りようとしたが、宿の主に断られた。そこで、「世の中をいとう(世を捨てて出家する)ことはだれにも簡単にできることではないが、かりそめの宿を貸すことさえ惜しむ(いとう)人もいるものだ」と戯れ歌をつぶやいたところ、主の女が「出家された方がかりそめの遊女の宿に執着なさらないでと思うばかりです」と返したのである。遊女に一本取られたというところだが、ここには「世をいとう」と「仮の宿」という言葉が二つの歌に重ねられている。厭離穢土が主題なのである。女が僧である西行に出家の心を諭すという逆説が歌われているのである。そこには、世をいとうというきびしい態度が軽妙なやり取りによって温められ洒脱化されている。それどころか、世をいとうと言いながら世の機微を楽しむところに歌人としての精髄がある。西行はこのような軽められた心にむしろ歌人僧の心が宿ると見届けたのであろう。
- *
西行の歌が機縁となって物語が進行する能には、本曲の他に『雨月』、『西行桜』、『遊行柳』がある。しかし、ここで主題とされるのはむしろ遊女妙の歌であり、彼女の歌が能の内容に深く関わり、さらにそこに法華経の教えが浸透しているという点で、『江口』には他の能に見られない個性がある。なにしろ曲の全編が仏の教えを舞台に美しく描きあげるという趣向を醸し出しており、終曲では遊女が普賢菩薩であることが示されるのである。
それにしてもなぜ西行なのだろうか。能作者の時代には西行はすでに伝説化した人物であり、『撰集抄』なども親しまれていたが、自然と人心とをこの上なく響鳴させ、日本人の美的心性を研ぎ澄ませた歌人であってみれば、この問いはむしろ愚問かもしれない。しかし本曲では
僧
西行がより深く関わる。しかも僧侶が遊女から仏の教えを説かれるのであるから、よくよく特異である(他に、老女小町が高野山の僧を説き伏せた『卒都婆小町』がある)。ここには、歌によって「普賢菩薩勧発品」の教えを映現させようとする世阿弥の工夫が働いている。「普賢菩薩勧発品」は『法華経』二十八品の最後の経典であるが、法華経は最後にこの最高の経典を「聴聞し、書写し、記憶し、読誦する」ことを勧めるために普賢菩薩を登場させたのである。普賢菩薩は釈迦三尊の一で文殊菩薩とともに釈迦如来の脇侍である。文殊菩薩が智慧の菩薩であるのに対し、普賢菩薩は行願の菩薩であり、法華経を実践し、その教えを守護する。ここでは法華の行を勧め、法華経を守護し、その行者を讃える「普賢行」が説かれたのである。普賢菩薩は、法華経の行者がいれば「六牙の白象」に乗ってその者に赴き鼓舞し讃えるという。世阿弥はこの菩薩の仮の姿を遊女に考案したのである(日本ではとくに女人成仏を説く仏として平安時代から女性の信仰を集めたことが、普賢菩薩を遊女として表す機縁となったのであろう)。
上掲の贈答歌は、人間の曇らされたままの状態と懺悔を経て真如の月に照らされた状態との交歓を歌っている。「普賢菩薩勧発品」の教えを詳説した『観普賢菩薩行法経』によれば、心が真如の月に照らされれば、「目を閉ずれば則ち見、目を開けば則ち失う」という諦観が可能になるという。肉眼の目で見れば遊女であるが、心の目で見れば白象に乗った普賢菩薩が現れるのである。また、観普賢経は法華経の行として懺悔を説いている。懺悔とは、煩悩の迷いに曇らされ盲目になった心を解脱させ(六根清浄)、妄想の心を転倒させることである。「懺悔清浄なること已りなば、普賢菩薩また更に現前して行・住・坐・臥に其の側を離れず」。それゆえ、普賢行とは懺悔を経て清浄に向かう行であり、その行を行うものは普賢菩薩に相見えるのである。観普賢経は「至心に六情根を懺悔すべし」と説く。懺悔によって心が清浄になれば、今までの欲望に曇らされた視野が明るい光明の世界に転ずる。懺悔が十全なものとなり、心が清浄の世界に住すれば、それは大懺悔と云われる。変化するものにとらわれず、不変のものが心に念じられており、あらゆる煩悩が滅しさられた心境である。このことが遊女妙の歌では「仮の宿に心とむな」と歌われたのである。
植野慶子によれば(「『江口』の遊女と普賢菩薩との同一性:女人救済の問題を中心に(後編)」『日本文學誌要』48、1993、法政大学)、『江口』には観普賢菩薩行法経の教えを受け継いだ四つの救済の思想が、盛りこまれているという。第一は、「シテによるワキの救済」であり、亡霊による現身人の救済である。第二は「普賢菩薩の衆生教化」であるが、『江口』との関わりではこの衆生はさしあたってこの能を観る観客だという。この能の背景というべき「月光に照らされた水面」が舞台を清浄の域に変貌させ、観るものの心をも「真如の月」のごとく清浄にしている。観客はこのような情景のなかで、遊女こと普賢菩薩の教えを身に浸透させるのである。第三は「遊女による僧の救済」であり遊女が迷える僧を救済する。この僧とは凡俗の迷いから醒めない旅僧であるが、西行でもあり、世捨て人を自認する仏門の徒一般でもあろう。第四は「女人による男性の救済」であり、もとより罪深く成仏が困難とされた女人がかえって男の迷妄を晴らすのである。このような救済論は通常の救済観念を逆転させたとらえ方であり慧眼であるが、一と三と四はほぼ共通であるから、『江口』の救済ドラマは普賢菩薩による「女人成仏」と「衆生の迷妄からの解放」という二つの主題を追うものと理解したほうが適切であろう。
つぎに、『江口』における懺悔道のすすめをクセとキリの詞章から見てみよう。
西国行脚の僧が江口の里に立ち寄り、江口の君の跡で西行の歌を口ずさんでいると、いずこからともなく女が現れ、「仮の宿をも惜しむ君かな」という歌のことばに不満の意を表した。そして返歌の真意を訴えるかとみるうちに、姿はかげろい、江口の君の幽霊ぞという声を残して消えてしまった。僧がその跡を弔おうとしていると、月の澄みわたる川面に川舟が現れ、遊女たちの舟遊びの姿が浮かび上がった。舞台には(今日では多くは橋掛りに)屋形舟の作り物が出され、三人の遊女(後シテ江口の君とツレの侍女二人)が舟に並び立つ。シテは小面、唐織壺折に緋大口、二人のツレは連面、唐織着流し(一人は櫂竿をもち右肩脱ぐ)という出立であり、舟歌を謡うのであった。三人が舟に並ぶ姿は鮮やかで美しい。
遊女は無常と有為転変の象徴である。ひとときもて遊ばれ、あしたには忘れられ隔てられる「川竹の流れの女」をのがれることができない。そのような「河逍遥の月の夜舟」に明かす日々を生きる身であるであるからこそ、彼女たちは「月は昔にかわらめや」と謡うことができたのであろう。有為転変の無常が、真如の月のごとく昔変わらぬ悠久の今であることを遊女たちは僧に諭すのである。無常と今とが一如であること、「流れ」に遊ぶことが生の常態であることを「江口」は見抜いている。人にあわれということがあるなら、この江口の遊女の「うつろう色」の生こそがそれであろうが、「げにやみな人は六塵の境に迷い、六根の罪を作る」という思いがそこにはある。
紅花の春のあした。
紅錦繍
の山.
粧いをなすと見えしも。夕べの風に誘われ.
紅葉の秋の夕べ。
黄纐纈
の林。
色を含むといえども. あしたの霜にうつろう。
松風羅月に. ことばをかわす賓客も。さつて来たる事もなく。
翠帳紅閨に。枕をならべし妹背もいつの間にかは隔つらん。
およそ心なき草木。
情けある人倫。いずれ哀れをのがるべき.
かくは思い知りながら。
ある時は色に染み. 貪着の思い浅からず。
またある時は声を聞き. 愛執の心いと深き.
心に思い口にいう.
妄染
の縁となるものを。
げにやみな人は. 六塵の境に迷い. 六根の罪を作る事も。
見る事きく事に。迷う心なるべし。
- *
もみじの秋には黄色の絞り染めのように林は染めあげられるが、朝の霜に色あせてしまう。(1)
松風や蔦葛にさす月影のもとで語り合った客人も去ったままふたたび来ることなく美しく飾った寝室で契りを交わした恋人たちもいつの間にか疎遠になる。(2)
心なき草木も、情ある人間も、どのみち悲しい運命をのがれることはできない。
そんなことはよく分かっていながら、ときには容色に溺れ色欲を貪り、
またあるときは美声を聞いて愛着の思いを深くし、心にもないことを口にして、妄舌(?)の戒めを破ることになるのだ。
じつに人間はみな、六塵(色声香味触法の汚染)の世界にさまよい、六根(眼耳鼻口身意)の罪を作るのも、
見ることや聞くことからくる迷いの心から起こることだ。
(1)『和漢朗詠集』小野篁
(2)『和漢朗詠集』遊女
序ノ舞のあとのキリの詞章も無情諦観を説くが、クセが「理論編」であるのに対し、キリは「生活編」といったところか。「仮の宿に心とむな」と説く。
- シテ
- 地
- シテ
- 地
- シテ
- 地
- シテ
- 地
- シテ
- 地
- *
この真如の世界といえども縁にしたがって様々な波(善悪苦楽)となって砕けない日は一日たりともないのだ。
波が立つのはこの仮の世に心を留めるからだ。
そうだ、執着しなければ世の辛さもないのだ。
人を慕うこともせず、待ちわびることもせず、別れをなげくこともするまい。
花鳥風月に心を奪われることもつまらないことだ。
思えば仮の世に心を留めるなと、私は人を諌めたのだった。
さあ、もう帰りましょうというかと見れば、遊女は普賢菩薩に姿を変え、
遊女の乗っていた舟は白象となり、白光に包まれ、白雲にゆらりと乗って
西の空に去ってしまわれたのはまことにありがたいことであった。
キリの終わりで、帰ろうとする遊女は突然姿を変え、普賢菩薩となって、白象に乗り、西の空に去っていった、と謡われる。遊女は普賢菩薩の仮の姿だったのだ。これは何を語っているのだろうか。『撰集抄』に生身の普賢菩薩を拝みたいと思っていた性空が「室の長者を見よ」というお告げにしたがって、目を閉じて心を静めると白象に乗った普賢菩薩が現れ、目を開くと遊女だった、という説話があり、世阿弥はこの『撰集抄』の説話をヒントにしたのであろう。江口の遊女こと普賢菩薩が説くのは、執着するなかれの一語に尽きる。何人にも何事にもとらわれない心を知ることが人生の大悟であった。この大悟にいたったとき、もはや遊女ではなく、仮の世にとどまることもなく、白象にまたがった普賢菩薩となって西方に帰ることができるのだ。白象は白雲であり、白光でもあろう。白雲は無の遊境でもあろう。
2019年7月17日
星の静寂 ――能の詞花を訪ねて13
「関寺小町」は能の世界における最高秘曲だとされる。それはシテである小野小町が百歳の老女であり、百歳の心境を表す芸を演じきることが至難であるから、と云われることが一般である。当時百歳を迎えることが稀有であったことを認めるとしても、しかしそれだけではいささか説得力に欠けるであろう。私には、この能が表そうとしているものが、一人の人間に与えられた可能な限りの長大な時間と有為転変をくぐり抜けたとき、その人間の前に何が映現するのかという根源的な問題であったからではないかと思われる。
いわゆる「三老女」には共通する特徴があるように思われる。それは老女の心を映し出す或る「媒体」が一曲のテーマになっていることである。「伯母捨」のそれは月であり、「桧垣」のそれは水であろう。そして「関寺小町」のそれは星である。能は最後に星にたどりつき星になるのだ。しかし、なぜ星でなければならなかったのか。そして、月と水と星と、これらは一体何を表しているのだろうか。
これら三曲は、心の最後の拠り処を、或る格別の「媒体」に身を寄せることによって象徴的に描き出そうとしているように思われる。これらの「寄る辺」となる「媒体」とは、人の心が彷徨して辿りついた或る境囲、いわば心が安堵する住まいであろう。私たちはそれをヘーゲルの表現にしたがって「エレメント Element」と呼ぶことにしよう。「エレメント」とは世界を包み込む「根本物質」のようなものであり、生命体にとっては、それなしでは生きることのできない不可欠の存在をいう。ヘーゲルは「魚にとってのエレメントは水である」と分かりやすく譬えている。それでは人間にとってのエレメントは何であろうか。呼吸する人間にとっては空気であろう。しかし、音楽家にとっては音であろうし、それも美しい音であろう。研究者にとってそれは真理であるべきであろう。守銭奴にとっては金であるに違いない。さらにいえば、「負修羅」の武将にとってのエレメントは心ならずも「敗北」ということなのかも知れない。エレメントは「境―位」、すなわちそのものが生きる本質と位階を表す存在なのである。エレメントは生きる者にとっての基礎代謝となる糧であると同時に、仰ぎ見られる理想でもある。それ故、私たちがおのれのエレメントを問うことは生の意味と尊厳を尋ねることほどの意味があるのだ。
さて、「関寺」に示されたエレメントは星である。この能は「星の能」なのだ。舞台は七夕の夜である。関寺では「星のまつり」が行われ、小町は住僧に連れられてまつりの場に行くのである。星がしずかに地上の人々の賑わいを見下ろしている。なぜ、作者は星に人の生の窮境を見ようとしたのであろうか。星は人間にとってどのような境位を表すのであろうか。
この能では、さしたる事件は何も発生しない(あえていえば、小町が関寺の住僧に正体を明かされたことくらいである)。「伯母捨」や「桧垣」に見られる深く透明感のある抒情や「わび」を感じさせる幽玄の境地も、特段に感じられるわけではない。生の温もりのような暖かみが仄かに漂うほかは、なにもないのである。時は七夕の夜であり、寺には「星のまつり」の賑わいがあり、舞台には稚児が登場し和みの風が香っている。むしろ静謐の穏やかさといったものが全曲を貫いているというべきであろう。
小町は関寺の近くにひそかに残された生を送っていた。彼女が歌人であることが土地の人々にそれとなく知られていたのであろう。七夕の夜、関寺の住僧は稚児たちを伴って、歌の話を聞かせてもらおうと彼女の庵を訪れたのだった。
これは江州関寺の住侶にて候。
さてもこの山陰にわら屋しつらいて老女の候が。
歌などをも読み候ほどに。
歌の不審のため。児達をおん伴申し。
ただいま老女の私宅に急ぎ候。
小町は藁屋で老残を託っていたが、稚児たちに歌のことを話してほしいとの僧の言葉に思わず心がほころんだ。僧の巧みな問いかけに、小町も口元が解け歌の由来を語るうちに、自らのことをふと口にして、僧に素性を知られてしまうのであった。歌が小町の心を開く機縁となったのである。
しかし、心が和んだのも束の間、おのれが詠んだ歌が自らの心を深い憂愁の内へとふたたび連れ戻した。今度は、歌が彼女の人生流転の悲哀の記憶を呼び起こしたのである。次のクセ(部分)は百歳の小町の心境を歌った絶唱の詞章である。
あるはなく。なきは数添う世の中に。
あわれいずれの日まで嘆かん(1)と詠ぜしこともわれながら。
いつまで草(2)の花散じ。葉落ちても残りけるは露の命なりけるぞ。
恋しの昔や。偲ばしの古えの身やと。
思いし時だにも。また古事になりゆく身の。
せめて今はまた。初めの老いぞ悲しき。(3)
・・・
関寺の鐘の声。
諸行無常と聞くなれども。老耳には益もなし。
逢坂の山風の。是生滅法の理をも得ばこそ。
飛花落葉のおりおりは。好ける道とて草の戸に。
硯をならしつつ。筆を染めて藻塩草。
書くや言の葉もかれがれに. あわれなるようにて強からず.
強からぬは。女の歌なれば。
いとどしく老いの身の. 弱りゆく果てぞ悲しき
(1)あるはなくなきは数添ふ世の中に あはれいづれの日まで歎かん
『新古今集』に収められた小町の歌である。元気だった人は亡くなり、
この世を去った人ばかり増えていくはかない世の中に、わたしもいつまで嘆いておられようか。
(2)キヅタの異名。私もいつまで永らえるだろう、と言いかけられている。
(3)昔の身が恋しいとと嘆いたときももう昔話になってしまって、今ではせいぜい嘆いたその頃が恋しい。
小町は独り歌のみを友として生きていたのである。彼女を悲哀の回想に誘った歌として次の歌が作中にあげられている。
わびぬれば身をうき草の根を絶えて 誘ふ水あらばいなむとぞ思ふ (古今集)
色見えで移ろふものは世の中の 人の心の花にぞありける (古今集)
思ひつつ寝ればや人の見えつらむ 夢と知りせば覚めざらましを (古今集)
これらの歌は小町の秀歌であるが、いずれも彼女自身の人生の境遇と変転を嘆いた歌である。自らのこれらの歌に誘われて、彼女は深い追憶のなかに沈んでいく。歌は折々に詠まれるものであるが、人生の回想を呼び起こす縁でもあることをこの作者は洞察しているのであろう。ここにあげられた歌は、小町の人生の折節を表しているが、およそ人の生の流浪のあはれを美しく(女の弱い流によって)表したものでもある。世阿弥はここでも歌が生の里程を表す媒体であることを示そうとしているのであろう。小町の心の在処はいつも歌だったのである。その意味では、この曲が示す生のエレメントは「歌と星」と言うべきであろう。
小町の人生そのものが「誘ふ水あらばいなむとぞ思ふ」という、誘発するものに誘われ、流れるものに身を任せようとする「流れる生」だったのであろう。能に表れた小町は、歌会では黒主の不正を暴き、卒塔婆に腰掛けては咎めた僧を問答によって打ち負かし、筆も持てぬ身となっても「鸚鵡返し」の技法で帝に返歌するという才女ぶりを発揮するが、それでも彼女の生涯は流転の生であった。実際、小町には流浪の説話が数多く残されているが、彼女の歌そのものが流浪的な余韻を残すものが多いということからも窺えよう。
花の色は移りにけりないたづらに わが身よにふるながめせしまに
(古今集、百人一首)
しかし、これらの歌が私たちの心を打つのは、私たちもまた「誘ふみずあらばいなむ」という流転の生を免れることができないという思いを身の内に抱くからであろう。人は誘発されるものに自ずと身を寄せ、われしらず流されていく。自らおのれの生を自由に采配し構成するということは転倒した夢想に過ぎないということを、小町の歌はむしろ告げようとしていたと思われるのである。
さて、僧は小町を関寺の「星のまつり」に誘う。星の下に集う人々の賑わいとそれを包む星辰の静寂が小町の心を幾分融かしたのであろう。しかも今宵は二星の逢瀬のときである。星に祝福の祈りを捧げるために人々は集う。そしてこの天の慶事のもとで人の歓喜も醸成され、集った人々の交歓も広がる。それでも賑わいのうちに星は静かに西に流れていく。そして、稚児たちの踏舞に誘われるかのように、小町はよろよろと立ち上がり、「老女の舞」を舞う。舞は微かな生の残照を表すかのように、しずかに、ゆったりと立ち上がり、そして次第に大地の深みに沈んでいく。舞がそのまま無になる。
「老女の舞」は「さす袖も手忘れ裳裾も足弱く漂う」というように、すべてを放念して、いわば「星になって」舞うのである。そこにはいっさいの作為が消尽している。世阿弥のいうように、「ただ、優しくて、理のすなはちに聞ゆるやうならんずる、詩歌の言葉を取るべし。優しき言葉を振りに合わすれば、ふしぎに、人体も幽玄の風情になる物也」。(『風姿花伝』)
私の恩師である金春信高は、彼の舞台生活の最後に「関寺小町」を舞ったが、次のような言葉を残している。
老女の世界というのは、無の世界に通じるんです。やる気に満ち、芸を見せようと見せようとすると、そこに卑しさが出てしまう。見せようとしないで、どうやって演じるのか。理屈では合点がいかないかもしれませんが、曲中の人物になりきり、虚心坦懐に決められた謡を謡い、型をし、舞を舞う。それが観客には素直に伝わるんです。位を重視し、ゆっくり動くというのは、それだけにごまかし難いのです。 (『花の翳』 2002年、岩波書店)
「関寺」は無の世界だという。この無は、すべてが過ぎ去って、いまやおのれも過ぎ去ろうとしていることを淡然と見送るという無であろう。諸行無常も過ぎ去り、老いの嘆きも過ぎ去る。そして、夜が明けて東雲になる頃一つの存在が無となる。星のように。生の終わりとは夜がいつしか開けることなのであろうか。されば星は生の流転の同伴者にちがいない。星が西に流れるように、生も西に流れ流れて、山の端に沈む。
百年は。花に馴れこし。胡蝶の舞。
あわれなりあわれなり。老木の花の枝。
さす袖も手忘れ。
もすそも足弱く。
ただよう波の。
立ち舞う袂も。翻せども。
昔に返る。袖はあらばこそ。
あら恋しの。古えやな。
さるほどにさるほどに。初秋の短か夜。
はや明け方の。関寺の鐘。
鳥もしきりに。告げ渡る東雲の。
あさまにもならば。はづかしの杜の
はづかしの杜の。木隠れもよもあらじ。
いとま申して帰るとて。杖にすがりてよろよろと。
もとの藁屋に帰りけり。
百年の姥と聞こえしは。小野が果ての名なりけり。
小町が果ての名なりけり。
2019年6月17日
『砧』 絶望の哀歌 ――能の詞花を訪ねて12
「砧」は不思議な曲である。物語の全体に暗く深い霧が流れており、シテ(芦屋の某の妻)の心は闇のなかを揺れ動いて像を結ばないようにみえる。しかし他方で、その心は自らが打つ砧の音のようにどこまでも澄み渡り、人の心を射抜くようである。この曲の「主題」は何であろうか。一般には夫の不実を嘆いた妻の怨恨を描いた曲と理解されている。しかし、それだけでは「砧」を理解するには足りない。晩年の世阿弥の透徹した、冷厳な人間洞察がこの作品を貫いていることを知らなければならない。
世阿弥自身がこの曲について語っていることは意味深長である。次のよく知られた文章は世阿弥の言葉を次男元能が書き記した『申楽談儀』の一節である。
静成し夜、砧の能の節を聞しに、かやうの能の味はひは、末の世に知人有まじければ、書き置くも物くさき由、物語せられし也。しかれば、無上無味のみなる所は、あじはふことならず。又、書き載せんとすれ共、更に其言葉なし。位上らば自然に悟るべき事とうけ給はれば、聞書にも及ばず。
* ある静かな夜、父に砧の能の音曲について伺ったところ、このような能の味わいは、この末世の世に理解する人もいないので、書き記しておくことも気が進まないことだと語られたことがあった。それゆえ、そのひたすら「無上無味」である境地を味わうこともできない。また、それをここに書き記そうとしても、合う言葉も見つからない。能が上達すれば自然にわかるようになるだろう、と云われたので、ここではその内容を記すこともできない。
世阿弥自身のこのような言葉にもかかわらず、この曲の詞章、節付けともまったく卓越しており、これに勝る味わいを持つ能は他にみられないと思われるほどである。妻の心にあふれる心情を吐露する謡は激しく、悲しく、やさしく響き、その言葉には幾重もの秘められた思いが襞のように折り込まれている。妻の心を覆っているものは深い深い絶望なのである。それでも一縷の希望がほの見えるあいだは命の炎はまだ消えない。その炎がふと吹き消されるとき、妻はもはや生きることができないのだ。
「砧」の妻の絶望は、キルケゴールが解く絶望概念の謎解きに通じるものがある。
絶望とはまさに自己を食い尽くすことにほかならず、しかも自らの欲することをなしえない無力な自己食尽なのだ。…この無力さは絶望のなかの冷たい炎であり、絶えまなく内に向かって食い入り、だんだん深く自己食尽のなかに食い込んでいく苛責なのだ。
(『死に至る病』枡田啓三郎訳、世界の名著51)
絶望の状態とは自己が末路に向かう途上の様態である。命の火種が冷たい風によって弱められていくのである。キルケゴールはこの衰滅化を自己食尽と名づけた。厳しい言葉である。芦屋の某の妻は自ら選びとったかのように衰滅の坂を滑り落ちていく。彼女は「袖にあまれる涙の雨の。晴れ間まれなる心かな。」という日々を送っていた。ところが、都より送り返されてきた夕霧の顔を見るや、暴発した心は不実の夫を責めるのではなく、自己を苛めるのである。「げにや偽の。なき世なりせばいかばかり。人の言の葉嬉しからん。愚の心やな。愚なりける頼みかな。」 必ず年の暮れには帰るという夫の言葉にも、喜ぶのではなくそれが信じられず、おのれがかすかな希望を抱いていたことへの自戒の念に切り替わるのである。そして年の暮れにも帰ることができなくなったという重ねての便りに、妻の心はもはや耐えることができなかった。「思わじと思う心も弱るかな。声もかれ野の虫の音の。みだるる草の花心。風狂じたるここちして。病の床にふし沈み。ついにむなしくなりにけり。」
絶望の状態にある妻は、一重に夫との再会の場面に心を奪われていた。彼女の心の全体はこの空想によって隙間なく占められていたのである。ところが、都からの重ねての便りはこの妻に最後の躓きを与えた。一体、躓きとは何であろうか? キルケゴールはいう。
つまずきとは不幸な驚嘆である。それゆえに、それは嫉妬に似通っている、しかしそれは妬む者自身に向かう嫉妬である、もっと厳密にいうなら、もっとも意地悪く自分自身に立ち向かう嫉妬である。(同書)
不幸な便りは、相手方への憎しみをまねくというより、おのれへの無慈悲な責めを招くのである。不幸を受け取ったおのれが許せないのである。キルケゴールはこのような状態を「抽象的な孤立化」と名づけた。
ついには自己全体が想像的となりかねなくなる。この想像化は、人間が想像的なもののなかへ飛び込むという比較的能動的な形でおこなわれる場合と、想像的なものに引きずり込まれるという比較的受動的な場合とがあるが、どちらの場合にも、その責任は自己にある。その場合、…自己はだんだんと遠く自己から離れていって、抽象的な無限化のうちに、あるいは抽象的な孤立化のうちに、想像的な生き方をするのである。(同書)
人生のすべてが想像の一点に収斂すること、これは人生に最大の喜びを与えることもあるが、その生命を最大の危険にさらすことでもあるのだ。キルケゴールも語らなかったことであるが、このような状態にあるとき、心には烈しい苛立ちのうねりが押し寄せるのである。心の苛立ちは自らをいたるところ刺し続け、内なる出血を招く。それは地獄の責め苦のごとくであるが、自らの生きる力を奪いさる決定的な自己刺殺ともいうべき働きである。それゆえ、苛立ちは何かある行為へと昇華されなければきわめて危険である。この行為が「可能性」という代償行為であり、ある特定の場へとおのれを振り向けることよって苛立つ心を転化させ鎮める働きである。可能性が与えられれば、絶望者は息を吹き返し、生き返ることができる。可能性なしでは人は呼吸することさえできない。可能性は追いつめられた人間にとって唯一最良のレメディー(治療法)なのである。彼女は、ふと聞こえてきた砧を打つ音がそれであることを、一瞬にして悟ったのである。
シテ あら不思議や。なにやらんあなたに当つて。物うつ音の聞こえ候。あれは何にてあるぞ。
ツレ あれは里人の砧うつ音にて候。
さて、「砧」はこのような経緯を孕みつつ、「恨みの砧」の物語へと転調する。その転調には、当時の人々に共有されていた擣衣の抒情を謳った歌が背景にあった。
たがためにいかにうてばかから衣 千たび八千たび声のうらむる(千載和歌集 藤原基俊)
秋とだにわすれんと思ふ月かげを さもあやにくにうつ衣かな (新古今和歌集 定家)
砧を打つ音には「うらむる」とか「あやにく」という負の響きがこもっていたのである。擣衣の響きは晩秋の夜の風情と一体である。その音は夜寒の風に乗ってどこまでも伝わる。妻はそこに「
音信
」を託した。音の伝信は「風のイメージ」と重なる。砧の音を伝えるのは風である。風は妻から発せられた音信の運び手である。はらはらと袖に落ちる「松の声」が「音信」に機縁を与えている。衣に触れるかすかな松葉の音が擣衣の音の予兆なのである。そして妻の打つ砧の音は秋の夜風に乗ってどこまでもどこまでも伝わっていく(と妻は信じている)。相良亨は、砧を打つことによって「思ひぞ慰む」と一縷の希望を託したことに、この能の美的意味があるという。「慰め」が最後の自己救済としての働きをもつことを世阿弥はよく知っていたのである。砧を打たなければ、妻の心は崩れ落ちていたかもしれないのだ。「砧の音は、はげしく淋しいもので晩秋の月光下の寒空にひびき冴えて澄みわたるものであった。慰めるといっても、冷え冷えと冴え澄んでいく慰めであろう。『砧』の「味」は、孤閨を守る女の怨慕の情が、砧を打つことによって晩秋の夜空に冴え澄んでいくところにあるのではないであろうか。」(相良亨『世阿弥の宇宙』、1990年、ぺりかん社)
地衣におつる松の声。衣に落つる松の声。
夜さむを風や知らすらん。
シテ 音づれの。まれなる中の秋風に。
うきを知らする。夕べかな。
彼女はひたすらに砧を打つ。次の詞章は「怨の砧」の歌であるとともに、「風の歌」でもある。擣衣の律動は彼女の心拍のようであり、「西より来たる秋の風」は彼女の思いをかぎりなく無化しながらその音を東の空に運ぶ。
シテ 宮楼髙く立って。風北にめぐり。
ツレ 隣砧ゆるく急にして。月西にながる。(1)
地蘇武が旅寝は北の国。これは東の空なれば。(2)
西より来たる秋の風も。吹き送れと。間遠の衣うとうよ。
シテ 古里の軒端の松も. 心あれ。
地軒端の松も心あれ。
おのが枝枝に。嵐の音を残すなよ。
今の砧の声そえて. 君がそなたに. 吹けや風。
あまりに吹きて松風よ。
わが心通いて人に見ゆならば。その夢をやぶるな
(1)宮楼は宮廷に建てられた水時計を置く楼閣、隣砧は隣の砧打つ音。
(2)蘇武は前漢武帝の時代に胡国に使節として使わされたが、捕らえられ、胡国の王のいうことを聞き入れなかったために十九年間虜囚の生活を送った。雁に故郷への手紙を託したという。
妻の打つ砧の音は「月の色風のけしき」に溶け込んで、まるで自然界全体が妻の悲しみの声を伝えようとしているかのようである。
シテ 文月七日の暁や。
地八月九月。げにまさに長き夜。
千声万声の。うきを人に知らせばや。
月の色風のけしき。かげにおく霜までも。心すごきおりふしに。
砧の音。夜あらし。悲しみの声虫の音。
まじえて落つる露涙。はらはらほろほろほろと。
いずれ砧の音やらん
妻は夫からの重ねての冷たい仕打ち(彼女はそう思いこんでいる)に、最後の命の炎をも消してしまうが、なんと邪淫の罪により地獄に堕とされたのであった。そして、地獄の責めとして砧を打ち続けることを命じられる。「砧も音なく松風も聞こえず、苛責の声のみ恐ろしや。」 地獄の砧は打てども打てども音がせず、亡霊となった彼女の耳には、唯一の「可能性」が根絶やしにされ、苛責の笞の音に転じるのである。この不可思議な展開を私たちはどう理解すればよいのであろうか。
シテ 獄卒阿防羅刹の。笞の数の隙もなく。
うてやうてやと。むくいの砧。
うらめしかりける。因果の妄執。
地因果の妄執の. 思いの涙。
砧にかかれば。涙はかえって。火焔となつて。
胸の煙の焔にむせべば。さけべど声のいでばこそ。
砧も音なく。松風も聞えず。
呵責の声のみ。おそろしや。
私には、妻の亡霊が地獄で受ける苦艱の様は絶望の「反射像」であるかのように思われる。絶望が結ぶ像はまさに「地獄」なのだ。絶望は死をも超えて絶望に堕ちたものを責め苛む。絶望とはこれほどまでに「死を超えた病」であることがこの物語から見えてくるであろう。このあと妻の亡霊は、帰郷した夫に地獄の苦しみを訴え、恨みの絶唱を謡うが、法華読誦の功力によって救われついには成仏する。しかし、その問題を考えることは別の機会に譲ろう。
稲田秀雄は、世阿弥による「つづれの錦と称される超絶技巧的な謡曲の文体」(稲田秀雄「能「砧」における修辞と構想」、同志社国文学(25)、1984年)をつぶさに分析している。そして、砧の音が音信であり、風のイメージの起点であり、形見であり、責め道具であり、成仏の機縁でもあることを指摘している。砧という一点に妻のすべての「思い」が収斂しているのだ。
ちなみに、世阿弥には「砧」と好一対をなす狂女物の曲「班女」があることに注目しよう。いずれも男に捨てられたと思い苦しむ女のかぎりない煩悶を描いている。前者は無事にめぐり合って華やかな結末を迎え、後者は待ちきれずに命が尽き果てる。前者は春の陽光に蘇り、後者は秋の寂寞に沈み、前者は扇に「可能性」を託し、後者は砧にすべてを託した。そして、前者は世阿弥の若い時代の作品であり、後者は晩年の作である。二曲は作者の終生の問い、人の心の奥底の真実を見届けることに答える試みだったのであろう。脇田晴子は、世阿弥自身の心のうちに「尽くしても尽くしても報われぬ思い」(『能楽のなかの女たち』、2005年、岩波書店)が心のうちにあって、この思いがこれらの曲に結実したのであろうという。とりわけ、晩年の世阿弥を襲った数々の不幸に耐えるなかで、彼は人間洞察の眼をこれほどにまで鋭くさせたのであろう。
2019年5月19日
『アンティゴネー』と能 ――能の詞花を訪ねて11
夢幻能の多くは、死者の霊が旅の僧の夢に現れ、弔いを願い、その弔いによって成仏するという展開をとる。夢幻能のスタイルは基本的に二場構成である。前半ではたとえば里女などの仮の姿で現れ、当の死者の存在をほのめかして消え、後半に僧の夢のなかで本体の姿を現して、死にいたった次第を物語り、僧の読誦とともに冥土に帰ってゆく…。このような筋書きは、文芸としては些か「奇抜」な部類に属するであろうが、能の世界でこれほど定着し愛好されているのは、この筋書きが日本人の心に密着し、安らぎを与えてきたからであろう。夢幻能は現行曲全体の優に過半を占めている。能の世界にあまりにも幽霊物語が多いことに私たちは驚嘆せざるをえないのである。
この世に舞い戻った幽霊は弔ってもらいたいのである。死者は弔いを受けることなしにはあの世に安住することができない。これが弔いの論理であろう。では弔いとはなにか。死者が執心から解放されることである。この世を去ろうとしているのに、この世の件の出来事に絆で繋がれており、冥界へと進むことができないでいるのだ。死者はなぜこの絆を断ち切ろうとするのか。それは絆のこの遮断こそが「死」ということの本懐なのだからであろう。死者は、この世に残しておきたい自らの物語を弔い人の心に渡すことによって、未練を断ち切ってあの世に旅立つことができるのである。生者も弔うことによって、死者がこの世を去り、彼岸の浄土に渡ったことを確認するのである。生の物語にけじめをつけること、ここに「死者の弔い」の意味がある。
ギリシア悲劇に『アンティゴネー』がある。悲劇詩人ソフォクレスの作品であり、『オイディプス王』、『コロノスのオイディプス』とともにテーバイ王家に訪れた呪いの悲劇を語る「テーバイ三部作」の一つである。オイディプス王亡き後のテーバイでは、オイディプスの王子の兄ポリュネイケスと弟エテオクレスとの間で王位争いの戦が起こり、互いに敵将となった二人は刺し違えて共に斃れたのであった。兄ポリュネイケスは反乱軍の側の将であったために、彼らに代わって急遽王となったクレオンによって、野に斃れたその亡骸を誰も埋葬してはならぬというお触れが出された。見せしめのため恥を曝させようというわけである。ところが、兄弟の妹であるアンティゴネーは独り野に行き、ポリュネイケスの亡骸に砂をかけ、閼伽の水を注ぎ、涙とともに弔ったのであった。次は、彼女を捕らえ引き立てた番人がクレオンに状況を説明する場面である。
かなりのあいだ、こうしていましたが、そのうち、中天にもう太陽の輝く円がかかりまして、熱さもだんだん増してきた、その時突然つむじ風が、大地から埃の雲を巻き上げました。空の厄介物です。それが平地に漲りわたって、野原に生えた木立の枯葉もみな汚してゆき、ひろい空までいっぱいに拡がりました。私どもは眼をつぶって、この天災を堪えていましたが、かなりのあいだたってから嵐がすんで眼を開けるとこの娘さんが目につきました。気が立った鳥の鋭い声で泣き叫ぶのです。ちょうど雛っ子どもを臥屋から、そっくり奪られた空の巣を見たときにね。そんなふうに、娘さんも露出しになった屍を見ると、泣声をあげて嘆き立てまして、そんな所業を働いた者どもに、烈しい呪いを浴びせたのです。それから両手ですぐと乾いた砂を運んで来て、よく叩きあげた青銅の水差を、高く掲げて三度、きまりのように灌ぎの水をかけめぐらしました。 (『アンティゴネー』、呉茂一訳、『ギリシア悲劇全集』第二巻、人文書院)
「墓に葬っても泣き嘆いてもならぬ」という布令を知っての仕業かというクレオンの詰問に、彼女は「正義の女神(ディケー)が、そうした掟を、人間の世にお建てになったわけでもありません。またあなたのお布令にそんな力があるとも思えませんもの、書き記されてはいなくても揺ぎのない神々がお定めの掟を、人間の身で破りすてができようなどと。」と答える。親しい身内の死者を葬ることは神の掟であって誰も制することができないと言って動じなかったのである。死者を葬ることは「神の掟」であるという。神の掟は人の掟にたいして絶対的に上回る。死者は放置してはならないのだ。
『アンティゴネー』は死者を葬るという生者の使命を主題とする戯曲であるが、能の多くの作品もこの同じ主題を扱っている。多くの能が幽霊の物語であり、弔いを主題としているということは、能がこの「神の掟」をギリシア悲劇よりも、さらには他のいかなる文学遺産よりも重く見ているという事実を表している。『アンティゴネー』では生者のみが登場し、死者は舞台に現れない。ギリシア悲劇には幽霊は不在である(その点では、ハムレットに復讐を誓わせる父王の亡霊を登場させる『ハムレット』の方が能との共通性を指摘できるかもしれない。もっとも能の亡霊は生者に復讐を誓わせたりしないが)。能は死者のための芸術であり、いかなる死者にも尊厳があり、弔われるべき威厳があることを訴えるための祭礼行為であることがもっと重視されてよい。もともと能は観客を喜ばせるための芸能ではなく、神を喜ばせるための祈請から興った「祈りの歌」だったのである。
夢幻能においては、亡霊の登場の仕方も、成仏の仕方も多彩である。旅の僧の前に不意に死者の霊が仮の姿で現れ、その夜、当の死者が本体の姿で現れるという曲ははなはだ多い。亡霊が酒を飲みに店にやってきたり、一旦は菜摘女に乗り移るが、それでも満足できなくて本体の亡霊がつきそうという破格の能もある。また、古塚に手向けていると死者が現れ、その供養に感謝するという能もある。多くは僧のまえに現れるのである。僧は生者と死者との仲立ちをになう存在であり、死者と語る霊力を持っていたとされたからであろう。それも、当て推量に旅の僧をえらぶこともあれば、たとえば相手を遊行上人や西行と心得て亡霊が出てくることもある(実方は歌人=同業者でもある西行を狙って現れた)。幽霊は旅人の夢のなかで出てくる。幽霊譚はすべからく「夢物語」である。幽霊は現ではないからこれは当然のことであって、夢物語だからといって馬鹿にしてはならない。この夢は霊夢なのである。往時の人々にはこのような霊夢が訪れることが時折あったのであろうか。近代合理主義の洗礼を受けた私たちには、このような霊夢は久しく絶えてしまった。霊界は否定され、死者はたんなる無とされ、人々に残された記憶はたんなる記録や思い出となってしまった。
『井筒』や『浮舟』や『松風』のシテたちはその悲しくも美しい物語を世に残して、「あの世」に消えてゆく。『敦盛』や『忠度』や『通盛』のシテたちは修羅の苦艱を「あの世」に持ってゆくことができないから、みやげ語りをするのである。これらの死者の話はたんなる記録語りではない。死者の「語り」はその死者が生者に託した伝言である。能は死者の伝言を芸術に高めようとする類例のない試みなのである。
弔いを主題とする作品のなかでも、『朝長』はとりわけ注目されるだろう。『朝長』は、若くして自害した源朝長の菩提の曲である。平治の乱の都大崩れの合戦で破れた源義朝の一行は東国に逃れようとして、一夜青墓の長の宿に身を寄せた。朝長は膝の口を射られ、青墓まではたどり着いたものの、雑兵の手にかかることを口惜しく思い、その夜半に自害した。
物語は、朝長の乳母子でいまは出家した僧が朝長の墓に詣でるために青墓にやってきたところから始まる。僧が墓前で弔っていると、一人の女性が弔いに現れた。次のシテ(青墓の長者)の出の謡は、死者との別れの歎きを謡って卓越した弔い歌である。
花の跡とう松風や。花の跡とう松風や。雪にも恨みなるらん。
これは青墓の長者にてさむろう。
それ草の露水の泡。
はかなき心のたぐいにも。哀れを知るは習いなるに。
これはことさら思はずも。人の歎きを身の上に。
かかる涙の雨とのみ。しおるる袖の花薄。
穂に出だすべき言の葉も。泣くばかりなる。有様かな。
光の陰を惜めども 月日の数のほどふりて。
雪のうち春は来にけり鶯の。春は来にけり鶯の。
氷れる涙今ははや。とけても寝ざれば夢にだに. *
御面影の見えもせで。痛わしかりし有様の。
思い出ずるもあさましや。思い出ずるもあさましや。
*雪のうちに春は来にけり鶯の こほれる涙今やとくらむ (古今集 藤原高子)
青墓の長者は、敗残の一行をもてなし、朝長の最期を看取った女性であるが、義朝がかねてから定宿としていたのであろう。いたるところ敵の目が光るなかでここは安心できる宿だったのである。朝長はこの宿で自害することを覚悟する。冒頭の言葉は、春の風は花を散らしたが(朝長の命を奪ったが)、訪れる冬の風が雪を散らすだろう(涙に明け暮れるだろう)、というほどの意味。それに続く詞章は心に残る文である。後半では二条后高子の歌を引いて、凍れる涙は解けても心の嘆きで寝ることもできないので、あの方の面影を夢にさえ見ることができないと歎く。つづく墓前の哀歌も心を打つ。
死の縁の所もあいに青墓の。所もあいに青墓の。
跡のしるしか草の陰の。あお野が原は名のみして。
古葉のみの春草は。さながら秋の浅茅原。
荻の焼原の跡までも。げに北邙の夕煙。
一片の。雲となり消えし空は色も形も.
なきあとぞあわれなりける。なき跡ぞあわれなりける。
青墓は地名であるが、死に縁のある名前だと謡う。墓のある辺りは青野ヶ原という名前であるが、春草はまだ萌え出ていず、さながら秋の浅茅が原の枯野のようである。萩を焼いた跡は本当に火葬場の煙のようだ。その煙を思わせる雲が色も形もなくなって消えてゆくのはなんと悲しいことか、というほどの意味である。
僧は長者に朝長の最期を委しく語ってほしいと頼む。それを受けた長者の「語り」は修羅の語りのなかでも異色の名曲であろう。その夜、僧が御法の読誦を唱えていると、朝長の亡霊(後シテ)が現れた。御法は朝長が好んだといわれる観音懺法であり、能も懺法の小書がつくと特別の後シテの出となる。亡霊は、都大崩れの様、義朝一行の逃避行、そして父義朝が野間で臣下の長田忠致に湯殿で討たれた様を語り、回向を頼んで消えていくのであった。
父義朝はこれよりも。
野間の内海に落ちゆき 長田をたのみ給えども。
たのむ木のもとに雨もりて やみやみと討たれ給いぬ。
いかなれば長田はゆいかいなくて主君をば。討ち奉るぞや。
いかなればこの宿の。あるじはしかも女人の。
かいがいしくも頼まれて。一夜の情のみか。
かように跡までも。御とむらいになることは。
そもそもいつの世の契ぞや。
一切の男子をば。生生の父と思い。
よろずの女人は 生生の母と思えとは。
今身の上に知られたり。
さながら親子の如くに 御歎きあればとむらいも。
まことに深き心ざし うけ 歓び申すなり。
朝長が後生をも 御心やすくおぼしめせ。
臣下の長田忠致を頼った義朝は臣下の寝返りに会って命を落とし、自害によって果てた朝長は宿の長によって手厚く葬ってもらった。臣下が裏切り、一夜の宿の女将が後々までも懇ろに弔ってくれるとはなんという世の約束であろうか、と謡う。続く「一切の男子をば。生生の父と思い。よろずの女人は 生生の母と思え」という詞章は、『梵網経』の「一切男子是我父 一切女人是我母」から引かれ、一切の男子を、生まれては死に、死んでは生まれる代々の世の父と思い、一切の女人をそのような世の母と思え、という意味である。経文ではこれに続けて、「我生生無不従之受生 故六道衆生是我父母」(誰もみなこの父母から生を受けないことはなく、したがって一切の衆生は我が父母なのである)という経文が続く。生者は弔う死者を我が父母と思い、死者は弔ってくれる人を我が父母と思うのである。そして一切の世の人間はお互いに「生生の父母」である。朝長の霊は、このように語って青墓の長の厚情に歓び、その弔いの御蔭で往生できるからご安心くださいと語り、消えてゆく。
2019年4月19日
月の能 ――能の詞花を訪ねて10
月は秋の風情を代表するものとしていつの時代にも愛でられ讃えられてきた。しかし、凍てつく冬の月や朧の春の月もよい。月は日本人の美意識を育て上げてきた至高の「守り神」の一つなのだ。能の世界でもこのことは変わらない。月はじつに多くの曲のなかで顔を表し、地上の物語を眺めてきたのである。多くの能は幽霊を主人公にしているが、もともと幽霊が出るのは夜であるから、月の明かりはうってつけなのである。「躯を守る幽魂は夜月に飛び」と「生田」で謡われるように、幽霊には月がむしろ必需品である。
月見ればちぢに物こそかなしけれ わが身ひとつの秋にはあらねど (大江千里)
『古今集』に歌われて以来、月は人びとの友であるだけでなく、彼らの生き様と内心を映し出す鏡でもあった。また、
雲隠れたりつる月の、にはかにいと明かくさし出でたれば、「扇ならで、これして
も月は招きつべかりけり」とて、さしのぞきたる顔、いみじくらうたげににほいやか
なるべし。
と、『源氏物語』(橋姫巻)に描かれて以来、月は地上の情景を描きあげるための不可欠の題材であった。
能の世界においても例外ではない。月の名曲といえば、多くの人は「羽衣」を思い出すかもしれない。もっとも、これは月からの来訪者の物語であり、しかも春の曙に男に衣を奪われるという筋であるから、風情を味わうという向きの話ではないかもしれない。
然るに月宮殿の有様。
玉斧の修理とこしなえにして。
白衣黒衣の天人の。数を三五にわかって。
一月夜夜の天乙女。法事を定めやくをなす。
白衣黒衣の十五人づつの天人の話は、恵心僧都(源信)の『三界義』に述べられているが、月を描いてこれほど機知に富み、詩情を誘うに見事な寓話はないであろう。
「融」は中秋の名月に浮かぶ都の庭園を美しく謡い上げた抒情的な曲である。源融が築いた庭園は陸奥の塩竃を模したものであったが、彼は月光に浮かぶ庭園に立って松島の月に思いを馳せていたのであろう。
心も澄める水の面に。照る月なみを数うれば。
今宵ぞ秋の最中なる。
げにや移せば塩竈の。
月も都の。最中かな。
月の情緒では、「井筒」もまた月下のあはれを美しく湛えたものとして白眉であろう。 在原寺の夜の月に紀有常の女が現れて寺井(井戸)に佇む姿は、およそ能舞台に映現したもっとも美しい情景の一つと云わなければならない。
寺井に澄める月ぞさやけき。月ぞさやけき。
月やあらぬ。春や昔と詠めしも。
いつの頃ぞや。筒井筒。
*在原業平の歌「月やあらぬ春や昔の春ならぬ わが身一つはもとの身にして」による。
月を描いて幽玄の極みにある曲では「野宮」を忘れてはならない。『源氏物語』賢木巻を題材にしたこの曲も中秋の名月に沈む静謐の神域を舞台にしている。竹の都と謳われた嵯峨野の月下の寂静のもとで黒木の鳥居にためらう御息所の霊の姿は、筒井筒の女とともに、能における秘められた花であるにちがいない。
野宮の。月も昔や。思うらん。
影さびしくも。森の下露。もりの下つゆ。
身のおき所もあわれ昔の。庭のたたずまい。
よそにぞかわる。けしきもかりなる。小柴垣。
「江口」は、「月澄み渡る水の面に。遊女のあまた歌ふ謡。色めきあへる人影は。」と難波の川面の艶にして物寂しい情景を謡い、「砧」は、凍てつく月下で夜すがら砧を打つ妻の悲痛の叫びを謡い上げた。「月の色風の景色。影に置く霜までも心凄き折節に。砧の音。夜嵐悲しみの声虫の音交りて落つる露涙。ほろほろはらはらはらと。いずれ砧の音やらん」。また、「古督」は、「月にやあくがれ出で給うと。 法輪に参れば琴こそ聞え来にけり。峰の嵐か松風かそれかあらぬか。」と月光のもとでかすかに伝わる琴の音を探り、「雨月」は、月下での老夫婦と西行との歌問答を描いてみせた。
月は漏れ雨はたまれととにかくに 賤が軒端を葺きぞわづらふ
*姥は月を愛でたいから軒端を葺くなといい、翁は板屋を打つ雨の音を聞きたいから軒端
を葺こうといい、いずれにしても面倒なことだ。
西海の藻屑と消えていった平家の公達を語る負け修羅の能でも、月は悲痛の物語を静かに見守る守護神であった。平清経は、平家の行く末に絶望して、暁にかかろうとする月下の西海の海に身を投げたのであった。
暁の。月にうそむく景色にて舟の舳板に立ち上がり。
腰より
横笛
抜きいだし。音も澄みやかに吹きならし。
今様を謡い朗詠し。こし方行く末をかがみて。
…西に傾く月を見れば。いざやわれも連れんと。
…舟よりかっぱと落ち潮の。底の水屑と沈みゆく
憂き身のはてぞ悲しき。
「通盛」は、平通盛夫婦の霊が篝火をつけた舟の作り物とともに登場するという異色の舞台で始まる(老翁と若い女の出立ちで登場するのは夫婦の風情に合わないが、巧みな能の公案というべきであろう)。シテが「暗涛月を埋んで清光なし」と登場で謡うのは、この曲の悲痛の情緒をよく表している。通盛の妻小宰相の局は、須磨の合戦で通盛が討たれたことを聞き、阿波の鳴門の沖で、西海に沈もうとする月とともに身を沈めた。
さるにてもあの海にこそ沈もうずらめ。
沈むべき身の心にや。涙の兼ねて浮かむらん。
西はと問えば月の入る。西はと問えば月のいる。
そなたも見えず大方の。春の夜や霞むらん。
涙もともにくもるなり。
月を謡って心の琴線にふれる曲のなかでも「松風」は際立っている。なかでもシテの出で謡われる月夜の汐汲みの歌は海人の「労働歌」というべきものであるが、月下の人事を謡ってこれほど美しい詩句は古今東西に見ることができないであろう。「松風」が至極の能とされる所以もこの情景と詞章にある。松風村雨の姉妹は亡霊となっても月光の射す夜な夜な汐を汲んでいたのである。この海人たちはわずかばかりの汐を焼いて糊口を得ていたのであった。
汐くみぐるま。わずかなる。
うき世にめぐる。はかなさよ。
波ここもとや須磨の浦。
月さへぬらす。袂かな。
…
かくばかり。経がたく見ゆる世の中に。
羨ましくも澄む月の
出汐をいざや汲もうよ
出汐をいざやくもうよ。
舞台は、海辺の松と桶の乗った汐汲み車の作り物が置かれ、須磨の浦となる。シテ、ツレ、地謡の掛け合いによる美しくもあわれな汐汲みの舞台は延々とつづき、観るものの心にも月光が沁み込むようである。すでに月は中空に高く浮かび、白銀の光を投げかけている。姉妹は桶の水面に映る月影に行平の面影を見たのであろうか、恍惚となる。
さしくる汐を汲みわけて。見れば月こそ桶にあれ。
これにも月の入りたるや。
うれしやこれも月あり。
月はひとつ。
影は。ふたつ
みつ汐の夜の車に月をのせて。
うしとも思わぬ。汐路かなや。
或る詩人は松風村雨のこの汐汲みの一節をほとんど狂騒的な筆致で絶賛している。「見よや。静かな月影は桶の中に浮かんでいる。ああ、諸君は想像の目で月の姿を見ねばならない。この能楽芸術は『想像の王国』である。想像の力で無が有を産み出さねばならない。この能楽芸術は『空虚の王国』である。諸君にして真実この王国の住者であるならば、諸君は現実の痛みと喜びとが幻像となって、空間を満たしていることを知るであろう。能楽芸術は詩の魂が祈禱を捧げる聖殿である」。(野口米次郎『能楽論』1943年、春陽堂文庫)
月の名曲は「松風」に終わらない。むしろ、これこそ月の能と言わなければならないのは、更科の虚空に浮かぶ満月のもとで旅人と老女の霊とが邂逅する「伯母捨」であろう。この曲はそれこそ月に捧げられた祈りの歌というべき味わいを有し、白衣に身をまとった老女の動きの少ない姿は、それこそ「夢かうつつかおぼつかな」という静謐の境を醸し出している。夕刻の迫るころ、旅人は伯母捨山の桂の木の辺りで里女と出会い、言葉をかわすが、女は伯母捨ということばを口にするやかき消すように姿を消したのだった。その夜、煌々たる月の光の下に現れた老女は、伯母捨という非業をも透明の月光に溶かしさり、月の物語を語ったのであった。煌々と山際から差し出でた望月が、いつしか中空高く輝き、西の空に傾き、夜もしらしらとあけるころ、老女一人が舞台に残り、その老女も消えて、舞台には一本の扇が残された…。(以下に引用した詞章は、金春安明手筆原稿「伯母捨古式」による。)
「伯母捨」の機縁となったのは、『古今集』の次の歌である。『大和物語』がこの歌を主題にして姨捨の物語を作ったのである。
わが心なぐさめかねつ更科や 伯母捨山に照る月を見て (読人知らず)
物語は、陸奥の信夫の某がしばらく都に滞在の後、善光寺に参詣し、中秋の月を見ようと伯母捨山に登ったところから始まる。
我この山に登りて見れば。
万里の空目前にして。
月のさこそと思いやる。
今宵の空のいつしかに。
なお待ちかぬる心地して。
心そらなる折かなかな。
するとどこからともなく女が姿を現し、伯母捨のゆかりの跡を教えるのだった。
- シテ
昔の伯母捨の。そのなき跡にて候えとよ。
- ワキ
捨ておかれにし昔の人の。
- シテ
- ワキ
- シテ
シテ これに木高き桂の木の陰こそ。
昔の伯母捨の。そのなき跡にて候えとよ。
ワキ さてはこの木のほとりにて。
捨ておかれにし昔の人の。
シテ そのまま土中に埋もれ草。かりなる世とて今は早。
ワキ 昔話になりし人の。
シテ なお執心や残りけん。
旅人は、夕影もすぎた伯母捨山にさし登る月に興を覚えていると、今度は白衣の老女が現れた。
さなきだに秋待ちかねてたぐいなき。
名を望月の見しだにも。
覚えぬほどに隈もなき。
伯母捨山の秋の月。
あまりに堪えぬ心とや。
老女は月を讃え、月光の因縁を説く。月の光を仏の祈願と説く老女の話は、仏教的な救済観と月光の空無の明かりとが渾然一体となった幻の世界を表しだし、まことに神韻を湛える幽玄の世界を創り上げている。月光を語ってこれほどの深度を感じさせる詩は他にないであろう。
然るに月の名どころいづくはあれど更科や。
伯母捨山のくもりなき。
一輪みてる清光のかげ。
団団として海嶠をはなる*
*団団は丸い様、海嶠は岬の意味。
一輪は望月を指し、まんまるな月が山の端から差出たさまを賈島の詩を引いて述べた一節である。「団団として海嶠をはなる」とは、いかにも指し出た月が煌々と輝きながら山の端を離れるさまを描いて巧みである。
然れば諸仏の御誓。いづれ勝劣なけれども。
超世の悲願普きかげ。
弥陀光明に. しくはなし。
さるほどに。三光西に行く事も。
衆生応して**西方に。すすめ入れんが為とかや。
**旧本による。現行本の多くは「衆生をして」
月の運行は仏の願いであり誓いであるという。弥陀の悲願が月光に乗って衆生のもとに届くという。三光とは太陽と月と星をさす。陽も月も星も次第に西に傾いていくが、それは仏が衆生を西方浄土に迎えるためであるという。
月はかの如来の。右の脇士として. 有縁を殊に導き。
重き罪を軽んずる. 転成の力***を得る故に。
大勢至とは号すとか。
天冠の間に。花の光りかかやき。
玉の台の数々に。他方の浄土をあらわす。
玉珠楼の風の音.
糸竹の調とりどりに。心引かるる方もあり。
はちす色々に咲きまじる。宝の池の辺りに。
立つやなみきの花散りて。芬芳しきりに乱れたり。
***六徳本による。難解な箇所であり、他に「天上の力」(『謡曲大観』第5巻、小学館日
本古典文学全集謡曲集1など)、「無上の力」(解註謡曲全集巻二、新潮日本古典集成
謡曲集上)、「无上の力」(岩波書店謡曲百番)などの校訂がある。
月は大勢至菩薩に擬えられるという。大勢至菩薩は阿弥陀如来の右に仕え(左は観音菩薩である)、衆生の罪を軽くする「転成」の力を持つとされる仏である。知恵の光を放つことによって衆生を救うとされるから、月と結びつけられたのであろうか。月光は大勢至の知恵の光だったのである。月の光輝を能作者は西方の極楽浄土になぞらえ、月宮殿の輝きと夢想し、その輝きが月光となって衆生に降り注ぐのだ、と説いたのである。
光もかげもおしなめて。到らぬ隈もなければ。
無辺光とは名づけたり。
然れども雲月の。ある時はかげみち。又ある時はかげ欠くる。
そ有為転変の世の中の 定めのなきを. 示すなり。
くまなく地上を照らす月光は無辺光と呼ばれるが、月は雲間に隠れたり姿を現したりする。またあるときはその光は満ち、あるときは欠ける。それはあたかも有為転変の世の中の定めのなさを示すかのようである。
老女の詩はたゆたうように続くが、感極まった彼女は月下の明かりのもとで舞を舞うのであった。舞は「関寺小町」「檜垣」とともに、老女の舞であり、およそ舞のうちでもっとも静謐と幽玄を湛えるものである。この老女の舞について、金春信高(金春流七十九世宗家)は次のような言葉を残している。「老女は無心に舞う。いつまでも、いつまでも。舞い続けた末に、舞台にうずくまって、はらりと扇を落とすのであった。長い静寂が流れる。やがて、「独り捨てられて老女が……」と謡いながら、老女はまた杖にすがって立ちあがる。杖を胸にあてて佇立する老女の姿は、天心の月とともに、いやましに神さびて輝くのであった。東雲の空がほのぼのと白む頃おい、老女は姿を消し、旅人も呆然と夢心地のまま山をおりる。三間四方の舞台に残っているのは、老女が捨てた扇であった。」(金春信高『花の翳』、2002年、岩波書店)
ひとり捨てられて老女が
昔こそあらめ今もまた。
伯母捨山とぞなりにける。
おばすて山と. なりにけり。
2019年3月21日
鬼女の憂い ――能の詞花を訪ねて9
執心に囚われた女が狂女にいたることがあることを私たちは見てきたが、それがさらに昂じて極限にまで行き着けば鬼女になるという。人が鬼になるというのである。鬼は人でも神でもなく、異界(幽界)の冥々たる存在であるが、たんに人間世界から超越しているのではなく、人の世にときに恐ろしい災禍をおよぼす存在でもある。
能は好んで鬼物を創作したが、いま私たちは「鬼女物」に注目する。なかでも「葵上」、「黒塚」、「道成寺」は三鬼女と呼ばれ、刮目すべき舞台を作り上げている。その他にも「鉄輪」「山姥」「紅葉狩」などの「鬼女物」の曲がある。これらの作品の主人公たちは、いわば執心がその最果てにまで行き着いて人の心を振り捨て、異界の存在になってしまったのであろう。もっとも、「山姥」のシテである山姥は産土神的な由来を持ち、始めから「鬼」=山の神であった。全国各地に山姥伝説が伝えられているが、山が里に住む人間にとって畏怖すべき異界であったことを受けているのであろう。ちなみに、足柄山の金太郎は山姥の子であったという。また、「紅葉狩」の鬼女たちは戸隠山の鬼が平維茂に退治された伝説によっており、また鬼無里には紅葉という鬼女がいたという。その由来は不明であるが、あるいは戸隠という険峻な山野ゆえの地霊なのであろうか。
鬼女たちは、般若面によく表れているように、角が生え、口が耳元まで裂けてしまうほどにすさまじい形相を伴う激しい怒りと逆上の執念に駆られている。にもかかわらず、その怒りの裏面には、悲しさが漂い、あわれと寛恕の思いをさえにじませている。もともと心美しい女性であった面影は消えていないのである。「鉄輪」の後シテである女の生霊は橋姫または生成の面を着けるから、まだ鬼女になりきっていない(いずれの面も口が十分に裂けていず、より般若に近い生成もまだ角が半成りである)。これは夫の離反を怨じた女が、自ら望んで鬼になって夫を取り殺そうと走った話であるために、その作為性が残って鬼になりきれなかったためであろう。
因みに、般若面は般若坊が作者であることによってその名がつけられたが、一説に怨霊退治の御修法で般若経が読まれたことによって怨霊が退散したことに由来するともいい、「葵上」を演じるにもってこいの面である。女面であるが、苦悩、嫉妬、怨恨が魔性にまで達した姿を表しており、角が生えることと蛇の姿になることがその「必要条件」である。また、装束は般若出立であるが、必ず鱗箔を身に纏う。
それでは鬼女とはどのような存在か。鬼女にはそれぞれに然るべき理由がある。憎しみや嫉妬の念が満ちて人が鬼に変化したのであるが、しかしなぜ「鬼」に変身するのだろうか。「鬼」という漢字の原義は「死者の霊魂」を意味する。また、オニは古くは「モノ」といい、神でも人でもなく怪しく目に見えない存在を意味した。この「モノ」が目に見えない隠れた存在を表すことから隠(オン)の字が当てられ、オニに転じたともいう。そして、この「モノ」がわが国の「たたり」信仰と結びついて、「もののけ」や怨霊となり、また仏教と結びついて餓鬼や地獄の羅刹になったという。それゆえ鬼は隠れた世界、冥界の存在であるが、安定したこちらの世界に接し、ときに結界を乗り越えて侵犯してくる存在でもある。鬼の住む世界はこの世の結界の彼岸にあり、人の住む里の向こう側(ヤマ)にある。鬼は目に見えない闇の世の使い、神と人との中間者、負の働きを有する潜勢態なのである。人の目に見えない鬼は、現世の人間には想像力によってのみ捉えられる。それゆえ、鬼はそのイメージが多様多彩に変化するのである。
ちなみに、『源氏物語』帚木巻には、「ものにおそはるる心地して~」という言葉がある。この「もの」は怨恨を持った霊、すなわち悪霊あるいは物の怪を意味し、異形の存在を意味する。この物語の世界では、物の怪という異形の存在が目を凝らして人間の一挙手一投足を窺っている。なかでも、六条御息所というもっとも高貴な女性が生霊や死霊となり、光源氏の晩年にまで憑いてまわるところにこの物語における負の主題がある。王朝世界の裏側には都人が怯え、祈祷に救いを求めざるを得ない闇の原理が働いていたのであろう。
さて「鬼女物」において語られる鬼女はこの「モノ」が可視化して人の前に現れた姿だと思われる。彼女たちを鬼女にしたその誘因は怨恨、嫉妬、絶望であった。その物語はいずれも「あはれ」の極みを語りだしている。彼らがなぜ鬼女になったのかという、その理由に「鬼女物」の精髄があるのだ。「老女物」が「あはれ」の深奥を教えるとすれば、「鬼女物」は「あはれ」の極北を描き出している。鬼女は人間の限界の姿だったのである。われわれは舞台で祈り伏せられる鬼女を見ながら、限界にまで追いやられたその苦悶に思いを馳せる。世阿弥は「形鬼心人」(『二曲三体人形図』)という言葉を残しているが、鬼のなかには人の心が失われずに残っている。そして能は、一つのモノのなかに鬼の形と人の心が相住むというその姿を描くことに腐心するのである。世阿弥は、鬼の能には「面白き」便りがなければならないという。人の心を驚かせると同時に和ませる働きがあるとき、「面白し」が生まれるというのである。「たゞ、鬼の面白からむたしなみ、巌に花の咲かんがごとし」(『風姿花伝』)。
「葵上」は『源氏物語』から採られた曲であるが、シテ六条御息所の生霊(物の怪)は前場では泥眼、後は般若の面で登場する。あたかも「嫉妬」という目に見えない怨念が舞台において嵩じ、「純粋嫉妬」にまで先鋭化したような能であるが、この上ない高貴な女性が我が意の及ばないところで鬼(生霊)となって暗躍するところに、この物語の「あはれ」がある。後の出で、唐織を被ぎ這い出る姿はこれぞ嫉妬の出現という傑作の公案であろう。
思い知れ。
怨めしの心やあら、怨めしの心や。
人の恨みの深くして。
うきねに泣かせ給うとも。
生きてこの世にましまさば。
水くらき。沢辺のほたるの影よりも光る君とぞ契らん。 (1)
わらわは蓬生の。
もとあらざりし身となりて。
葉末の露と消えもせば。 (2)
それさえことに怨めしや。
- 私のこの深い恨みは、そなたがどんなに苦しみ泣こうとも、生きているかぎりは光源氏と契るであろうから、晴れないのだ。
- 私はもとあらの(根本がすけすけの)蓬に置く露のように消えてしまっても、
「黒塚」の鬼はまことに「あはれ」である。『拾遺和歌集』にある、
陸奥の安達の原の黒づかに 鬼こもれりといふはまことか (平兼盛)という歌によって作られた能であるが(『大和物語』(第五十八段)にも同歌があるが、嫁取りの物語として歌われている)、深刻なのは伝承の物語の方である。伝承譚は次の通り。
その昔、岩手という女が都の公家に乳母として奉公していた。彼女の仕える姫は生まれながらにして不治の病におかされていたが、岩手は何とかして姫を救いたいと考え、妊婦の胎内の胎児の生き胆が病気に効くという占を信じ、生まれたばかりの娘を置いて旅に出た。奥州の安達ヶ原に辿りついた岩手は岩屋を宿とし、標的の妊婦を待った。長い年月が経ったある日、若い夫婦がその岩屋に宿を求めた。女の方は身重である。ちょうど女が産気づき、夫は薬を買いに出かけた。岩手は女に襲い掛かり、女の腹を裂いて胎児から肝を抜き取った。だが女が身に着けていたお守りを目にしたとき、岩手はその女が自分の娘であることを知った。あまりの出来事に岩手は狂いはて、旅人を襲っては生き肝をすすり、人肉を喰らう鬼婆に成り果てたという。 (ウィキペディア「黒塚」からの要旨。木口勝弘『南奥の歴史と民俗』、みずうみ書房、1982所収〉
「道成寺」は乱拍子や鐘入によって観る人を圧倒し、また若手能楽師の登竜門となる曲でもあるが、シテ(白拍子の女)にはあまりにも悲しい悲恋の物語があった。そのモデルとなった安珍清姫の伝説は平安期の『法華験記』や『今昔物語集』に見られるが、「道成寺」では、ワキの住僧が落ちた鐘をまえにその謂れを語っている(ワキの習いとなる詞章である)。少し長いが全文を引用しよう。
むかしこの所にまなごの荘司と申す者の候いしが。一人の息女を持つ。また奥より熊野詣での山伏のありしが。かの荘司がもとを定宿とし。年年とまりけるが。いたいけしたる土産などを持ちて来たり。かの息女に与えしかば。荘司娘を寵愛のあまりに。あの客僧こそ汝がつまよ夫よなどとざれけるを。幼心にまことと思い年月を送る。さるほどにかの客僧。またある時荘司がもとに泊りしに。かの女申すよう。いつまで我をばかように捨て置きたもうぞ。この度は奥へ連れてお下りあれと申す。その時客僧大きに驚き。夜に紛れて荘司がもとを逃げ去り。女退がすまじとて追っかけしに。山伏この寺に来たり。かようかようの子細によりこれまで参りて候。まっぴら助けてくれよと申されければ。この寺の老若寄り合い談合し。おおよそに隠しては悪しかりなんと思い。その時撞き鐘を下しその中に隠す。さるほどにかの女。日高川のほとりを上下へと走りありきしが。おりふし水増さりて越すべきようもなかりしかば。一念の毒蛇となって。日高川をやすやすと泳ぎ渡りこの寺に来たり。ここかしこを尋ねありきしが。鐘のおりたる事を不審に思い。竜頭をくわえ七まといまとい。尾にて叩けば鐘はすなわち湯となつて。山伏も即時に消えぬ。なんぼう恐ろしき物語にて候わぬか。 (金春流「道成寺」二十九巻ノ三)
鬼女物の曲はいずれもその意表をつく演出によって観客の耳目を惹きつけるが、その背景にはこれらの悲話があったのである。思うに、幽界とは人の心の奥深くに掘られた執心の洞窟であり、鬼とはそこに住む記憶の化身なのであろう。
舞台における鬼の演じ方について、世阿弥が興味深いことを語っている。彼の言うところは味わうに値するであろう。
凡、怨霊・憑物などの鬼は、面白き便りあれば、易し。あひしらひを目がけて、細かに足・手をつかひて、物頭(不明、鼓のカシラのことか?)を本にしてはたらけば、面白き便りあり。…先、本意は、強く恐ろしかるべし。強きと恐ろしきは、面白き心には変れり。抑、鬼の物まね、大なる大事あり。よくせんにつけて、面白かるまじき道理あり。恐ろしき所、本意なり。恐ろしき心と、面白きとは黒白の違ひ也。されば、鬼の面白き所あらん為手は、極めたる上手とも申べきか。 (『風姿花伝』)
黒白の違いがある「恐ろし」と「面白し」を一つながらに演じることにシテの要点があったのである。それは、「強き」でありながら「幽玄」を表すことでもある。ところが「強かるべきことを幽玄にせんとて、物まね似たらずば、幽玄にはなくて、これ弱き也。」となり、また「強かるべき理過ぎて強きは、ことさら荒きなり。幽玄の風体よりなを優しくせんとせば、これ、ことさら、弱きなり。」(『風姿花伝』)となって、まことに始末が悪い。このために彼は演者に「動十分心 動七分身」という境位を求める。「心を十分に動かして身を七分に動かせ」というのである。とくに足踏の技について彼が強調している話は興味深い。
身と足と同じやうに動けば、荒く見ゆるなり。身をつかふ時、足を盗めば、狂うとは見ゆれども、荒からず。足を強く踏む時、身を静かに動かせば、足音は高けれども、身の静かなるによりて、荒くは見えぬ也。 (『花鏡』)
鬼の能、ことさら当流に変れり。拍子も、同じものを、よそにははらりと踏むを、ほろりと踏み、よそにはどうど踏むを、とうど踏む。砕動風鬼、これなり。 (『申楽談儀』)
足踏について彼は、「強身動宥足踏 強足踏宥身動」ということを説いているのである。強でありながら弱(宥)であるところに、鬼の働きが強きでありながら幽玄であることが可能になるというのである。おそらく「鬼女物」や「鬼神物」において、動と静という能の二極構造がもっとも明瞭に現れているのであろう。
2019年2月20日
「百万」の 理由 ――能の詞花を訪ねて8
能「百万」は、世阿弥が「嵯峨物狂」という古曲を改作し、百万という曲舞の名手を狂女のシテとして登場させ、能の世界に曲舞を本格的に取り入れた画期的な曲である。「嵯峨物狂」は曲舞を中心とする曲であったと考えられるが(今はその名のみが伝えられている)、彼の父観阿弥が得意としていた曲であった。いわば能と曲舞との橋渡しの役を果たした曲である。「百万」はこの曲舞の能を受け継いで改作された曲であるが、これを機縁にして能楽のなかにクセ(基本形は、次第−クリ−サシ−クセ(クセの終句は次第と同句である)という長大な小段群から成る)が導入され、一曲の中心的な展開部として定位するようになったのであるから、画期的なのである。「百万」には当初は「地獄の曲舞」が収められていたといわれるが、狂女百万の物語に適うべく現行の「百万クセ」に入れ替えられたのであろう。「地獄の曲舞」は元雅(世阿弥の嫡男)によって「歌占」に収められ、百万クセと並んで、曲舞の原型を表すものとされている。こうして「百万」は能におけるクセを確立するとともに、狂女物の作品群の原点ともなったのである。
物語はまず、都の僧(ワキ)が一人の子ども(子方 百万の子)を連れて大念仏を見物に清涼寺にやって来たところから始まる。ところが、その子の母百万が、出奔したわが子を探して清涼寺にまでやって来、子を探していたのである。彼女は曲舞の名手であるが、大念仏に詣でた群衆の前で舞を舞うことによってわが子を探しだそうとしていたのだ。こうして、わが子が目の前にいると知らずに狂女は念仏会の舞を舞うのであるが、そこにはいくつもの仕掛けが嵌められていた。
嵯峨清凉寺の大念仏(融通大念仏)は、鎌倉期に円覚上人によって始められた念仏会である(1279年)。一人の念仏が周りの人々の念仏と通じ合うことによってより大きな功徳が生まれるという「融通」の教えが大きな反響を巻き起こし、「洛中辺土の道俗男女雲のごとくにのぞみ、星のごとくにつらなりて群集」したという(「融通念仏縁起絵巻」)。雲のごとき群衆が南無阿弥陀仏を曲調豊かに合唱し、壮大な一体感を体験するという法楽の境地は民衆にとって何よりの喜びだったのであろう。大念仏会には乞食非人も多く集い、自ずと白拍子や曲舞女、傀儡たちが法楽の舞や曲芸で参集者を魅了したにちがいない。そして、民衆の中には「土車」に引かれた不具者たちも集っていたのである。
ちなみに、清凉寺大念仏会における歌舞は今日にいたるまで「嵯峨大念仏狂言」の形で伝えられている。往時の法楽の舞芸が無言の宗教的仮面劇となって悠久の面影を今日まで伝えているのである。大念仏会には観阿弥や世阿弥も訪れたことがあったのであろうか、あるいは能「百万」の影響もあったのであろうか、次第に猿楽や狂言の作品を取り入れた仮面劇が造形されるようになったものと思われる。
能「百万」は、円覚上人その人が母と生き別れになっていたところ、あるとき一人の僧から母の居所を教えられ再開を遂げることができたが、その僧は地蔵菩薩の姿を顕して飛び去ったという説話にヒントをえて作られた曲である。この円覚上人の物語と百万という曲舞女の物語が結びついて、清凉寺で母と子が再会するという物語が生まれたのであろう。それゆえ、「百万」における舞は実際に清凉寺で舞われた念仏踊りを写し取ったものとも推察される。とくに、百万が舞う「車の段」や「笹の段」の所作にはその面影が伝えられているかもしれない。
能の開口では、子(稚児であろう)を伴った僧が門前の者(アイ)になにか面白いものはないかと尋ねると、百万という女物狂いが面白く舞うという。下手くそに念仏を唱えると、百万が腹を立てて出てくるというのである。まずはアイによる滑稽な念仏踊りが見ものである。そこへ笹を手にした狂女が出てきて、アイの肩を笹で打った(笹を手にすることは狂女のシンボルである)。そして、狂女の舞が「車の段」、「笹の段」とつづき、長大な「クセ」へと繰り広げられる。舞尽しの舞台は果てることのない大念仏の写しであるかのようである。
百万が舞う「笹の段」はとくに興味深い。車を引く所作が印象的でユニークな舞なのである。
わずかに住める世になお。三界の首枷かや。
牛の車の常とわに.いずくをさして引かるらん.
えいさらえいさ。引けや引けやこの車。
物見なり物見なり。げに百万が姿は。
百万が土車を引く所作が謡われる箇所である。牛のポーズをするかと見るや、渾身の力を絞って車を引く型に移る。百万が引く土車には当時広まった互助的風習が背景にある。土車は、通例不具者や病人が乗るための低い無蓋車である。彼らは自力で歩いて来て大念仏会に加わったり社寺参りをすることができない。唯一の手立ては車で運んでもらうことであるが、そのためには引き手を頼まなければならない。行く人に車を引っ張ってもらって巡礼や参詣をするという風習が当時存在したのであろう。そして、引いた人もその功徳で来世の幸せが得られると信じられたのであろう。それゆえ引き手は袖振りあった行きずりの人であり、車を引くことはひとつの施行であり、慈善行為とされたのである。いわばこの時代の一種の相互扶助の福祉事業であるといえよう。シテの百万はその土車引きを模した狂い舞(笹ノ段)を舞ったのであった。土車の物語は後に「小栗判官絵巻」に描かれているが、照手姫が土車を引いたという場面は「百万」から採られたものかもしれない。
「百万」の描く世界は相互補助と弱者救済の世界だったのである。狂女の苦悩と悲願の舞は弱者の穢土からの救済への祈願と一体であるという思想がそこにある。「百万」には遊女から狂女への変容が見られると思われる。歌舞集団としての女性から市井の女性への変貌、あるいは両者の融合がこの時代に生まれたのではないか。それまでは非人とみなされていた遊女たちがその芸によって市井の寵児になったというべきか。能はさまざまな女性を描くことによって、女の懊悩の生きざまを芸術表現に高めたという功績をもつが(それ以前に、女の生き方の美的表現の桂冠というべき『源氏物語』がある)、その機縁をなしたのが「百万」であるように思われる。世阿弥が狂女物を構想したとき、彼は社会の背面を担う女性たちの生存と被差別者や不具者の生存とのあいだに掛け橋をかけたのである。
能には遊女、白拍子たちが多く登場するが、彼女たちはいずれも社会の悲哀を生き抜いた芯の強い女性たちであり、美しい心の持ち主である。「江口」、「檜垣」、「熊野」、「朝長」、「班女」、「千手」、「祇王」などに登場する女性はいずれも高い志操を心に秘め、その卓越した態度や行動によって観るものに感動を与える。また、「舟弁慶」、「二人静」、「吉野静」などの「静物」は、静御前の才色両有の姿を描き出している。これらの作品のシテたちは遊女であったから、能の世界はこれらの中世社会の陰を生き抜いた女性たちによって至高の表現美を与えられたことがよく分かる。遊女的精神が中世文化に浸透したとき、能はひとつの美的世界を発見し、それを「狂女物」や「執心女物」の様態として、舞台上にあらたな人間美の世界を開いたのではないだろうか。狂女の悲嘆と遊女の悲哀のなかに人間の真実を見たとき、たしかに能はひとつの卓越した表現世界を発見したのである。
2019年1月21日
「狂女物」の源を訪ねる ――能の詞花を訪ねて7
狂気の問題をいま少し考えてみよう。能における狂気の芸術は、それがたんなる狂人の物語であるにとどまらず、豊かな人間性描写と一体であることにその特徴がある。狂女たちはそれぞれの仕方で苦悩を精神美にまで昇華させている。それでは、彼らはどのような性格を持ち、どこから来たのであろうか。私たちは狂女の「故里」を訪ねて古代中世の社会の陰で活躍をした美しい花を訪ねてみよう。
能が見据える狂気は、身は現世にありながら心が異世界に転移したときに生まれる。『源氏物語』において、六条御息所の魂が物の怪(生霊)となり、わが身からさ迷い出ることを夢見にそれと知りながら止めることができず、宇治川に身を投げようとした浮舟が横川の僧都に助けられるも死線をさまよい過去を切り捨て、世の中とのつながりを断ち切ったとき、たしかに「狂気」のひとつの極点が語られたのであった。狂気とはあらぬかたに心が振り切れてしまう状態を言うのだ(「移し心」の狂気と言おうか)。能はこのような「思いの流謫」に寄り添い、その多様な展開を求めて「狂気の芸術」を創りげてしまったのである。
狂気が美と一体となるにあたって重要な役割をはたしたものが歌舞遊楽である。歌舞はもともと「ハレ」の心を発露させる行為であり、祝祭のための禊である。舞手はその心がわが身から飛翔しており、その意味である種の狂気の状態にある。そのような心的状態を能は狙う。能は狂気を歌舞と一体化させることによって超俗的な美が誕生することを知っているのである。
日本の芸能のルーツをたどれば、巫女の神事に遡るであろう(その始まりは天岩戸の前で舞った天鈿女(あめのうずめ)の舞である)。巫女は神を下ろす(霊が依り憑く)ためにさまざまな所作をおこなうが、そのなかに歌謡と舞があった。巫女はその呪法にシャーマニズムの跳躍を受け継いでおり、神事において虫や蝶の如く跳ねたり、舞ったりした。そのなかでさまざまな歌謡を生み出し、寿詞を唱えたが、その際に鼓や鈴を携えることが多かった。それらは神の御声の象徴であったという。
巫女は、熊野巫女、貴船巫女、祇園社巫女など各地に座(巫女座)を組んで競いあったといわれる。脇田晴子は、「巫女はやはり舞が堪能でなければならなかった。それでないと神が感動して神助を与えないし、神が感動したかどうかはわからないものであるから、人々が感動することによって、そして本人も興奮しないと神は降臨しないのであろう」と言っている(脇田晴子『女性芸能の源流――傀儡、曲舞、白拍子』、2001年、角川選書)。舞は神楽にとどまらず、地方によって多種多彩であり、各地で歌舞の形式が形成されていったものと思われる。そして、これらの歌舞の要素が次第に巫女から分離し、神事から離れて歌舞を専門の生業とする集団を生み出していったのである。
傀儡(クグツ)と呼ばれる最初の芸能集団は、朝廷の支配を直接受けず、税を収めず、山に住み定住をしなかった狩猟民族の末裔だといわれる。彼らは木偶を舞わせたり、軽業を舞うことから傀儡と呼ばれたが、とくに女の傀儡(傀儡女)は、歌謡を歌い舞を舞い、あるいは売笑を行うことによって、影響力を伸ばした。今様、足柄片下、催馬楽、田歌、棹歌、辻歌、風俗、呪師などはもともと巫女の歌い出したものであるが、傀儡女がこれらを引き受けて独立した歌謡を生み出したという。
傀儡子(クグツ)は、定まれる居なく、
当
る家なし。
穹盧氈帳
(1)、水草を
逐
ひてもて移徙す。頗る北狄の
俗
に
類
たり。男は皆弓馬を使へ、狩猟をもて事と為す。・・・女は愁眉・啼粧・折腰歩・齲歯咲(2)を成し、朱を施し粉を傳け、倡歌淫楽して、もて妖媚を求む。・・・一
畝
の田も耕さず、一枝の桑も採まず。故に県官に属かず、皆土民に非ずして、自ら浪人にひとし。上は王公を知らず。傍牧宰を怕れず(3)。課役なきをもて、一生の楽と為せり。夜は百神を祭りて、鼓舞喧嘩して、もて福の助を祈れり。 (大江匡房『傀儡子記』)
(1)穹盧は天幕、氈帳は毛織物をいう。
(2)齲歯は虫歯、虫歯の痛みをこらえるかのように咲(笑)う。
(3)牧宰は国司。近くにいる国司をも怕(怖)れない。
後白河法皇の時代の頃までには、傀儡女は足柄や美濃青墓において専門の今様の歌唱集団を形成していた。足柄では宮姫、なびき、四三などの歌の名手が知られ、青墓には目井や後白河の師匠となった乙前がいた(能「義朝」の前シテである青墓の宿の長者(延寿)もまた傀儡女だったという)。傀儡女らの芸は、のちに猿楽に取り入れられ、操り人形はからくりなどの人形芝居となり、江戸時代に語り物や三味線と合体して人形浄瑠璃に発展した。傀儡の芸や今様は、能楽や歌舞伎の源流となり、あるいはそのまま寺社の神事(神楽、剣舞、相撲など)となって伝承された。
遊女は傀儡から分かれたものであるが、とくに難波津が交通の要衝として歓楽化するとともに、江口、神崎、蟹島の傀儡が遊女と呼ばれるようになった。彼らは、白拍子を得意とする白拍子舞女となったり、あるいは流行し始めていた曲舞女となった。白拍子は水干と袴の神事装束(男装?)で舞ったが、基本拍子を踏むことによって白拍子と呼ばれた。
摂津国に至れば、神崎・蟹島等の地あり。門を比べ戸を連ねて、人家絶ゆることなし、倡女群を成し、扁舟に棹さして旅舶に着き、もて枕席を薦む。声は渓雲を
遏
め、韻は水風に
飃
へり。経廻の人、家を忘れざるなし。洲蘆浪花、釣翁商客、舳蘆相連なり、
殆
水なきがごとし。(1) 蓋し天下第一の楽しき地なり。江口は則ち観音を祖と為し、中君・□□・小馬・白女・主殿あり。蟹島は則ち宮城を宗と為し、如意・香炉・孔雀・立牧あり。神崎は河菰姫を長者と為し、孤蘇・宮子・力命・小児の属あり。皆これ
倶戸羅
(2)の再誕、衣通姫の後身なり。 (大江匡房『遊女記』)
(1)洲には蘆が生い茂り、白浪は花のごとし。翁の釣り船や酒食を商う舟、遊女の舟などの舳と艪が接し、水面も見ぬほどのにぎわいである。
(2)インドの声の美しい鳥の名。
とくに基本歌謡としての今様の流行は狂女物などの能を生み出す最大の苗床となった。その火付け親ともいうべき後白河法皇は『梁塵秘抄』を著しているが、そこには彼の今様狂いがみごとに描き出されている。後白河法王は若いときから今様の狂信的愛好者であったが、乙前を師と仰ぎすべての今様を習って、完全にマスターしたという。次の文は、彼が『梁塵秘抄』を編むにあたって、自らの遊興の半生を述懐した詞である。
此今様をたしなみ習ひて、秘蔵の心ふかし。定めて輪廻業たらむか。我身五十餘年をすごし、夢のごとしまぼろしの如し。既になかばは過にたり。今はよろづを投捨てて、往生極楽を望まんと思ふ。たとひ今様を歌ふとも、などか蓮台の迎へにあづからざらむ。其故は、・・・哥を歌ひてもよくきかれんと思ふにより、外に他念なくて罪に沈みて、菩提の岸に至らむ事を知らず。それだに一念の心起こしつれば往生しにけり。ましてわれらはとこそ覚ゆれ。
大方詩を作り、和哥をよみ、手をかくともがらは、かきとめつれば、末の世迄もくつる事なし。こゑわざの悲しき事は、我身かくれぬる後とどまる事のなき也。其故に、なからむあとに人見よとて、未だ世になき今様の口傳をつくりおく所なり。 (『梁塵秘抄』佐佐木信綱校訂、岩波文庫)
また、都では百万、乙鶴らが曲舞女として活躍した。曲舞はもともと法楽の舞から始まったが、寺社で舞われ、清凉寺大念仏会などをつうじて広まっていった。観阿弥がこの曲舞を能に取り入れ、能の定型を作りあげたのである。「この百万が原型となって、その後狂女物といわれるジャンルができ、いくつかの変種が作られるほど風靡していくが、探し求めて遍歴するのはいつも母親で、子が探し求める話は少ない。これは母の子を求めての狂乱という母性の発露がテーマになっている・・・」(脇田晴子、前掲書)。
百万は大和の地で曲舞を広め、その礎を築いた伝説的な女性であり、また山姥の舞で都を風靡して百万山姥の名でも知られる曲舞女である。この百万の舞を機縁として狂女物や女物の能が生み出された(「百万」と「山姥」)のであるから、能は百万にずいぶん大きな恩義を負うている。そして世阿弥が百万を狂女に仕立て上げて「百万」を創作して以、狂女は能に不可欠の主役となったのである。遊女や白拍子、曲舞女が狂女のルーツだといえば、人は訝るかもしれない。しかし女物狂いのシテの多くは白拍子や曲舞女などの女であり、舞の名手たちである。彼女たちの舞は人事の世界にぽっかりと穴の空いたような異世界を呼び起こしたのである。この異世界を狂気と読み解いたところに世阿弥の眼力がある。
2018年12月23日
狂女物の世界 ――能の詞花を訪ねて6
能の世界は狂気に満ちている、と聞けば不審に思われるだろうか。ところが能の舞台では狂者がさまざまな場面で活躍をし、観る人の心をかき立てるのである。能においては、狂気は人間の不可欠な「資質」である。悩む人の心は懊悩から執心へ、そして執心から狂気へと進む。能は人の心のこの「運動法則」をよく心得ていて、多彩な作品によってこの「情態」を舞台に出現させる。
能の世界には、胸の焦がれ、渇望、悲哀、恩愛、怨念の情に駆られた主人公たちがさまざまに登場する。そのなかでも「狂女物」は、苦悩に打ちひしがれた現実の女性を主人公とし(したがって「狂女物」は現在能である)、その狂気の行状を描く。「狂女物」はより広範な作品群である「執心物」の一つの特化した形態だと考えられる。両者は同族であり、その特性は互いに重なり合っている。狂女物は生者の狂気を、執心物は死者の執心を語るのであるが、狂気は執心という火種が燃えさかる炎であり、その火種は死後にまで熱を持ちつづけるとみえる。
「狂女物」は、その多くが人気曲であり、能の世界の一翼をなすものとして多くの人に親しまれている。能の愛好者なら、「角田川(隅田川)」や「花筐」の名を耳にすれば、心の底からふつふつと興味の泡が沸き立つのを覚えることだろう。世阿弥が言うように、「狂女物」は「此道の第一の面白づくの芸能なり」(『風姿花伝』)。
親に別れ、子を尋ね、夫に捨てられ、妻に後るる、かやうの思ひに狂乱する物狂、一大事なり。よき程の仕手も、ここを心に分けずして、ただ一偏に狂ひはたらくほどに、見る人の感もなし。思ひゆえの物狂をば、いかにも物思ふ気色を本意にあてて、狂ふところを花にあてて、心を入て狂へば、感も、面白き見所も、定めてあるべし。(世阿弥『風姿花伝』)
「思ひゆえの物狂」ということが狂女の心のたち切られた琴線なのである。主人公が女性であり、子や愛人など親しい人を失った、いわば心に穴が空いたような「欠損感情」に苛まれていること、悲しみを静かに耐えるのではなく、失われた者を探し求めて危険な行動に出ようとすること、これらが「狂女」の資格である(「雲雀山」のようにシテ(乳母)が逆境の姫君を守るがゆえに狂うという「変化形」もある)。奪われた愛を取り戻そうとする、その激しさが人の心を打つのである。私たちは狂女たちの激しい心情けにある種の崇高美をさえ見ることができるであろう。
狂乱とは何ものかによって心が分断され、錯乱し錐揉みしつつも我知らずハイテンションとなった状態である。狂女たちはときに不可思議な「非凡さ」を発揮する。異常によって正常が突如沸騰し、昇華され、純粋な境地にまでいたることによって、それまでたんなる日常(平凡)であったものが足下に沈み、超越の美の域に跳躍するのである。狂気がなければ美は生まれず、狂気が幽玄(美)の縁となることが、狂女物の真骨頂である。
翻って考えてみれば、能の主人公たちは、およそ凡庸な、唯々諾々と日々をすごす私たちのような凡人を抜け出て、その行動において卓越している。逆境が彼らを強くするのだ。能の登場人物はそれぞれに凡庸を抜けて「異常性」を帯びており、平均値から外れた非凡さの持ち主である。「非日常的」な魂の持ち主を題材とする能の世界は、およそ「狂った」人々を描く芸術であり、日常性と非日常性との連接をテーマとする芸術だと考えられるわけである。こうしてみれば、「狂女物」は能における「至花」とも「妙花」とも呼ぶことができるであろう。
狂気を描いた作品の多くは、人間の悲哀のかぎりない多様さと繊細さ、人の心の無垢の美しさ、意表をつく行動の激しさ、執心ということの断固とした決定的な力を描き上げることによって、人間が秘めている不思議な力を描き出そうとしている。ギリシア悲劇には、神の呪いを受け盲目の狂人となったオイディプス王や、命をも顧みず軀となった兄を弔おうと必死に土をかけるアンティゴネーの物語があるが、人間の狂乱の真実をえぐり出したという点で、能の視線とも重なるであろう。また、シェイクスピアは、姉娘たちに裏切られた父リア王の壮絶な狂気を描き上げ、水面に浮かぶ狂気に果てたオフィーリアの姿を描き出したが、彼の描く狂気の主人公たちに劣らない豊穣な狂気の世界を能もまた多彩に描き出したのだ(たとえば、猿沢池に浮かぶ「丹花の唇。柔和の姿ひきかえて。池の藻屑に乱れうく」采女の姿は、オフィーリアを彷彿とさせるであろう)。
「狂女物」とされる作品はそれほど多くない。現行曲を拾ってみれば、「百万」「三井寺」「角田川(隅田川)」「桜川」「柏崎」「花筐」「班女」「雲雀山」「富士太鼓」「蝉丸」「籠太鼓」「鳥追舟」「飛鳥川」「賀茂物狂」などであり、十数曲にすぎない。しかし、いずれの曲も悲哀に溢れているとともに、機知と純心の煌めきを垣間見せており、あわれの情趣に満ちている。
狂女物は、クセのみならず、クルイや段など多彩な歌舞によって飾られた作品が多く、魅力あるジャンルを形成している。まことに「角田川」の渡守がいうように、「狂女ならば面白う狂え」である。狂女物の古型は「百万」や「三井寺」に見られるような親子物狂物と考えられるが(他に、「柏崎」、「隅田川」、「桜川」など)、さらに恋慕を題材とした狂女物(恋慕物狂物。「班女」、「花筐」)、さまざまな苦悩を題材にした狂女物(艱難物狂物。「雲雀山」、「富士太鼓」、「蝉丸」、「籠太鼓」、「鳥追舟」、「梅枝」など)があり、多彩に広がる。(竹本幹雄は、親子物狂物をさらに「追放型」(「雲雀山」など)、「出家型」(「柏崎」など)、「誘拐型」(「角田川」など)に分類している。「親子物狂い考」、一九八〇年、「国語国文学会」)。
第一型の「親子物狂物」は、母が行方知れずの子を訊ねるというストーリーの曲である。現行曲には「角田川」「百万」「三井寺」「桜川」「柏崎」があるが、いずれも母が失われた子を探して旅に出る(「三井寺」のように、霊夢によって三井寺に導かれるという筋立てもある)という形を取り、日常の生活の場から離れるという特徴をもっている。空間的な場の移動が何ものかに憑依された母の心をいっそう引き立てるのである。子を探す母の強い意志、その軋轢による狂気、子を探すための狂乱の舞、これらが他の能では得られない鮮やかな印象と感慨を見る者に与えてくれる。
第二型の「恋慕物狂物」に属するのは「花筐」と「班女」の二曲を数えるのみである。しかし、世阿弥の手になるこれらの曲は主人公の華麗さと悲しさ、詞章の鮮やかさ、舞台の美しさのいずれの点においても卓越しており、名作揃いである。「花筐」は、清冽な狂気を描く「クルイ」、李夫人の物語を謡い上げた幽玄の窮みの「クセ」が印象的であり、「班女」は、加茂神社で祈り舞う狂女の姿、さらに扇の交換の場面が恋の懊悩と成就を描き上げて心を打つ。また、前者は美しい花籠、後者は扇の交換という恋を象徴する飾り物が添えられていることも私たちの興趣をひく。
世阿弥が恋慕物狂の曲として、「花筐」と「班女」を書いたことは注目される。恋慕の二つの形が描かれるからである。それらを表現型恋慕と内面型恋慕と呼べば、恋とはまさしくこれら両極の間を揺れ動くことではないか。私たちの目の前に残されたこれら二曲は人の恋における内外二相を象徴的に描き上げたという点で、稀有の遺産となっている。
第三型の「艱難物狂物」は、親子あるいは恋慕の物狂物に属さないいろいろな境遇の狂女を扱った一連の作品をいう。そこに描かれるシテは、その立場もさまざまであり、狂乱の理由も多様である。「雲雀山」のシテは乳母であり、「富士太鼓」は太鼓の名手の妻、「蝉丸」は盲目の皇子の姉逆髪の君という具合である。艱難のなかにある人がそこから逃げようとしないで、その状況にまっすぐに立ち向かおうとするとき、ひとつの美が誕生する――人はさまざまな困難に遭遇すれば己の日常の安定から放り出されるが、そのなかを生き抜くことによって不可思議な力を獲得してこの艱難の先に新たな生の意味を見出すことがあるということを、これらの作品は教えている。
狂女物において注目すべきは、なぜ狂うにいたったかというその理由がその曲の情趣を性格づけている点である。むしろ、たんなる狂気の振る舞いが見どころなのではなく、狂気がどのような精神的緊張から生まれたのかということがわれわれの関心事であり、このことを見抜いたときそこに美的世界が現出するのである。観世寿夫がいうように、「狂いの場をいかに上手くやってのけるかという事よりも、なぜ物狂いになったのかということと、この女の一貫した感情と行動のほうをまず大切にするべきで、その中からおのずと狂いの場がクライマックスになるはずである」(『世阿弥の世界』、1980年、平凡社)。
狂女物の主人公たちはいずれもが悲しくも美しい。狂女物の曲において、シテは哀しさ、恋しさから心乱れ狂乱するものの、内に秘めた美しさ、芯の強さを滲ませている。まさに世阿弥のいう「秘即花」が狂女物において発揮されるのである。物狂いと幽玄とが対立するのではなく、重なりあい一体となる、ここに狂女物の一番の特色がある。こうして二つの対立する「原理」が融合したとき、能作者の求めた美の世界が誕生するのである。
又、女物狂の風体、これは、とても物狂なれば、なにとも風体を工みて、音曲細やかに、立振舞に相応して、人体幽玄ならば、なにとするも面白かるべし。よそをひを美しく、曲のかかりを工み寄せて、事を尽くし、色を添へて作書すべし。 (世阿弥『三道』)
狂女の出(登場)と扮装は注目される。狂女はその異常性を表わして、華やかな挿頭をさして登場したという(今日では「笹」を持って登場するのが狂女の定型である)。
およそ、物狂いの出立、似合ひたるやふに出立べき事、是非なし。さりながら、とても、物狂いにことよせて、時によりて、何とも花やかに、出で立つべし。 時の花を挿頭に挿すべし。 (世阿弥『風姿花伝』)
狂女の代表的な扮装は、唐織の右袖を片肌脱いで後ろに垂れたように着ける出立ち(ぬぎかけ)である。カケリなどの物狂おしい所作を見せるのにふさわしい扮装である(「雲雀山」「班女」など)。また、長絹を身につけ、頭に烏帽子を被り、縫箔を腰巻に着る出立ち(「百万」「柏崎」など)。狂女は旅をするが、その際には水衣をはおる(『隅田川』『桜川』『三井寺』など)。このような扮装も狂女を醸し出すうえで大切な要素である。
狂いの場は、狂女の苦しみによって日常的な秩序が打ちこわされ非日常的な空間が現出した場である。それを囃す周囲の人間はむろん狂っていない。この落差が狂人をいわば高みに浮遊させるのである。あたかも神に一歩近づいた霊力を得たかのように。また、狂人は長い旅をするが、その道中で物狂の霊力を得るのであろうか。ある地点(寺社が多いが、市井や路上もある)に着いたとき、不思議な霊力が発現して狂乱をおこすのである。そしてこの狂乱が願いを成就に近づけてくれるのである。その意味で狂乱の場はある種の神性を帯び、浄福を回復するという祝祭性を有するのである。――そして、再会(願いの成就)によってその場はふたたび日常の場に帰っていく。
2018年11月23日
執心ということ ――能の詞花を訪ねて5
執心という言葉は私たちにはあまり心地よく響かない。偏執狂、意固地、さてまた
根に持つ
という言い方を想起させる。 昨今は
水に流す
ということのほうが好まれる時勢であるが、いつの頃からそんなふうになってしまったのだろう。 ところが能は、執心が人間にとって欠くことのできない、それどころか人間の品格を表すものであることを教えるのである。 執心とは、ある一つの事柄が心にかかり、あるいは心を覆い尽くして振り払えない状態をいう。そのようなとき、 現代の私たちはすぐに気分転換を図ろうとし、心にかかった事柄にとことんつきあってみようとしないかもしれない。 さて、執心を見つめようとする人と気分転換をはかろうとする人とではどちらが精神的に真摯であろうか。
能の多くの作品は執心を主題としている。とりわけ夢幻能は執心能である。夢幻能は死者がこの世に帰ってくる次第を語る能であるが、 当の幽霊はまさしく執心の化体である。執心がなければ死者はどうして幽霊になってこの世に帰って来るという面倒なことをするであろうか。 そして幽霊は執心を晴らされてあの世に帰って行くのである。執心は能が関心を寄せる最大の主題の一つであり、能の描く内面性とは執心である。
能はことさら執心を愛好し、偏執的な人物や場面をとりあげる。なぜか。人は何かに駆られて、おのれを自失し、信じがたい行為をすることがある。 あることが心を占領し、あたかも事象に連れ去られて行くかのように、自制を超えて一徹に邁進するのである。 そのような忘我にも似た純粋な姿は私たちの心を打ち、美しさを感じさせる。執心とは
憑き物
であるが、この憑き物は何か異物の仕業ではなく、 おのれの前方にある不可思議な磁力のようなものである。執心に駆られた人は自分自身にも知られない導きの糸を我を忘れてたどり続ける。 執心は魂が
憧れ歩く
ことであり、救済への自己誘導だったのである。
執心は精神のテンションの高さの産物であるがゆえに、精神美の一つの形態となることができる。執心の持ち主は現在に生きるのではなく、 過去と未来に生きる。回想が心の住処であり、夢が心の糧である。恋慕は執心であるが、悔悟も執心である。執心に生きるものは、 ある対象に惹かれ囚われることによって、自己を投げ出そうとし、おのれのすべてを捧げようとする。執心は自己コントロールを振り切って邁進する。 その極みは狂気であり物狂いである。他方で、このような執心を鎮めるものがあるとすれば、それは祈りであろう。祈りは執心の対極にある心の状態である。 狂気はいわば執心に乗っ取られた状態であり、祈りはこの執心を無化しようとする没我的行為である。
「執心物」の能の多くは、執心によって狂気や狂乱に陥った人物を主題とし、死後その執心のゆえに現世に立ち戻り、旅の僧や生前の縁者と邂逅し、 生前の苦患を語り、祈りによってその苦患から救われる様を描く。それらの能は、さまざまな対象に取り憑かれた人物を描くが、私には男女のあいだでは 執心の有り様が異なるように思われる。いま便宜的に執心男物と執心女物(狂女物も本来はこのグループに属するが、他の執心物が夢幻能であるのにたいし、 狂女物は現在能である)に分けて、その姿をたどってみよう。
執心男物には次の特徴が看取される。
第一、業と罪への執心 能のなかにはなんとも暗く重々しい作品がある。なぜこのような暗澹たる作品が書かれたのかと訝しく思われるほどである。 殺生、密猟、奇怪な悪事などから離れることができず、その報いを受けて、地獄で苦しむ亡者が語られるのである。 彼らは禁断の行為や殺生を繰り返したために地獄に堕ちるが、自らの非を知りつつ、それでも救いを求めるのである。悪人正機を地で行くような能である。 「阿漕」「善知鳥」「鵜飼」(これら三曲は「三卑賤」と呼ばれる)がその典型的な作品である。なお、執心物には属さないが、盗賊を描いた「熊坂」、 怪鳥をシテに仕立て上げた「鵺」、射殺された後にも石となって殺生を続けた野干を物語る「殺生石」なども烈しい執心を描いた個性的な作品である。
第二、恋慕の執心――執心のもう一つの縁は恋の世界である。かなわぬ恋、許されぬ恋、男の友情と死などが主題の、悲哀に満ちやりきれない思いをのこす能がある。 男の恋慕には粘着力があり、亡者の四周に濃い暗色の紅のイメージが漂う。「錦木」、「通小町」は恋が実現することなく命果てた男を描き、 「船橋」は親に遮断された男女を描く。「松虫」は不可思議な男の友情(LGBTの曲か?)を描く。「女郎花」は男女の行き違いから女が身を投げ、 男も続くという悲恋(三角関係か?)を描き、「恋重荷」は女御を見初めた老人のかなわぬ恋を描く。いずれも恋慕という人間の情動に絡み取られ、 のっぴきならない苦境に沈み込んだ男たちの物語である。「定家」は式子内親王にまとわりつく定家(死後にはテイカカズラとなって親王の墓にまとわりついた)を 題材にした曲であり、これぞ執心物の観があるが、シテは式子内親王の亡霊であり、定家はその表題にもかかわらず登場しない(本鬘物に属する)という型破りの曲である。
第三、執心と諦観――一般に執心物とは見られないが、人の心の深い「こだわり」が闇を突きぬけ、闊達の境地にいたるさまを描いた作品がある。 深い想いが捨身や諦観にまでいたるのである。それは
無念
に通じ、両者は対立的であるように受け取られているが、紙の表裏のように切り離されることがない。 それらの能は人の心の不可思議な深みを描き出しており、観るものに茫然とした感慨を与えるであろう。「木賊」は行方知れずの子を思うあまり、 執心が「酔狂」にまで昂じた老人の物語であり、「弱法師」は逆境の盲目の乞食僧俊徳丸の物語であるが、天王寺を舞台に澄みきった高貴な心と憂愁の想いとが 溶け合った静謐の心を描きあげた曲である。「藤戸」は海の渡しを教えたばかりに斬られた男の無念とその超克を描く。 「芦刈」は貧困に耐える男にも恥と矜持の心があり、妻への恥じらいを失わないという情愛のあわれを描く。 それらは執念が澄みきった諦観を呼び起こすという、逆境の生の展開図ともいうべき作品群であろう。
他方、執心女物は物狂いゆえに日常世界から隔絶してしまった女性たちのあわれと「超常美」を描くことに意が払われる。
第一、懊悩に沈む執心――懊悩とは悩みに身悶えることをいう。自己の思いを行動に表すことが許されなかった世界において、 女性たちはその懊悩を極限にまで内化させる。そのために日常性から飛び出してしまった彼女たちは、いわば純粋心意の世界へと身を翻すのである。 そこに見られる心意は「聖なる執心」というべきものであろう。『源氏物語』から採られた「玉鬘」や「浮舟」は、男に振り回されわが身を自失した (彼らは妄執に駆られ、物の怪に取り憑かれる)貴女のあわれを描き、「求塚」は二人の男の板挟みに身を投げた女のあわれを、 「梅枝」はライバルに誅された太鼓の名手の妻のあわれを謡う(同じ主題の曲に狂女物の「富士太鼓」がある)。いずれの曲も懊悩のあわれが主題であるが、 なかでも「砧」におけるシテ(芦屋の某の妻)のあわれは超絶している。夫の不実とも誠意ともつかぬ仕打ちに中ぶらりんの精神状態に陥り、 砧を夜すがら打ち、「風狂じたる心地して」あっけなく倒れた妻のあわれは筆舌に尽くし難い。
第二、心の混濁が沈殿し、いわば
澱
となって取り除かれ、水や月のごとく澄みきった心意にいたった執心がある。 もはやそれは執心ではなく、何物にもとらわれない清浄の境位にいたった「聖なる追憶」の世界であろう。そのような老女の達観を描いた 「姨捨」、「檜垣」、「関寺小町」はもはや執心女物ではなく、敬意のもとに「老女物」と呼ばれ「秘曲」とされるが、 その澄みきった心の淵に執心の翳りが映されたとき、私たちはかぎりないあわれに心を動かされるであろう。
第三、狂女と鬼女は執心に囚われた女たちの果の姿である。執心が狂気(狂女)となり、鬼(鬼女)となるのである。 しかし、能の大きなジャンルをなすこれらの「狂女物」と「鬼女物」については別稿で考えるとしよう。
2018年10月25日
能と和歌 ――能の詞花を訪ねて 4
能の舞台には美的表現方法が集積している。野上豊一郎によれば、「能楽は詩と音楽と舞踊の総合芸術である」。能は詩でもあるのだ。詩の美しさは、言葉の妙のみならず、律動と響きの快さでもある。能の詩は、「あらゆる日本語の律動の美しさのもっとも優秀なものになっている」(「能楽概説」、『能楽全書』第一巻)。ところで、日本の詩を代表するものはなんと言っても和歌であろう。そして能に美しい詩的表現が見られるのは、それが和歌の遺伝子を受け継いでいるからである。
和歌が能に与えた美意識は余情と幽玄であろう。余情は心に残って消えない気分や情緒のことをいい、歌に言外の情趣があることを意味する。そして余情の最奥の趣が幽玄である。「幽玄こそ実に中世の歌道を貫く美意識であり、能楽美の理想であった」(峯岸義秋「謡曲と和歌」、『能楽全書』第三巻)。世阿弥は「ただ美しく柔和なる体、幽玄の本体なり」といい、能のすみずみに柔和な美しさとしての幽玄があふれることを説いているが、それを与える源泉が和歌なのである。それゆえ彼は、「言葉の幽玄ならんためには歌道を習ひ、姿の幽玄ならんためには…美しく見ゆる一かかりを持つ事、幽玄の種と知るべし」(『花鏡』)という。世阿弥は能の美を歌道の幽玄論から汲み取っているのである。
能と和歌とは相即不離の関係にある。能の詞章を育み、その表現を豊かで味わい深いものにしているのは和歌であるといっても過言ではない。峯岸は上の書で、「和歌的美と和歌的精神とを最も鮮やかに顕現しているのが物語と謡曲とである」とも述べている。『源氏物語』のストーリーが和歌とともに進行することをわれわれは知っているが、謡曲もまた和歌が織り込まれ、和歌によって生気が与えられる世界なのである。じっさい、能の詞章は和歌の様式に倣っており、その心も万葉古今を受け継いでいる。あるいはむしろ、能の情緒は『新古今集』のそれと大いに重なるのかも知れない。
それだけではない。一曲の能そのものが一篇の長歌である。それはあたかも舞台に映現した一首の和歌であり、歌の言葉が衣をまとい、生きた姿(シテ)となって動き出した世界である。さながら能の舞台は、和歌が舞台に変換されて、その心を語り出したかのようである。私には、現在物や鬼神物の作品を措いて、およそ一曲の能はたんなる劇でも物語でもなく(一般に能は音楽劇や物語と見られているが、物語にしては能のストーリーは単純にすぎる)、むしろ一幅の心象風景の描写であり、音楽化され映像化された和歌であると見たほうがよいと考えている。
世阿弥の能には、とりわけ和歌の心が息づいている。その詞章には縦横無尽に和歌が取り入れられ、和歌が讃えられ、和歌的手法が駆使されている。彼は、能は歌道(和歌)にしたがうべきだという。和歌から「風月延年のかざり」を受け継ぐのである。また彼は、能とは万物のなかに流れる歌の心を汲みとり再現したものだとも述べている。彼が作曲した「高砂」には次のような章句がある。
有情非情のその声。みな歌にもるる事なし。
草木土砂。風声水音まで万物をこむる心あり。
はるの林の。東風に動き秋の虫の北露になくもみな。
和歌のすがたならずや。 (高砂)
また他の所では、「ただ、優しくて、理のすなはちに聞ゆるやうならんずる、詩歌の言葉を取るべし(ことばが優美で、道理が即座にわかるような歌の言葉を選ぶべきである)。優しき言葉を振りに合わすれば、ふしぎに、人体も幽玄の風情になる物也」とも語る。能を演じる者は歌道の嗜みを心得てはじめて、本当に自在に舞い謡うことができるようになる、と説いているのである。
金春禅竹もまた和歌の心酔者である。彼は、『歌舞髄脳記』において、「それつらつらこれを思ふに、歌は此道(申楽)の命也」と述べている。彼は、能においては歌と舞とは一心だという。そして能の歌は歌道を師範とするという。
かれこれ思ふに、歌舞一心の曲味なり。此心を悟り、此位をわきまへ知らん物は、歌道を尊ぶべし。…此神楽の家風(能の家)に於ひては、歌道を以て道とす。歌又舞なり。此歌舞、又一心なり。形なき舞は歌、詞なき歌は舞なり。…詠曲して舞(まひ)うたふこと、無上幽情の感などかなからん。恐らくは、この心を悟り知らざらん事を。ただ、心深く、姿幽玄にして、詞卑しからざらんを、上果の位とす。
世阿弥や禅竹の能には、一曲のなかに十数首の歌が詠み込まれている作品がいくつもあるが、他方で後世の能作者の作品で歌がまったく引かれないものも多くある。能への関心と手法が変化し、和歌的情緒から劇能的関心に移行したことがその理由に考えられるが、何よりも戦乱の時代を迎えて文芸的精神が後退し、和歌的な抒情も教養も衰えていったことが一番の理由であろう。この意味で、和歌の美を駆使した作品群は能の文芸的精神の高揚の記念碑的な意味を有しているのである。
和歌が一曲の魂というべき情緒を与え、その息吹を受けて余情と幽玄にあふれる卓越した作品がいくつもある。「高砂」はその主題に万葉古今の讃歌を掲げた曲であるが、「井筒」、「定家」、「西行桜」、「江口」、「関寺小町」などは和歌と能が一つに融け合い、それぞれ至高の幽玄の世界を描きあげた名曲である。そこに表され出た美的境位は日本の文芸的意識の自己規定というべき水準を示していよう。また「杜若」や「松風」や「草紙洗小町」のように、一首の和歌を主題とし、律動的な歌物語に仕立て上げた好もしい作品もある。さて、次の相聞歌ほど美しい抒情を能の世界に与えたものはまたとないであろう。
筒井つの井筒にかけしまろがたけ たけ過ぎにけらしな妹見ざるまに くらべこし振分髪も肩すぎぬ 君ならずして誰かあぐべき
(伊勢物語 二十三段)
*「井筒」では「つつ井筒井筒に懸けしまろがたけ 生いにけらしな妹見ざるまに」 と謡われる。
紀貫之、在原業平、和泉式部、小野小町、西行などの歌人をシテやワキに登場させ、彼らの歌を主題とした謡曲にも情感にあふれ、詩興を催させるものが少なくない。「蟻通」「雲林院」「小塩」「東北」「卒塔婆小町」「鸚鵡小町」「雨月」「遊行柳」などは、いずれも歌人の歌を能のなかに巧みに取り入れ、和歌的な情趣を舞台に漂わせる興味のつきない曲である。
和歌も能も、「人のあわれ」と「もののあはれ」を鑑賞者の心に再現することをめざしている。それらが相手とするものは、ものごとの情景のなかに映し出された人の心である。紀貫之は『古今集』の仮名序において、歌は人の心を慰めるために言の葉となって心よりあふれ出るものだと説いている。
やまとうたは、ひとのこころをたねとして、よろづのことの葉とぞなれりける。…ちからをもいれずして、あめつちをうごかし、めに見えぬ鬼神をも、あはれとおもはせ、をとこ女のなかをもやはらげ、たけきものゝふのこゝろをも、なぐさむるは歌なり。
「やまとうた」を「能」と置き替えれば、貫之のこのことばはそのまま能についての説明となるであろう。
2018年9月25日
能と物語 ――能の詞花を訪ねて 3
能の多くの作品は、『伊勢物語』や『源氏物語』、『平家物語』などの物語作品から主題や人物を取り上げている。 能と物語文学とは切っても切れないつながりがあるのだ。能に先立つこれらの物語文学は、爛熟した貴族文化と仏教文化の産物であり精華である。 日本の文化はこの時代に一つの精神的−美的高地に登りつめたが、物語文学はその代表の一つである。
その背景には400年におよぶ平安王朝の「鎖国」的内向化があり、その間に個性的な文化意識と美意識が高度に発展し、 今日の日本人にまで通用する独特の自然感応の心が研ぎ澄まされたのである。日本的美意識の大きな原型がこの時代に育まれたと考えてよい。 それは情感と悲哀の意識であり、大きな流れに翻弄される人間の儚さに心を動かされる感性的意識であり、その美的表現であった。
物語文化の興隆はこのような日本的美意識に支えられている。 異国情緒の漂わなくもない『竹取物語』が、物語の劈頭から終結部にいたるまで論理的根拠を超えた大きな超越的状況のもとでの 「人間の小さな営為」を描くことを特質としていたが(なぜ竹から生まれたのか、なぜ月に帰るのかは「人智」を超えており、問われない)、 この「構え」はその後の物語文学に受け継がれたのである。
『源氏物語』はこのような物語文化の頂点であるとともに、古今東西の文学の最高作品の一つである。 そこには驚異すべき日本的美意識の精髄が凝縮されている。その意表を突く展開、主人公たちの懊悩ぶり、 さらになによりも繊細を尽くし、抒情に浸された文章が私たちを魅了する。他方で、『平家物語』は初期の武家社会らしい素朴さと無骨さを残しているが、 仏教的無常観に貫かれており、もう一つの日本的心性を醸成する縁となった。なにより、平家一門の滅亡の物語は人々の心に強烈な無常観とあわれの意識を植えつけた。
能には『源氏物語』を題材にした卓越した作品がある。『源氏物語』は、能が舞台に幽玄の抒情を、そして美しい女の風姿を描きあげようとするとき(鬘物)、 格好の題材を提供するのだ。『源氏物語』をつらぬく「物のあわれ」から能の世界を見直すとき、能における「幽玄」とは、模糊としたたんなる情感的な朧を意味するのではなく、 物の摂理とそのまえに翻弄される人間の悲哀に裏打ちされたあわれを描くためのキーワードだということに気づくであろう。
『源氏物語』はたんなる光源氏の女性遍歴(いろごのみ)の書ではない。紫式部が伝えようとしていることは、 出来事や色事という表層の深部には人それぞれが負わなければならない非情の流れ(宿世)があり、それが各人の生き方に翳り(有情)を与え、 その世界に物のあわれを漂わせている、ということに他ならない。とりわけ懊悩に苦しむのは高貴な女性たちである。 物語はむしろ彼女たちのあわれの生き方をたどり、そこに救済の光(女人往生)を見出すことに眼目を置いていたと言うべきであろう。
世阿弥は、「女体の能姿」を描くことが「舞歌の本風」だとして、その題材を『源氏物語』に求めている。
女体の能姿、風体を飾りて書くべし。是、ことに舞歌の本風なり。その内に於きて、上々の風体あるべし。 あるいは女御、更衣、葵、夕顔、浮舟などと申たる貴人の女体、気高き風姿の、世の常ならぬかかり、よそをいを、心得て書べし。 長けたるかゝりの、美しくて、幽玄無上の位、曲も妙声、振り・風情も此上はあるべからず。少しも不足にてはかなふべからず。 かやうなる人体の種風に、玉の中の玉を得たるがごとくなる事あり。如此の貴人妙体の見風の上に、あるひは六条御息所の葵の上に付祟り、 夕顔の上の物の怪に取られ、浮舟の憑物などとて、見風の便りある幽花の種、逢ひがたき風得なり。
(世阿弥「三道」)
能の現行曲には、「半蔀」「夕顔」「葵上」「野宮」「須磨源氏」「住吉詣」「玉葛」「落葉」「浮舟」「源氏供養」などが伝わっている。 これらは、物語のなかのある場面を切り出して、その抒情を謳い上げようとするが、その多くは後日談として描かれている。 主人公は、後の世になって旅人の前に亡霊として現れ、その胸の想いを語り、救済を求めるという夢幻能の定型のもとに描かれるのである。 これらの現行曲が取り上げる女性(シテ)は、夕顔、葵上、六条御息所、明石君、玉葛、落葉宮、浮舟であるが、藤壷、紫上、女三宮、 大君たちは残念ながら能の現行曲として残されていない。彼女たちが能のヒロインになっていれば、どのような世界が繰り広げられたことであろうか。
他方で、『平家物語』は平安時代の貴族文学と異なり、中世における武家の文学である。 およそ文学は人間の生きざまをその深奥から描き出すときに名作となるが、『平家物語』は打ち続く苦患の戦いと敗者の苦悩と無念、 人間の駆引き愛憎を主題としており、無数の人物群像がこの宿命に絡みとられるさまを一篇の壮大な叙事詩として語り出す。さながら修羅の大海が描き出されるのである。
平家滅亡の悲哀の歴史は日本人の魂の奥深くに浸みこみ、私たちの無常観と流水のごとき生き方に縁を与えてきた。 物語にちりばめられた数多くのエピソードは詩的イメージの宝庫となった。武家社会の始まりを象徴する歯切れのよい文体は、日本語を詩的言語にするとともに、能作品の豊かな源泉となった。
能には「負け修羅」という分野があるが、そのほとんどは幾重もの苦難のなかに滅んでいく平家の武将たちを描き出そうとした能である。 西海に沈んだ平家の公達を描く能は多くある。「忠度」「俊成忠度」「経政」「清経」「敦盛」「知章」「通盛」「小督」「舟弁慶」など。 また、それぞれの末路へとたどる人物たちの能には、「祇王」「俊寛」「頼政」「実盛」「巴」「兼平」「千手」「藤戸」「正尊」「盛久」 「奈良詣(大仏供養)」「景清」「小原御幸」「熊野」(「鵺」のような怪鳥の物語もゆかりの能である)と数多い。
また、『平治物語』や『義経記』から採られた曲には、「朝長」「鞍馬天狗」「烏帽子折」「熊坂」「橋弁慶」「八島」「吉野静」「二人静」「安宅」など、興味深い能がずらりと並ぶ。
能が扱う題材は、武骨であってはならない。世阿弥は修羅物を好まなかったが、敗者であり、貴人の教養があり、詩歌を愛する平家の武人たちには心を許したようだ。 世阿弥は武将たちの舞を軍体と呼んだが、その要点を「
体力砕心
」(力のこもる身体的動作を主体としつつも、細やかな心遣いをすること)と言い表している。
又、軍体、「体力砕心」〈力ヲ体ニスル、ソノ心ヲクダカンコト、大事也〉と名付。力を体にして心を砕く所を、 よくよく心人(心身に同じ)に宛てがゐてさてその態をなさん事、是、軍体の我意分なるべし。軍体は、
凡
修羅の風体なれば、 はたらきと
者
、弓箭を帯し、打つ手、引く手、うけつそむけつ、身をつかいて、足踏も、
早足
(軽快な足さばき)をつかふ心根を持ちて、 さて、人ない(身の保ち方)をばなだらかにして事をばなして、さてあらかるまじき堺をよくよく心得てはたらくべし。是、軍体の我意分なるべし。
(世阿弥 拾玉得花)
彼らがたんに敗者として冥界に堕ちることが語られるのではなく、その心根が描かれることが肝要であり、 魂がふたたびこの世に帰ってきて生者と心を通わせることが修羅物のあわれなのである。平家の能はまったく個性的な敗者=死者の救済の物語である。 能は没落して行くものが、救われ、成仏することを描く芸術であるという性格を有するが、平家の公達はまさにそのための格好の題材だったのだ。
2018年8月11日
死者の来訪と能 ――能の詞花を訪ねて 2
能の詞章を鑑賞するに先立って、いますこし序論的考察を続ける。
能の多くの作品は夢幻能(複式夢幻能)と称せられる。前場で旅の僧の前にいずこからともなく若い女性(たとえば里女)が現れ、故事を仄めかしたと見るや忽然と消え失せ、後場で亡霊の本体が往時の姿で登場し、昔を懐かしみ、僧と語り合ううちに夜はしらしらと明け、亡霊の姿も消えていくという筋書きの能であり、いわば基本形の能である(たとえば「井筒」)。このような一見風変わりな物語構成をもつ能が日本人に受け入れられ、長く愛好されてきたことに、私は少なくない驚きを感じる。
能は死者と異界の存在(神、精霊、天狗、悪鬼など)の芸術である。とりわけ能の作品の多くが幽霊を主人公(シテ)にしており、死者と生者が語り合い、交感しあうという筋書きをとる(死者を扱わない能をわざわざ「現在能」と呼ぶ)。それらの能が描こうとする主題は、執念や未練をもってこの世界から去っていった死者のあわれのこころである。死者は敗北の無念や恋の挫折、親子の別れなどといった苦しみ(執念)を抱えたままあの世に逝くが、それらの執念を晴らそうとしてこの世に戻ってくる。そしてその執念は、生者と語り、あるいは僧の祈りを受け、あるいは歌舞を舞うことによって晴らされ(成仏し)、あの世に帰ってゆく。
死者の執念とは何だろうか。死にゆく者は死んでも死にきれない何ものかをこの世に残したまま、後ろ髪を引かれる思いで死んでいくのである。死とはこの世からの振り切りであるが、人はこの振り切りを完成させないまま、三途の川を渡らなければならない。そのような死者はこの世に帰ってきて、生者と語ることによって救われるのである。この意味で能は死者の語りの芸術である。
幽霊や精霊や神や鬼や天狗という超越的な存在が主人公(シテ)として登場する芸術は、ほとんど他に例を見ない、世にも稀な異界の来訪者の芸術である。能面は、これらの異界の存在者を表すためにとくに発達したということができる。そのなかでも幽霊は、能を特徴づける中心的な存在である。それでは、この幽霊たちとは誰か。人々の記憶に留められた過去の英雄や貴女たちである(草木鳥獣などの精霊も「準−幽霊」と見ることができよう)。かつてこの同じ世でわれわれと同じ喜びと苦悩を担った魂たちである。人間の情念が異界の世界の住人となってもこの世に執着し、かつての姿をとどめつつ(霊化された姿となって)能の舞台に還ってくるのである。それは死者の執念であるとともに、死者を想起する生者の執念でもある。執念において生者と死者とが交感し、往時の世界が意味づけられるのである。それでは、生者と死者を結びつける執念とは何だろうか。それは死者が体験し、生者に伝えなければならない「大きな記憶」ではないのか。人間にとって手放すことのできない「大きなもの」がかつて存在した。この「大きなもの」は記憶にとどめられなければならない。そのために幽霊はこの世に帰ってくるのだ。この「大きなもの」が能の主題となる。「井筒」では幼少期に抱いた
淡い想いの記憶
というものであろうし、「実盛」では老いても手放すことのできない
武士の矜持
というものであろう。
能におけるこのような個性的な構成法は、人は、過去の人々を精神的存在に昇華させて現世に呼び戻すことによって、ともに生きているのだという思いを満たすことができるという、人間のもっとも深い真実を伝えるために、編み出されたのであろう。過去の時代から精神的なものが生き続けており、事象の違い(
色
)や時制の差(流転)を超えて過去と現在とが同質のものを保持しており、精神の普遍性が保たれているという思いが能という場に身を結んだのであろう。人は過去の世界との連続性を体得しなければ、刹那的な現在の欲望に巻き込まれておのれの精神をも見失わざるをえないという余儀ない洞察が死者の芸術を生み出したのである。
中世社会は末法到来の宗教的緊張のなかにあった。民衆の生活の苦しみと戦乱や災害や死への恐怖が新しい宗教を呼び起こした。そして鎌倉仏教の精華が民衆の心に浸透したとき、中世芸術もまた開花したのである。室町期に開花した能はそのような仏教文化の産物だといえなくもない。能の思想は仏教から大きな影響を受けている。無常、仮の世、輪廻、生成流転、厭世、成仏、浄土といった一般的仏教観はあらゆる作品に満ち溢れている。とりわけ、能の心に深く刻みつけられた仏教的痕跡は、法華経思想と真言密教と山伏修験道において顕著であり、それらが神道の影響と溶けあって(両部神道)、能における独特の宗教的雰囲気を築き上げている。とりわけ法華経の影響が色濃く見られることは能の性格を考えるうえで重要である。能は悲劇ではない。現世では苦しみや葛藤を受け、執念から離れることができない人間が最期には仏に救われる(むしろ執心を残したまま冥界に堕ちた魂がこの世に戻ってきて生者(たとえば旅の僧)の祈りを受けることによって成仏する)ことを謡う救済劇である。一切のいのちあるものは成仏するという法華経の思想が能の構成法にまで取り込まれているのだ(亡者は幽霊となって成仏する!)。草木国土悉皆成仏は能が受け継いだ生命讃歌の思想である。
日本の神々もまた能の「守護霊」としてさまざまな作品で活躍する。春日、賀茂、伊勢、住吉、宇佐、熊野などの神社も能のゆかしい舞台である。能の原点は「翁申楽」であるが、「翁」は申楽の成立以前から伝わる日本の歌舞の原点となる祭祀的作品であり、天下太平五穀豊穣を祈る神聖な(地霊神的な)祭礼である。また、脇能は神による寿ぎの能であり、舞台を聖なる空間として予祝する。「高砂」「弓八幡」「養老」「老松」「加茂(賀茂)」「竹生島」などの作品は、能が祝言から始まり、神々への帰依から生まれたことを謳う作品である。春日若宮御祭は、1136年から始まり、猿楽や田楽の興りを促した現存する最古の祭礼であるとともに、能の生誕の場である。また、興福寺の薪猿楽(薪能)は1255年以前に始まっている。これらは大和における祭礼能(大和猿楽)が能の起源であることを伝えている(同時代に近江申楽などがあり競い合ったが、大和申楽のみが今日まで伝えられた)。
私たちのうちには日本の大地に眠る精神的種子が遺伝子のように脈々と受け継がれている。今日、本当の日本美を再発見しようとする機運が起こっていると考えたい。そのとき、日本美には生命の救済の思想が裏打ちされていることを思い起こすべきである。忘れかけた感性を取り戻すことは容易ではないが、心の底には失われないで眠っている感性がある。日本美が蘇ったとき、生命の救済という日本文芸の琴線もまた私たちに親しいものとなるだろう。
2018年7月28日
詞の花ということ ――能の詞花を訪ねて 1
『詞花和歌集』という勅撰和歌集がある。和歌を詞(ことば)の花と讃えて名づけられた名前である。能もまた詞花の世界である。能の舞台には美しい能面、装束そして舞が繰り広げられるが、見所に響く謡や語りのゆかしい日本語もまた美の世界なのだ。
能はわからないという声を耳にする。中世室町期の日本語がそのままで謡われるのであるから、古文の授業をいきなり聞いているようなものであり、わかりづらいのは仕方がない。そのうえ、現代とはずいぶん異なる当時の生活と文化がそのまま舞台に浮かび上がるのであるから、別世界に放り出されて面食らったような印象を受けるのは当然である。時代劇のドラマのように現代風にアレンジされているわけでもない。能を観るときには、生(なま)の中世の人物と文化を目の当たりにしているのである。このことは能のわかりにくさの原因でもあるが、六百年以上前の世界に肌で接することのできる芸術は他に例がない。私たちは能を観るとき、至上の過去の世界を旅しているのであるから、最初の違和感はむしろサプライズとして受けとめたほうがいい。
幸いなことに能の詞章は古文の入試問題ほどには難しくない。少し慣れれば、不思議なほどに今日私たちが語る日本語と同じように聞こえてくるだろう。そして親しむにつれて、旅の列車で聞こえてくる地元の人々の会話がなつかしく心をそそるように、その息遣いがいきいきと伝わってくる体験を味わうだろう。同じ魂が通っているからである。なによりも能の詞章は美しい。私たちの祖先がこんなに美しい日本語を語っていたのかと感動させられるのである。
能は、武家の時代がようやく成熟し、新たな美意識と芸術文化(室町文化)が興隆するなかで確立した芸術である。そこには新しく誕生した鎌倉室町期の武家文化と遺伝子のように受け継がれてきた平安期の貴族文化とが渾然一体となった奇跡の造形が畳み込まれている。その美しさの背景には、とりわけ王朝時代と武家の草創期の時代の日本文学がある。能は平安、鎌倉期の物語や和歌集の文芸に直結しているのだ。この、能の根っこというべき文芸の源泉に立ち戻れば、能はその瑞々しい衣を纏って私たちに美の
花筐
を贈り届けてくれることであろう。
これから私たちは能の詞花を訪ねる旅に出かけよう。本欄で案内する企画は、能のことばをその故郷である古典文芸の作品から眺めてみようというものである。それらの作品を繙きながら能の詞章を読み返してみることによって、能のことばに新しいいのちを蘇らせたいのである。能はなぜ室町期に興ったのだろうか。平安期に日本文化の原型が、とくに物語や和歌が高度に開花したが、貴族社会の没落、さらに平家の滅亡と武家社会の誕生という、歴史の大転換が新しい文化興隆の機運を生み出した。また災厄時代の到来と言うべき、たび重なる天変地異は人々の心に自然への深い畏怖の念を刻んだに違いない。とりわけ、鎌倉期は末法到来という精神的緊張のなかで偉大な宗教改革者たちが活躍し、日本仏教をはるかに高い段階に引き上げた。この文化エネルギーが次の室町期には、美的な芸術へと結晶し、さながら芸術の時代を誕生させたのである。室町文化は武士文化でありながら、都の文化であり、北山文化や東山文化と称せられ、書画や建築、庭園とならんで、能(申楽)の文化も開花したのだった。
能は「幽玄」の芸術であるといわれる。幽玄には静寂玄妙の幽玄と優麗典雅の幽玄とがあるが、能の幽玄は後者である。世阿弥は『花鏡』において、「幽玄之入境事(幽玄の境地に達すること)」という箇所で次のように述べている。
幽玄の風体の事、諸道・諸事に於いて、幽玄なるを以て上果とせり。ことさら当芸に於いて、幽玄の風体第一とせり。
およそ芸術において「幽玄の風体」ということがもっとも肝要だというのである。一般に幽玄は「微かで奥深く暗い」というイメージで受けとられているが、世阿弥はそのようには受けとっていない。もともと幽玄は優美な姿を表すことばであり、歌論において俊成や定家らが優艶、静寂、余情という歌の境地を表すために使い始めた言葉である。和歌によって醸成された幽玄美が能の革袋に流しこまれ、新しい美酒となったのである。
能は花の芸術である。世阿弥は申楽を「花の比喩」で語る。花の本当の美しさはたんなる華やかさにあるのではなく、老木に咲く花、盛りを過ぎて萎れた花にあるという。また花の美しさはその外見にあるというより、不意に表れ出た面白さと奇しいめずらしさ、はっとさせるその瞬間性にあるという。舞台の花、能面の花、装束の花、筋の花、主題の花…、能はまさに花の世界である。しかしその花は葉陰に隠れていなければならない。旅人は不意に花を見つけて驚くのである。そして何より、詞(ことば)のなかに花を見つけて驚くとともに吐息をつくのである。
秘すれば花なり。秘せずば花なるべからず。 (『風姿花伝』)
また能は気の芸術である。能舞台は静と動が拮抗する緊張の世界である。静のなかから動が生まれるとき、気合いと気迫が込められ、次の瞬間その緊迫が弾ける。気とは動を生み出す静だったのである。この気によって、能は厳格な八拍子のリズムにのって、掛け声のかかった打楽器と独特の地声で謡われる地謡が競合して張りつめた音響空間を造りあげる。気とは心根のことであろう。世阿弥は「心根を知る」という。詞(ことば)は気の発露である。何気なく謡ってはいけないのである。
心根を知るとは、 出息 ・ 入息 を地体として、声を助け、曲を色どりて、不増不減の曲道に安位する所なり。 (『申楽談儀』)
能は愛と狂気の芸術である。多くの能の物語において夫婦愛、親子愛、恋愛が語られる。いずれも精神的に高められており、直接的な肉体的表現はまったくない。愛を観念的に表現するという点では能に勝る文学芸術はない。愛と狂気は一体である。能には多くの狂乱物(狂女物)があるが、それらは愛を原因にするものがほとんどである。いずれも激しい精神的葛藤を描きあげるが、その表現は美的に昇華されており、狂者が愛すべき存在であることを美しく謡いあげるのである。能は愛の詞(ことば)によって花の芸術となるのである。
能は女人往生の芸術である。能を美の芸術とするものは、とりわけ老若の心美しい女性たちである。能の最高作品は老女物であり、一日の能の中心は葛物(シテが若い女性)である。男尊女卑の世にあって、能作者たちはなぜ女性たちの宿縁を描くことができたのであろうか。陽の歴史の裏側にある陰の存在が救済されること、ここに能の表現の真意があり、さらに日本文芸の魂というべき陰翳の思想が見られるのではないか。花の美しさはその翳りにあったのだ。「平家物」の能は敗北した男たちの修羅を描くが、そこにも美しい、あるいは気丈な女性たちが活躍する。「源氏物」の能は高貴でありながら社会の陰に押しやられた女たちの悲しさを謡い上げた。
能は謡う。生成流転の綾の世界を流浪する人の心の沈潜と高揚を。神男女狂鬼の乱舞となって、能は尽きることのない詞花の花園に私たちを導くのである。